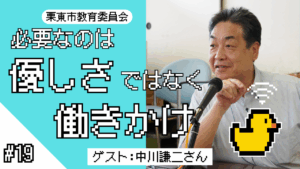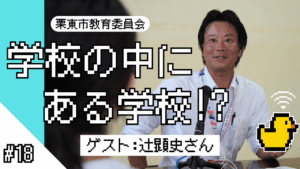本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第21回はゲストに栗東市教育委員会の辻顕史さんと中川謙二さんをお迎えしています。今回は、前回の続きから、学校ならではのハーバールームでの取り組みについてお聞きしていきます
ハーバールームについて
(1)なぜハーバールームが必要なのか?
子どもたちは、学校で教科の学習や学級活動、行事、あるいは部活など通して、様々なことを学び、成長して いきます。 そして、学校が用意したカリキュラムだけではなく、学校に集まった多くの人との交わりを通して、人格を鍛え、社会の一員として活躍するすべを身につけていきます。 確かに人と共に何かを成し遂げること、人と共感し合うこと、それは”ひとり”では 味わうことのできない大きな感動とよろこびを与えてくれます。
しかし、未熟で思春期にある子ども同士のふれあいは、時には、繊細な心を傷つけることや、かけがえのない個性を排除すること、そして苛酷な努力や変化を教師以上に期待することもあります。一旦傷ついてしまった子どもたちは、まさに荒波の中を航海し続ける一般の船のようです。帆がおれても、船体に穴があいても、航海し続けるしかありません。本校では、そんな子どもたちのために、港(ハーバー:harbor )を用意しました。そこは“ドック”のように大々的な修理をする場所ではありません。しばし、荒波から逃れ、新たな航海に向けて、本来の力を回復させ、新たな航海に向け て態勢を整えるためのささやかな入り江…それがこの「ハーバー・ルーム」なのです。
私たちは、これまでのハーバールームでの働きかけを通じて、子どもたちは、
1.プレッシャーや集団から解放されるだけで、本来の明るさを取り戻すこと、
2.最終的には孤独ではなく、適度な人とのふれあいを求めること、
3.適切な教師の働きかけやルームメイトとのふれあいによって、コミュニケーション能力を高めること、
に気づきました。
(2)ハーバールームの使命と活動
ハーバールームの使命(目的)は、教育活動の一環として、個々の生徒の特性に応じた支援を行い、将来的な自立に向けて力を高めることです。そのために、ハーバールームでは、以下の取り組みを進めます。
1.登校から下校まで、一人ひとりの学校生活を見守ります。
2.個別の学習や活動の場を保障しつつ、ルームメイトのふれあいの機会を設けます。
3.生徒支援部が必要な支援や課題を考え、日々の運営はサボート支援員が行います。
4.全教職員が、利用生徒の教科指導(一日2時間)を分担して受け持ちます。
5.利用生徒と担任の絆をサポートします。
6.利用生徒へのカウンセリングやSSTをSCが行います。
7.いじめや暴力被害にあった子どもの安心安全を守ります
※『栗東市立栗東中学校 校内支援教室「ハーバールーム」 利用のしおり』より抜粋
前回の記事はこちら
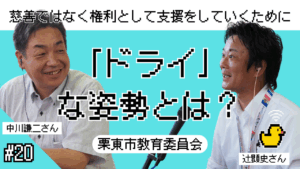
前回からの続き
 井ノ口
井ノ口・・・学校は学校で、経済状況や人種などに関わらず、すべての子どもが平等に教育を受けられることを目的とした、とても大切な場所だと思います。
でも一方で、全員が同じリズムで、同じ形で学び続けられるわけではありません。だからこそ学校の中に、もう少し柔らかい仕組みや、子どもたちが自分のペースで居られるような場所が必要なんじゃないか。そういう意味でも、ハーバールームのような取り組みはとても価値があると感じました。



そうですね。ハーバールームが「学校の中にある」ことは大事だと思います。



学校が「ダメ」というわけじゃなくて、学校も変わっていっているとも思いました。
私自身も、実は不登校にはならずに、中学も高校も普通に卒業したんですけど、ずっと「学校ってあんまり好きじゃないな」「全然楽しくないな」と思っていました。
毎日「どうやったら休めるかな」と考えて、仮病を使ったこともあります。でも結局、親に「車で送るから早く乗りなさい」って言われて、校門の前で降ろされる。そういう中高生でした。
でも今振り返ると、気にかけてくれていた先生もたくさんいたな、とも思います。特に体育の先生なんですけど、その先生がなぜかヨガの授業をしていて。「シャバ―サナ」というポーズがあるんですけど、いわば15分くらい横になって休む時間なんです。「みんな疲れてるだろうから、寝ていいぞ」って。そうやって寝かせてくれる授業があって。
そのときのことを、台本を書きながらふと思い出しました。私はずっと「学校なんて行かなければよかった」と思っていたけど、実はそうじゃなくて。学校以外の場所をすごく求めていたのは確かなんですけど、でもやっぱり「学校も学校で大事なんだな」と、今は思うんです。



かつて平成の初めごろ、不登校を受け入れる団体と学校教育とでは、価値観があまりにも違っていました。
辻さんが「もう一つの学校を学校の中に」とおっしゃっていましたが、僕らもそのイメージを持っていました。全く違う仕組みを持った学校を作るということは、Windowsの中にiOSを入れてしまうようなもので、共存できるのか?という感じだったんです。
けれども「外から学校を叩いてもびくともしない。でも中から改革することで変わっていく」という発想がありました。
例えば今回、辻さんが取り組んでいる児童生徒支援室事業。対象は不登校の数十人、という見方もできますが、栗東市では全児童・全保護者を対象にしています。
そのきっかけになったのは、以前話に出た「ポートルーム」です。そこでは、子どもを送り届けてくれる子や、給食を届けてくれる子がいた。頑張って応援してくれる子どもたちがいたんです。だけど、よく考えるとその子たちも何か抱えている。つまり、本来なら支援を受ける側になっても不思議じゃない子どもたちが、支援する側に回っていたりするんです。
そう考えると、この部屋の存在は、実際に利用している子どもだけじゃなく、学級の中で耐えている子どもたちにとっても“保険”になる。自分が本当に行けなくなったとき、どうしたらいいかを知っておける場所になる。
僕は「不登校」というのは、恥じることではないと思っています。当然のこと。怒ることでもない。そういう観点で見ると、教室の中でギリギリの線で耐えて通っている子もたくさんいるわけです。本当はもっと力を抜いて来てもいいのに、と思ったりします。
実際、ポートルームを最初に作ったときに用意したのは「パンフレット」でした。入口に置いておいて、どんな子どもでも手に取れるようにした。そうしないと「なんであの子だけ特別扱い?」というジェラシーが生まれて、意地悪が起こるからです。だから必ず「校長先生の許可があれば誰でも使えます」と書きました。



私が担当していた時は、パンフレットはなかったですが、実際誰でも使えるし、ちょっと教室から足が止まったら、ハーバールームを案内していましたね。



学校のすぐそばにあるからこそ、子どもたちの「次のイメージ」につながるんです。半透明で見えるか見えないかくらいの仕組みを学校の中に作っておきたい。そう思っています。そういう意味では、本当にハーバールームや子どもたちのことを、担当の辻さんがみんなにオープンに話しているのはすごいことやなと思います。



子どもも一緒に成長したと思いますね。僕が担当になったときには、もともとハーバールームに通って子もいたんですよ。前の先生が退任されて、頑張ってくれて。その子たちからすると、担当が変わったのは衝撃やったと思います。
でも、僕は生活指導の担当として授業にも入っていました。生活指導の先生が授業に加わるのは、このシステムの良さで。1日10コマのうち2コマくらい入ることもありました。僕もその一環でずっとハーバールームに授業に行ってたんです。
だから、とっつきやすかったみたいで。前の先生がいなくなったことで子どもたちは最初戸惑ったみたいですが、すぐに打ち解けられました。
そこから「もっと人数増やそうか?」って言うと「えー」って言われたりもして(笑)。でも僕は「いや、やっぱみんなの部屋やから、いろんな子に来てもらいたい」って思っていて。実際10人くらい引っ張ってきたんです。そうすると一つの集団ができる。不思議なもので。



鳥の巣と同じでね。雛鳥って、最初から仲間が増えることを喜ぶわけじゃないんです。自分にかかる愛情が減るのを感じるから、「もうこれ以上入れんでいいんちゃう?」って思ってしまう。



そう。でも僕は増やして良かったと思ってます。小さなコミュニティができて、子ども同士のつながりが生まれる。先生と一対一だけじゃなくて、子ども同士で関わることも増えるから。僕自身、常に部屋にいられるわけじゃなかったので、子どもたちが7人くらいでカードゲームしてたり。そういう光景が自然と出てきたんです。
もちろんリスクもあって、トラブルも起きる。でもそこは普通の生徒指導と同じ。例えば「それは違うやろ」と叱ったり、「なんでそんなこと言ったん?」と理由を聞いたり。「昨日家で何があったん?」と背景を尋ねたりもしました。で、「それは傷ついたやろ。どうする?謝る?」って促して、実際に謝らせたりもした。



そう。利用の前半部分は「安心できる場所づくり」。でも後半は普通の教育活動なんですよね。悪いことをしたら叱られる。そういう関わりが自然に入っていく。
新しく入ってきた子はまず「居場所探し」から始めますよね。最初は1人で隅にいたり、ちょっと離れて座ってみたり。みんながボードゲームしているところに、少しだけ混ざってみたり。その子なりに居心地の良さを確かめていく。それにだいたい1週間くらいはかかるかな。
でも周りの子もちゃんと待ってくれるんですよ。「今、あの子は居場所を探してるんやな」と思いながら。そういう期間を保障することがすごく大事だと思うんです。



そうそう。それが1週間なのか2週間なのか3週間なのかは子どもによって違うんですけど、見極めがまた面白いんですよね。先輩の子が「一緒にやろうや」って声をかけて、その子が「うん」って答えた瞬間、大成功!みたいな(笑)。
その中でも自然とリーダーが出てくるんですよ。戸惑っている子がいたら、「私も最初はそうやったで」って話してあげると、新しく来た子は驚いたり安心したりする。そういう会話から過去のつらい経験も少しずつ「笑い話」に変わっていくんですよね。
それってすごいことで、その子が乗り越えた証拠やと思うんです。あの時期があったから今がある、そして次に進める。自己実現に向かう大事なステップだと思います。



確かに。縦のつながりって本当に大きいですよね。2年生にとっては「来年自分はどうなるんやろ」って不安があるけど、目の前に3年生が勉強している姿があると「あ、こうやって進んでいくんやな」ってイメージが持てる。だから怖くないんです。



そう。だから中1から不登校の子とか、小6のときにしんどかった子が、中学に入って1日目からここに来る子もいました。
そのときは「勉強なんかせんでいいよ」って言うんです。保護者は不安そうに「勉強は?」って聞いてきますけど、「大丈夫。3年になったら絶対やります」って答えるんです。
実際、3年生になると不思議なもので、みんな勉強を始めるんですよね。しかも隠れて(笑)。



そうそう。「期待を裏切るのが嫌」って気持ちが働くんですよ。周りに「目覚めたな!」と思われると、後でやめにくい。だからこっそり勉強してるんです。



そうなんですよ。普段は「勉強なんかせん!」って言ってる子が、裏で参考書を開いて、「先生、ここちょっと教えてください」って(笑)。で、親には「めっちゃ勉強してます!」って報告するんです。



本当はもっとずっとお話を伺いたいんですが、最後の質問に移りたいと思います。
ハーバールームの話を聞いていると、やっぱり「学校にこういう場所があること」が大事なのはもちろんですが、それを学校の外や地域に広げていくことも必要ですよね。すでに取り組まれている方もいらっしゃいますが、そういう人たちに向けて「こんな姿勢で子どもと関わるといい」「こんなことを意識するといい」というアドバイスがあれば伺いたいです。



なるほど。実際、地域でフリースクールをされている方ともお話することがあるんですけど、やっぱり「縛られない発想」がすごく魅力的ですよね。
逆に言えば、フリースクールの先生がもし学校教員だったら、きっと厚みのある取り組みをされただろうなとも思いますし。
もともと学校の中に「柔らかい仕組み」を入れていこうと20年前から取り組んできました。その発想自体は地域のほうが先輩だったと思うんです。学校は、地域で生まれた自由な仕組みをどう取り込んでいけるかを模索してきた歴史があると思います。
一方で、不登校の問題の裏側には「学校に毎日きちんと通うことを誰が求めているのか?」という問いもありますよね。子ども自身や保護者が「もっとゆるくてもいい」と思えたら、不登校にならずにすんだ子もいたかもしれない。
そういう意味では、地域と学校が連携して「もっといい加減でいいんだよ」と言える仕組みをつくれるといいのかなと感じています。



僕も同じで、「同じ手法を真似すればいい」という話ではないと思っています。
学校には学校だからこそできることがあって、フリースクールにはフリースクールだからこその強みがある。
もし自分がフリースクールを立ち上げるとしたら、ハーバールームと同じ形にはならないでしょうね。対象を「学校に行けない子」に限定するのか、それとも「誰でも来ていい場所」にするのか、その考え方でまったく変わってくると思います。
大事なのは「連携」だと思うんです。例えば、週に2日は校内教育支援センター、3日はフリースクールに通う、みたいな形も全然ありだと思う。
そのために、学校とフリースクールが定期的に連絡を取り合って「今こんな活動してます」と共有できたらいいですよね。子どもを一緒に支えるチームとして、立場の違いを越えてつながれたらいいと思います。



なるほど。学校とフリースクールって、距離があるように思われがちで、実際に壁を感じてきた人も多かったと思います。私自身もそうでした。
でも、今日のお話を聞いて「むしろつながったほうが子どもの育ちや学びをより支えられるんだ」と実感しました。とても大事な視点をいただけたと思います。
はい。では、少し長くなりましたが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。これで栗東市教育委員会編は一旦終了となります。
先生方が何度も強調されていたのは「学校の中に居場所があることの大切さ」でした。
フリースクールはとても意義ある取り組みですが、まだまだ広く知られていないのが現状です。実際、私自身も学校に通えなくなりかけたとき、「行かなくなったらどうなるんだろう」という不安をずっと抱えていました。
その点で、ハーバールームのように“学校の中にある居場所”は大きな意味を持つと思います。普段は学校に通っている子も、「もし行けなくなっても支えてくれる大人がいる」と実感できる。そういう安心感が子どもにとって何よりの支えになるのではないでしょうか。