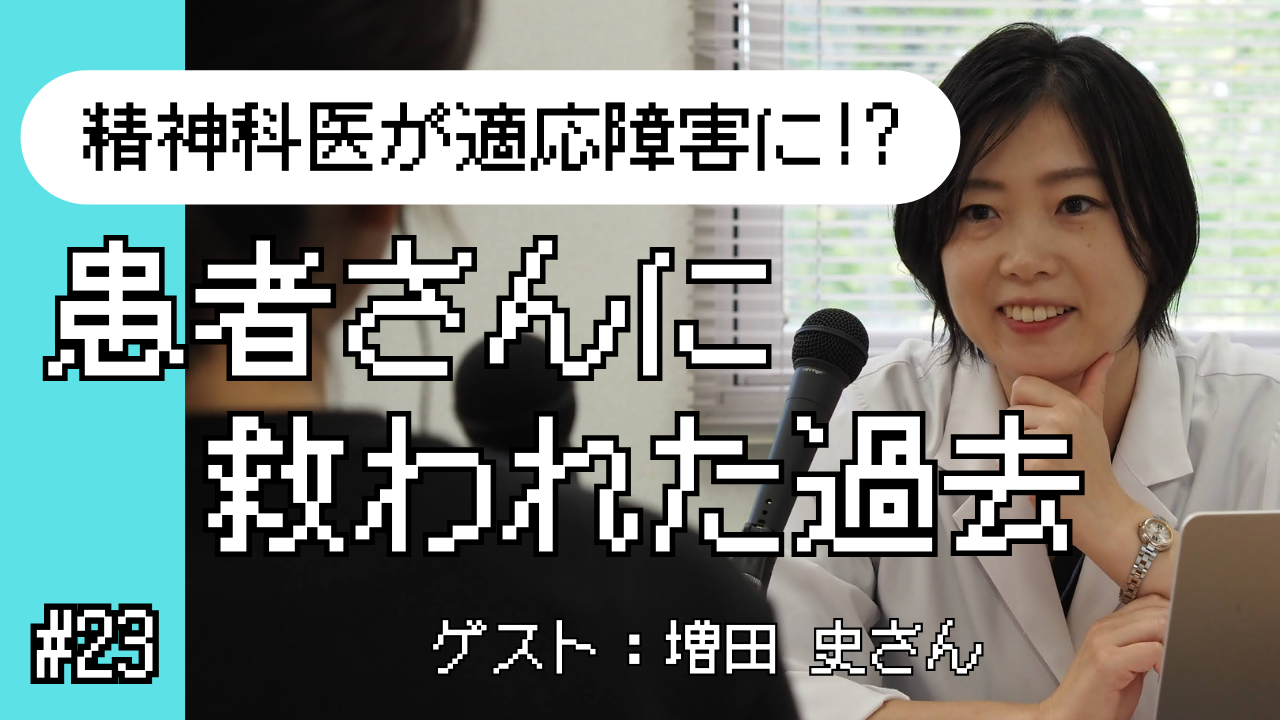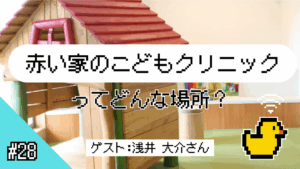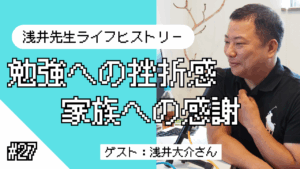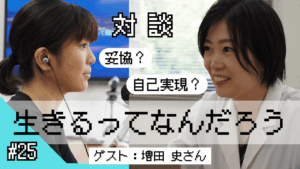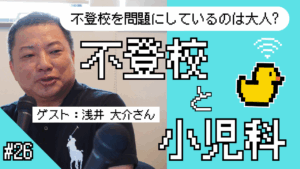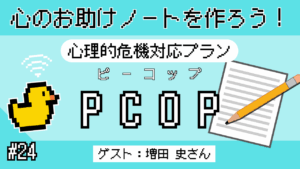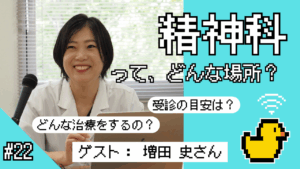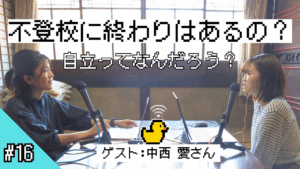本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第23回は、ゲストに精神科医で医学博士の増田 史 先生をお迎えしております。今回は、増田先生自身が経験された適応障害についてお聞きしていきます。
増田 史(ますだ ふみ) さん
精神科医、医学博士。2010年に滋賀医科大学医学部卒業後、初期研修を経て、2012年に滋賀医科大学精神医学講座に入局。脳波を用いた脳機能研究に取り組んでいたが、徐々にうつ状態となり、精神科を受診。適応障害と診断される。休職やカウンセリングで少しずつ回復し、今も回復途上。2021年より滋賀医科大学精神科助教。脳機能研究や児童思春期を中心とした臨床を行うほか、精神疾患に対するスティグマ(偏見)解消にも取り組んでいる。2児の母。出産と育児、また仕事との両立は「想像をはるかに超えてしんどい」。
参考:10代から知っておきたいメンタルケア〜しんどい時の自分の守り方 増田史 ナツメ社 2021年9月1日初版発行 2022年7月1日第3刷発行
本編の前に…
 井ノ口
井ノ口本編に入る前に、一つご案内させていただきます。今回の記事では、増田先生ご自身が体験された「適応障害」のつらいご経験についてお話しいただきます。とても貴重なお話ではありますが、内容によっては聞いていてつらく感じたり、過去の記憶が思い出されてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
もし途中でしんどいなと感じたら、どうか無理をせず読むのを止めていただき、次回以降の配信を、お待ちください。
増田 史先生の小さい頃



前回は「精神科ってどんな場所?」ということをざっくり伺ったと思うんですけど、実は増田先生ご自身も「適応障害」を経験されたことがあると伺いました。そして、現在も回復の途中ということです。
それで、ちょっとお話を先生が小さい頃に戻したいんですが……。先生のご著書『しんどいときの自分の守り方』にも書かれていましたけれども、小さい頃から運動が苦手で、眼鏡をかけていて、自信が持てずしんどい気持ちで過ごされていたとありました。その頃って、どんな感じだったのでしょうか?



そうですね……私は小学校や幼稚園のときから、みんなが一斉に動き出すと、いつも一番最後に後ろからついていくタイプでした。ぼやっとしてる子ども、という感じですね。
小学校1年生のときは、もう最初から学校が嫌で、毎朝泣いていました。祖父母に連れられて学校に行くような日々でした。担任の先生に「朝泣いちゃったカレンダー」みたいなものを作られて、泣いた日にはマークをつけられるんです(笑)。今思えば、逆に励ますようなやり方のほうがよかったんじゃないかなとも思いますけど……。



1年生の時からそんな感じだったんですね。



はい。2年生になっても学校は嫌で……親に「行きたくない」と言うと、「じゃあ連絡帳に書いて先生に出してきなさい」と言われました。
それで「学校を辞めます」と書いて先生に出したら、放課後残されて「先生のことが嫌いなんか?」と聞かれるんです。別にそういうわけじゃないんですけど……なんとなく丸め込まれて、また次に休みたいときにも「また連絡帳に書かないといけないんだろうな」と思って。そんなふうに過ごしていました。



なるほど……。



中学校に入ると今度は成績をキープすることが自分のアイデンティティになって、しんどかったですね。学校自体がすごく荒れていて、NHKが「今、荒れる中学」みたいな特集の取材に来るくらいの状況で(笑)。
授業どころじゃなくて、先生たちも疲弊していて。怖かったですし、暴力もありました。勉強は、偉そうに言えるほどできていたわけではないんですけど、私はもともと過剰適応タイプで、「何かを成し遂げなければ存在意義がない」と思い込むようなところがありました。だから「勉強できなかったら自分には何も残らない」みたいな感覚になっていたと思います。
頑張りすぎた社会人時代



その後、大学を出てから、精神医学講座に入られたんですね。



そうですね。最初の2年間は別の病院で研修医をしていて、その後に滋賀医大の精神医学講座に所属しました。



そこで、気持ちがしんどくなっていかれた。



そうですね。ここからはちょっとつらい話になります。聞いていてしんどくなりそうな方は、無理せず次回の配信から聴いていただければと思います。どっちがつらいか比べるものではないので、自分のペースで大丈夫です。
私の場合、「過剰適応」だったんです。社会の規範に全部応えないといけない、そうでなければ自分には価値がないと思い込んでいました。
「仕事はちゃんとしなきゃ」「子どもは若いうちに産まないと」「大学にいるなら研究しないと」──そういう「べき」に全部乗ろうとしてしまった。
その一方で圧の強い対人関係に見舞われることがあって。その中で自分を責め続けてしまい、「やっぱり自分が悪いからだ、もっと頑張らないと。頑張らなければ生きている意味がない」とまで思い詰めていました。
10年前に長女を出産したんですけど、そのとき私は大学院生で、前駆陣痛が来るまで毎日夜11時近くまで研究していました。ギリギリまでやらないと“自分に×をつける”ような気持ちになってしまって、なかなか帰れなかったんです。
出産後も、2か月半ほどで娘を保育園に預けました。迎えに行くのが遅くなって保育士さんに叱られても、“すみません”と謝るばかり。そのとき“全部は無理なんだ”と気づけばよかったのですが、逆に“もっと頑張らないと”と自分を追い込んでしまい、無理を重ねていました。
職場に車で向かっても、降りられない。死にたい気持ちでいっぱいで、それでも何とかやり過ごす日々でした。2年ほど経つと夜も眠れなくなり、体重も減っていきました。ちょうどその頃、夫の転勤で別の職場に移ることになったんです。
新しい職場に移ってからの半年ほどは順調で、“あのときは環境が悪かっただけ。私ならできる”と思いました。けれど、だんだん同じような状態になっていきました。
そのときは、直径10センチほどの円形脱毛症ができてしまい、ヘアバンドで隠しながら過ごしていました。咳喘息も発症し、体にも不調が出てきたんです。
そうなるとまた、“やっぱり自分が悪いんだ”と自分を責めてしまい、常に“死にたい”という思いが心を覆うようになりました。眠れるときもありましたが、起きている時間はずっと鉛のような重さに押しつぶされている感覚で、呼吸するのも苦しいほどでした。
不思議なことに、そういう状態でも頼まれた仕事だけは何とかこなせてしまったんです。過剰適応というか、そういう状態でした。
で、ふっとパソコンから目を離したりすると、もう「死にたい」って気持ちが一気に出てくるんです。
そんな状況で──これは本当に聞く人がつらくなるかもしれないので、無理に聞かなくて大丈夫なんですけど──家のとある場所にロープを置いておいて、「このロープを使えば、こうすれば死ねる」って考えてしまったことがありました。そのことを思うことで、逆に「いざとなったら大丈夫や」って自分をかろうじて保っていた、みたいな感覚です。
でもそうなると、子どものことや家族のこと、友達のことなんて全然考えられなくなるんですね。今思うと本当に怖いなと思います。
それぐらいになって、「これは本当に危ないかもしれない」と思ったんです。遅いくらいなんですけど。そこでふと、「なんで私、受診してないんやろ」と思ったんですね。
自分は普段「こういうときは精神科に行きましょう」なんて偉そうに言っているのに、なぜ自分は行けていなかったのか。それは、自分の中にスティグマ──偏見があったからやと気づきました。
いつも勇気を出して受診してくれていた患者さんたちに、申し訳ないなと思いましたね。最後、私の背中を押してくれたのは患者さんたちだったと思います。みんな勇気を出して来てくれていた、その姿が「私も行かなあかん」と思わせてくれました。
実際に受診して、「こうこうこうで……」と話したら、先輩の先生が「今の状況わかるか?」って。私が「わかりません」って大泣きしながら答えると、
「鬱状態やし、適応障害やし、休んだほうがいい」って言ってくれたんです。そのとき「そんな選択肢があったんや!」って驚きました。
今思えば、あの職場は辞めてもよかったと思うんです。でも当時は全くそういう選択肢が浮かばなくて。だから「休んでいい」と言われたとき、すごく楽になって。
初めて「死にたくない」って思えたんです。それは自分でもすごくびっくりしました。
それで、なんとか持ち直すことができました。



想像を絶するお話ですね……。



その後、半年ほど寝込むような大きなしんどさが続きました。何が起きていたのか考えてみると、自分の中に“誰かに認めてもらわないと生きる価値がない”という思いがあったことに気づきました。
その自分の性質に、“誰かを支配しないと安心できない”という相手の性質が重なってしまった。変にマッチングしてしまったんですね。その関係にはまり込んでいたんだと思います。
このまま自分の考え方を変えなければ、本当に生きられなくなると思いました。むしろ、気づかないうちに自分が加害者の側に回ってしまうのではないかという怖さもありました。
だからこそ、どうすればお互いにマッチせずにすむようになるのかを考えたんです。結局、どちらのタイプの人も小さい頃に理不尽な目にあったり、十分に助けてもらえなかった経験があるのではないか。だから、その連鎖を止めたいと強く思いました。
適応障害を経験したことは、まさに“どう生きるか”を問い直す出来事でした。自分軸で生きると決意せざるを得ないタイミングだったんです。これまでは、自分の手綱を誰かに預けていたからこそ倒れてしまった。
自分の気持ちや考えを見ないふりをすると、必ずどこかで歪みとして出てしまうのだと痛感しました。だからこそ、自分自身のことに責任を持とうと決めました。その経験を経て、考え方は大きく変わったと思います。



増田先生は今も、ご自身が過剰に適応してしまう性質と向き合いながら、お仕事や子育てをされていると思うのですが、どのように向き合っておられますか?



ここ数年で知り合った人たちから見たら、『どこが過剰適応やねん』と思われるかもしれません。でも、そう思ってくれているなら、私も少しはいい方向に変わったんだと思います。鬱状態になった後、自分の変わった面もよく見えるようになりました。
例えば、以前は周りの人は完璧で、自分は劣っていると感じていましたが、今は『みんな完璧じゃないし、自分も同じくらいかも』と思えるようになりました。それを少し念頭に置けるようになったのは、大きな変化ですね。
あとは、以前は『社会人として頑張らなきゃ』という思いが強かったのですが、よく考えると家族のことも大事だし、それを認められるようになったのも良かったです。ただ、体力はかなり落ちてしまいました。予定を組むのも難しく、リカバリー期間を取らないと通常業務に戻れないことがあります。でも、そうして調整していくと少しずつマシになってきました。以前は週4日は寝込んでいましたが、最近は週1回くらいで済むようになっています。
人と接するとき、特に強い関わり方をされる方がいると反応してしまうことがあります。でも、自覚できている分、だいぶ区別がつくようになりました。『これは現実に即しているわけではなく、反応として出ているだけだ』と理解できるんです。「よしよし、過剰適応が出てきたね」って自分に言うんです。
以前は自分の感情が消えてしまう方がいいと思っていて、中学生の頃からロボットのようになりたいと思っていました。でも最近は、やっと自分の感情と一緒に生きていこうと思えるようになりました。



ありがとうございます。今回はここで終わりにしようと思います。



ありがとうございました。皆さん、今は大丈夫です。深呼吸して、回復してから次の作業に移ってくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
精神の専門家のような方でも、自分がつらいと感じることを「努力不足のせいかもしれない」と我慢してしまうことがある、というのは意外でした。
一方で、増田先生だからこそ理解できること、寄り添えることもあるのだな、と感じながらお話を伺いました。
最後までお聞きいただき、ありがとうございました。それでは、また来週お会いしましょう。