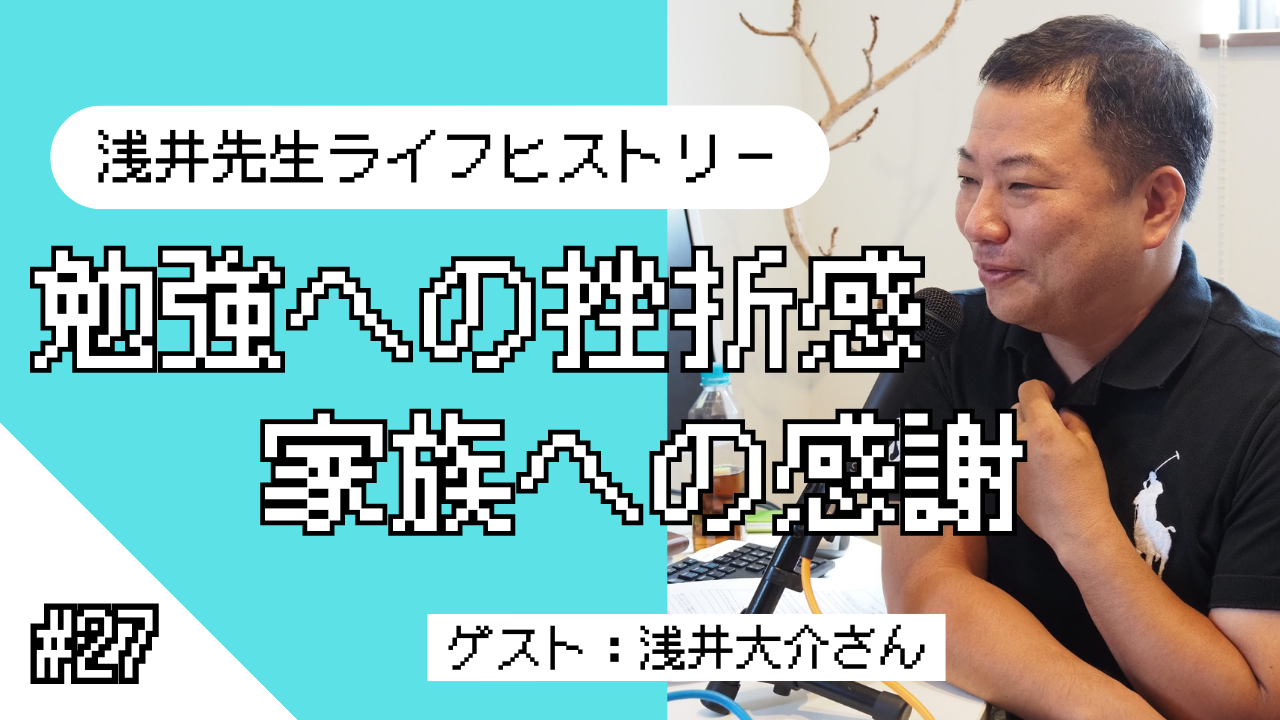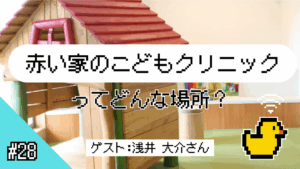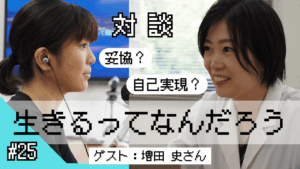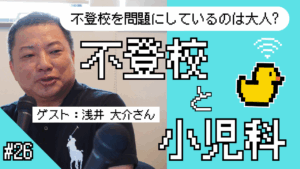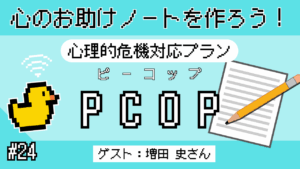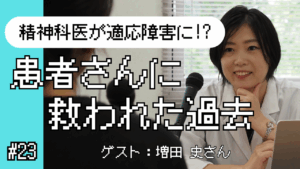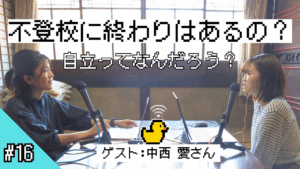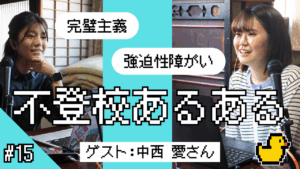本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第27回は、ゲストに小児科医の浅井大介先生をお迎えしています。今回は、浅井先生が医学部に入るまでに経験した勉強への挫折感と、浪人中に気づいた家族への感謝のことをお聞きしていきます。
浅井 大介 さん
小児科専門医、血液専門医。京都府立医科大学、京都第二赤十字病院などで小児科医として従事。2018年にあさいこどもクリニック(現:あかい家のこどもクリニック)を開院。診療のかたわら、国内の災害医療支援や海外の小児医療支援にも携わる。
参考:あかい家のこどもクリニックHPより
挫折の連続だった、小学校から高校まで
 井ノ口
井ノ口第27回は、引き続き小児科医の浅井大介先生をお迎えしています。今回は、浅井先生がお医者さんになるまでのライフヒストリーをうかがっていこうと思います。よろしくお願いします。
前回は、不登校の子どもたちへの向き合い方についてお話しいただきましたが、実は浅井先生ご自身も、学校にあまり馴染めなかった子ども時代を過ごされたそうですね。



そうなんですよ。僕、京都市内の出身なんですけど、小学校のときは野球部補欠でした。
それで、親に連れられて進学塾に入ることになったんですが、小6のときに入塾試験に落ちたんです。しかも2回も。で、3回目にようやく「お情け」で入れてもらって。
でもね、その教室に入ったときに、なんかクスクス笑われたんですよ。「あ、あの落ちたやつや」みたいな感じで。それでも頑張って、まぐれで一番とか二番の成績を取ったこともあったんですけど、なんかそれもまた笑われた記憶があって。結局その塾でも馴染めないまま、中学受験をして、もちろん落ちました。
今思えば、あのときも主体的に選んでなかった。
合格発表の日、受かった子たちがみんなに褒められてる中で、自分は廊下の傘立ての横に座って、出ていくのを見てたんですよ。同じように落ちた子が2人くらいいて、「俺ら今日、居づらいな」って言ってたのを今でも覚えてます。
あれはほんとに傷つきましたね。



なんと…中学校に入ってからはどうでしたか?



中学では軟式テニス部に入ってました。
でも塾は相変わらず馴染めなくて、中3のときに辞めました。うちの子に聞いても「中3で塾やめるなんて、お父さん変わってるね」なんて言われます。
で、結局高校受験も失敗して、公立も私立も落ちて……最終的に普通科の学校に入ったんですけど、そこも全然馴染めませんでした。
最初は「今度こそ勉強頑張ろう」と思って、予備校の高校生クラスに友達と入ったんですけど、結局それも高2で辞めちゃって。部活にも入りそびれて、友達も少なくて、ほんとにつまらなかった。学校もほとんど行ってなかったんですよ。
朝、学校に行くクラスメイトとすれ違うんですよ。「お前、逆方向ちゃう?」って言われながら、僕は私設図書館とか全然違うところに行ってたんです。そんな感じで、留年しかけてましたね。
でも、誰にもあんまり何も言われなかった。親も「ほっとけ」って感じで。16歳のときに原付バイクの免許を取って、原付で通学してました。(笑)ほんとにまともな高校生活じゃなかったですね。
でもある日、本屋さんで「大学入試資格検定試験」の本を見つけて、「こんなんもあるんや」と思ったんです。ただ、そのときは「自分には無理やな」と思って。それでも、「さぼりながらでも、ギリギリでも高校は卒業しよう」って思ったんですよ。それをすごく覚えてます。
当時の成績は、5段階で「1が3つ、あとは全部2」とかそんな感じで、ほんとにギリギリ。でも、なんとか卒業して。18歳の高校3年の夏は、自分の人生について本気で悩んで、考えてましたね。
勉強方法から学び直した浪人時代



どんなことに悩んでいたんでしょうか?



そのときに、三つのことをやろうって決めたんですよ。
一つ目は、「人のためになることをしたい」。
二つ目は、「受験へのコンプレックスを克服したい」。
三つ目が、「一度でいいから、本気で死ぬ気で何かをやりたい」。
この三つです。
で、その中で「国立の医学部に行けたら、すごいことやな」と思って。
人を助けたいという気持ちもありましたけど、どちらかというと「今まで本気でやらなかった自分を変えたい」という思いの方が強かったですね。
でも、勉強のやり方がまったくわからなくて。予備校に入れてもらったんですけど、すぐ行かなくなってしまって、夏前にはもう引きこもり状態。
それが3年くらい続いたんです。成人式にも行ってないし、21歳ぐらいまで何もうまくいかなかった。
当時は友達からも「お前どうすんねん」って言われてね。でも、どうにもならなくて。そのうち、北海道の大学で二次募集があったから、受けて、たまたま受かって。それで北海道に行ったんです。
でも結局、そこでまた遊び倒してました。麻雀にパチンコにバイクに……。バイクで事故したり、いろいろあったけど、それでも3年は楽しく過ごしました。24歳になる前に、「このまま卒業しても意味ないな」って思ったんです。
それで両親に電話して、「中退して帰ります」って伝えたんですよ。当時、フェリーで30時間かけて京都に戻ったんですけど、港に着いたら、親が待っててくれてたんですよ。
ほんまに感動しました。「こんなにお金も時間も使ってくれたのに、中退して帰る自分」を迎えに来てくれたんやって思って。 両親はもう亡くなりましたけど、そのとき父が「せっかく港まで来たし、寿司でも寄って帰るか」って言ってくれてね。小さなカウンターのお店で食べた寿司、あれは一生忘れません。あのとき、「今度こそ心を入れ替えて本気で頑張ろう」って思ったんです。



ここからまた、勉強の日々が始まるんですね。



うん。でもね、僕は「心を入れ替える」って言葉は信じてないんですよ。
心は勝手に変わらへん。行動を変えるしかないんです。
だからまず、「今までの勉強のやり方を全部見直そう」と思って、徹底的に分析しました。「自分はやる気があったのになんでうまくいかへんかったんやろう」って考えて。それで気づいたのは、勉強の“やり方”を勉強してなかったってこと。
予備校に行ってるだけで、やった気になってたんですよ。だからまず、「勉強の仕方を学ぼう」と決めました。
それから、当時出版されてた「医学部合格体験記」っていう本を、10年分くらい買いあさったんですよ。どんな参考書をどう使うか、休日の過ごし方、暗記の方法……全部ノートにまとめて研究しました。
「どのやり方が自分に合うか」っていうのを試していってね。そして、自分に合う方法は「間違えた問題だけ徹底的にやる」ことだって気づいたんです。僕は今でも「勉強とは“復習”や」と思ってます。
模試も全部受けて、問題を左に、答えを右に書くノートを自分で作ってね。ある本で「ノートは、入試前日の自分に宛てるラブレターだ」と書いてあって、それを見つけたときに、すごくハッとしたんですよ。「試験前日に、自分が自信を持って見返せるように、まとめるノート」。それが本当のノート作りなんやって。
それを3年間やり続けたら、成績がどんどん上がっていって、最終的に国立の大学に合格できたんです。
でもね、3年間の中で、もうひとつ決定的な出来事があったんですよ。
医学部合格に足りなかったのは、「感謝」!?



その出来事とは?



成績も上がって、友達もできて、順調に見えたんですけど……2年くらい経っても、なぜか結果が出なかった。「なんで自分はここまでやってるのに、まだ合格できへんのやろう」って思ってたんですよ。
ある時ふっとね——お風呂に入ってるときに気づいたんです。
「自分には“感謝”が足りてなかったな」って。
医学部に行きたいとか、結果を出したいっていうのは、全部“自分のため”やったんですよ。自己都合の頑張りやったなって。
だって、もし自分が医者になっても、出会う人たちは“好きで病気になってるわけじゃない”。苦しみや悲しみの中にいる人たちに向き合うのが医者なのに、自分は“うまくいかへん”“結果が出ない”って愚痴を言ってる。それって全然違うなって。
そこで初めて、「自分はほんまに恵まれた環境で勉強させてもらってる」って気づいたんです。新聞配達して、銀行口座作って、勉強の合間に働きながら……それでも勉強できる環境をもらってた。でもそのことに全然感謝できてなかった。それに気づいたのが、すごく大きかったです。
両親もね、僕のことをあんまり干渉しなかったんですよ。「あなたの人生やから、あなたが決めなさい」って。
当時は一日10時間以上勉強してました。でもそれは、誰かに押しつけられたからじゃなくて、自分で選んだこと。「自分が行きたい」って思ってやってたから。しんどくても、楽しかったですよ。模試で全国2位を取ったときなんて、ゲーム感覚で楽しんでいました。
疲れたら科目を変えたり、場所を変えたりしてね。時間の使い方や集中の仕方も、自分なりに工夫してました。そういう経験が、今の仕事とか経営にもすごく生きてるなと思います。
だから僕が振り返っても、一番大きかったのは“主体的に選んで動けたこと”、そして“感謝を持てたこと”。この二つですね。
それにね、ある経営者の方が言ってたんですよ。
「どうせ失敗するなら、若いうちに、なるべくお金をかけずに失敗しろ」って。ほんまその通りやと思う。
僕も10代20代のうちにたくさん失敗できてよかった。
家族もいなかったし、大きな責任もなかった。
予備校代くらいなら、あとで自分で返せるしね。
だから僕、不登校も“失敗”とは思ってないんです。
もちろん問題はあるけど、その中で気づきや学びを得られたら、それは大きな財産。そういうふうに思っていますね。



不登校の子どもたちにも「努力・忍耐・根性」じゃなくて、「どうしたら自分は生きやすいか」をちゃんと考えてみて、ということでしょうか?



努力を否定しているわけじゃないんです。頑張るべきときは頑張る必要があるし、そういう局面もあると思います。でも例えば「学校へ行きたくない」っていう子がいたときに、学校へ行くことを頑張るのか、それとも学校以外の選択肢で頑張るのか——そこを自分で選ぶことが大事だと思うんです。
僕自身も、学校がすごく嫌だったんです。でも「大学入試資格検定」を取るよりは卒業した方がいい、と思ってそっちを選びました。クラスメイトに変な目で見られながらも、「行ってよかったな」と今は思っています。
それに、僕はいつも「高卒資格だけは取っておいた方がいい」と言ってるんです。
今はN校とか、いろんな選択肢があります。高校を出ているかどうかで、将来的に選べる道が全然違う。たとえば生涯賃金の面でも、中卒と高卒では数千万円単位で差が出ます。大学で「これを学びたい」と思ったときも、高卒資格があれば進みやすい。だから、何年かかってもいいから、高卒資格は取ってほしいと思っています。
中学は基本的にどんなことがあっても卒業できるけれど、高校をどう卒業するかは人によって違う。そこをどうやってクリアしていくか——それは「努力・根性・我慢」ではなく、「どういう戦略を立てて、どういう方法で登っていくか」なんですよ。
人生って、僕は「山登り」みたいなものだと思ってるんです。
しんどい山に無理して登ってもしょうがない。自分が登れる高さや傾斜、気候、時期、装備をちゃんと考えて、自分に合った登り方を見つけることが大事です。
でも、その「登る山」を決めるのは自分自身なんです。
親や先生が手を引いて登らせてくれるわけじゃない。主体的に「この山を登る」と決めて、自分の足で登ってほしい。そのうえで、「どんなルートがあるか」「どんな準備をすればいいか」っていう戦略や戦術を一緒に考えるのが、周りの大人の役割なんだと思います。



自分で決めるのが大事、というのは繰り返しおっしゃってますね。



当たり前のことだけど、それがいちばん大事。
結婚も、就職も、転職も、全部そうですよね。自分で決めて、自分で登っていく——それが主体性だと思います。
なぜ高卒認定は取るべきなの?



やっぱり浅井先生のお話を聞いていると、ある種“厳しさ”があるなと思うんです。
でもそれは、ただのスパルタ的な厳しさじゃなくて、優しさの裏にある厳しさというか。きれいごとではない現実を見据えた上で、「高卒認定を取ってほしい」とおっしゃっているところに、先生の考え方がすごく表れている気がします。



もちろん、他に本当にやりたいことがあるなら、そっちの道に進めばいいと思うんです。たとえばサッカーでも音楽でも。ただ、残念ながら今の日本社会では、学歴で判断される部分がまだまだ多い。それによって選択肢が狭まってしまうことは、どうしてもあるんですよ。それに、お金っていうのもすごく大事で。
やりたいことができたときに、資格を取るとか、講座を受けるとか、誰かに会いに行くとか、全部にお金がかかりますよね。そのときにお金がなかったら、「まずお金を貯めることから始める」っていう時間的ロスが生まれてしまう。だから、もし今「特にやりたいことがない」なら、まずは高卒資格を取っておく。それが、将来の選択肢を広げるための一歩になると思うんです。
これ、入試前日の自分に向けてノートを作っていたにも通じるんです。しんどくても、苦しくても、意味がないように思えても、それが“未来の自分へのプレゼント”になる。僕は医者としてじゃなくて、一人の人生の先輩として言いたいんです。
事実と感情は分ける必要があります。
社会の“事実”として、学歴や経済状況で見られてしまう現実がある。だから感情だけで動くんじゃなくて、事実を冷静に見て、自分の選択を整えておく。そういう意味で「高卒資格を取っておいたほうがいい」と言っているんです。
今の日本って、少子化や人口減少がすごいスピードで進んでいて、外国の人もどんどん入ってきてますよね。コンビニでも夜勤の店員さんの多くが外国の方だったり。そういう社会の中で働いていくなら、やっぱり学歴があるかないかは現実的に大きいんです。
だから、「中卒で生きていく」と決めて頑張るならそれもいいけれど、もし迷っているなら、取っておいた方がいい。僕はそう思います。



なるほど….



よく「先生はやりたいことがいっぱいあっていいですね」「頑張ってますね」って言われるけど、実は逆なんですよ。
僕、ほんとはサボりたいし、休みたいし、朝も起きたくない(笑)。でも何で頑張れるかというと、“頑張るために目標を設定している”からなんです。みんな、「目標があるから頑張る」と思ってるけど、僕はその逆で、「頑張るために目標を作ってる」。
人生って、“順番が逆”なんですよ。
「感謝してるから成功する」って言葉があるんですけど、それも同じ。
「成功したから感謝する」んじゃなくて、「感謝してるから成功する」。
順番を間違えないって大事なんです。
だから僕は、いろんなことをやってるように見えるけど、全部理由がある。ひとつのことに執着すると、細かいことが気になりすぎて動けなくなるタイプだから、いろんなことを並行してやることで、自分を保ってるんです。それが僕にとっての“頑張り方”。
経営者の勉強会でアメリカのシリコンバレーに幼稚園をいくつも立ち上げた女性と話したんですけど、その方が言ってたのが、「我慢して頑張る未来には、我慢して頑張る現実がやってくる」ってこと。逆に、肩の力を抜いてリラックスして生きていると、そういう未来がちゃんとやってくる。
頑張りすぎるとドーパミン的な“報酬回路”が動いて、「もっともっと」ってなっちゃう。ゲームで次の武器を欲しくなるのと同じで、きりがない。だから大事なのは、「自分がリラックスして幸せだと思える状態をどう作るか」。それが生き方の根っこなんです。



肩の力を抜くための、高卒認定ということでしょうか?



そうですね。自分の診療の中で「朝起きる」っていう目標を設定しても
週に何日起きられました?
次はもうちょっと起きましょう。
次は一時間目から行きましょう。
次はテストでいい点数取りましょう……って、もうキリがないんですよ。
だから大事なのは、「何のために朝起きるのか」「何を目指してるのか」「どこを目指してるのか」「自分の幸せってどういう状態なのか」っていうところ。
だから、「高卒認定を取りましょう」っていうのも、僕は個人的には、あった方がいいと思う。でも、別にいらんっていう選択も全然アリやと思う。ただ、「持っといた方が気持ちが楽になることもあるよ」っていう、そんな感じです。
まとめ
浅井先生が不登校の子供たちの診療に力を入れていらっしゃる背景として、浅井先生の人生がすごく大きく関わっていることがよくわかったかなと思います。 前回おっしゃっていた人生の経験は全て贈り物だっていう考え方をまさに体現されてる生き方だなと思います。 最後まで聞いていただき、ありがとうございました。