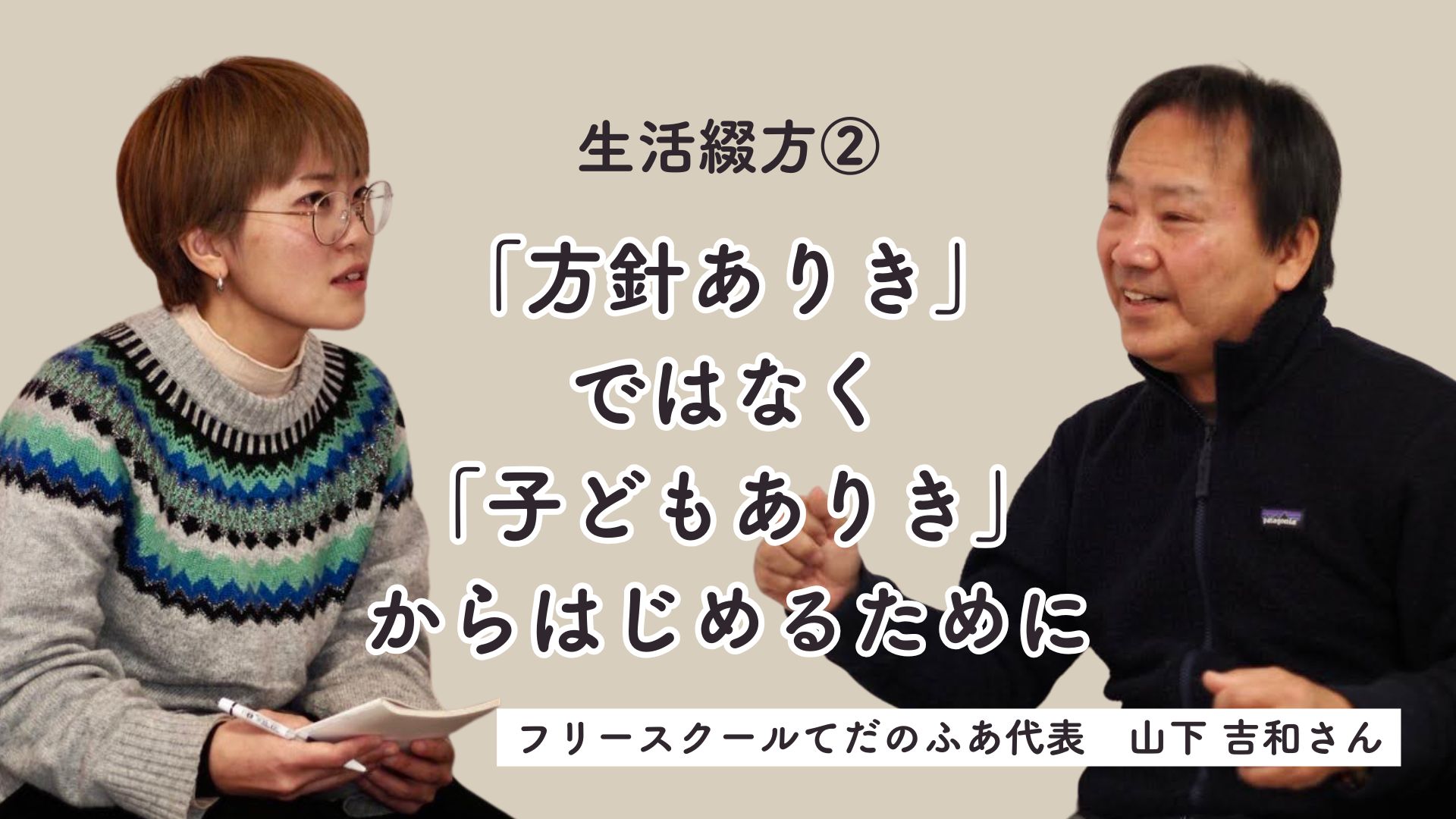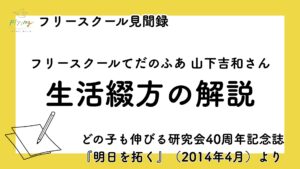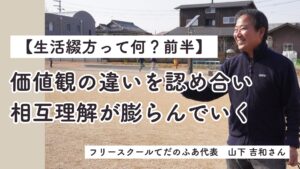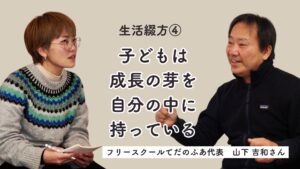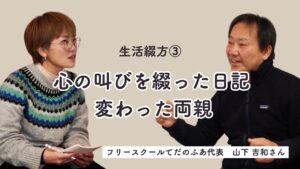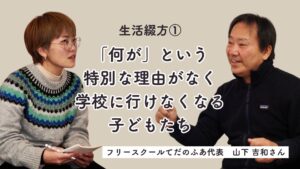彦根市京町のNPO法人「フリースクールてだのふあ」は、築100年の改装された古民家で運営する不登校の子どもたちのためのフリースクール。2020年に設立され、今では小学生から高校生まで約30人の子どもたちが通います。「すべての子どもたちは成長の芽を持っている」と語る代表の山下吉和さんには、そのことを実感した体験がいくつもありました。
今シリーズでは、山下さんが初めて向き合った不登校のケンジ君(仮名)と、ケンジ君と周囲の大人の成長を助けた『生活綴方』の実践について、全4回に分けてお伝えします。
山下 吉和さん
NPO法人 てだのふあ 代表
1961年、長浜市生まれ。87年、滋賀県教員となり佐和山小など彦根市内の小学校に31年間勤務。「生活綴(つづり)方教育」に力を注いだ。県中央子ども家庭相談センター指導員を経て2020年にフリースクール「てだのふあ」を開校。登山ガイド資格も持つ。

生活綴方②「方針ありき」ではなく、「子どもありき」 からはじめるために
彦根市京町のフリースクール「てだのふあ」を運営する山下さん。初めて不登校の問題に向き合ったのは、教員時代でした。「何が」という特別な理由があるわけではなく不登校になったケンジ君。「学校に来なくていいよ」と伝える代わりに、山下さんが提案したのは5つの方針でした。
1つ目、嫌だという気持ちが身体に表れている以上、無理には登校させない
2つ目、毎日30分、家庭訪問をする
3つ目、専門機関(児童相談所)と連携する
4つ目、不登校の学習会に一緒に参加する
5つ目、日記帳でお互いの理解を深める
――「5つの方針」はどのように考えて提案されたのでしょう?
最初の一週間の様子を見て、ケンジのリアルな姿を知ることから始めることが必要だと思いました。不登校でも、発達障害でも、反社会的な行為を繰り返す子どもでも、基本的なスタンスは同じです。先入観でとらえるのではなく、子どものリアルな姿からその子どもの内面をさぐりながら出発すること。その子の家庭的な背景、生い立ちも含めて「丸ごと」子どもをとらえる努力をすること。具体的に提示された子どもの姿に対して、今この子に何が必要か、どんな力をつけるべきなのかを探ること。どんな働きかけを準備して、行動に移すのかを明確にしていくための第一歩として考えたのがこの「5つの方針」でした。方針をさぐるための、方針です。
決して「はじめに方針ありき」ではなく、「子どもありき」 からはじめるために、僕はケンジに日記帳を持たせることにしました。ずっと教室で続けてきた「生活綴方」という教育方法をケンジとも実践しようと思いました。
――「生活綴方」について教えてください。
戦前からある教育方法で、東北地方などの生活の厳しい農村部を中心に広がりました。いわゆる日記指導です。子どもらが書いてきた日記を取り上げて授業する。子どもたちは「貧しいのはなんでだろう」「苦しいのはなんでだろう」と日々ありのままに感じたことを日記の中で書いてくる。それを取り上げて、教室内に社会を持ち込み、もののあり方、見方を共有し、人間の真実を追求していく。そういう教育方法のひとつが戦後も残っていました。
通常の日記指導というのは、前置きがあって、中があって、最後はこういう風にまとめましょうという型があります。一方で、生活綴方は作文指導ではなく、書き方も自由、書きたい時に書いたらいい、書かない自由もある。
僕は子どもらに日記帳を2冊持たせて、毎日1冊を預かっていました。その日預かった一冊の中から、テーマを決めて抜粋し、翌日の授業で使うために、まとめるんです。
例えば、今日は「優しさ」がテーマと決めたら、優しいをテーマにしたような日記を集め、「友達」というテーマやったら、友達のこと書いた日記を集めて教材を作ります。私たちはそれを「一枚文集」と呼んでいました。それをもとに、道徳や朝のホームルームなどの時間を使って授業をします。日々続けていくことで、子どもたちは自分では発見し得なかった視点に他者の視点から気が付いたり、意見の違いを認め合うことを学びながら、ともに協力し合って社会をつくり上げていく力を身につけていきます。
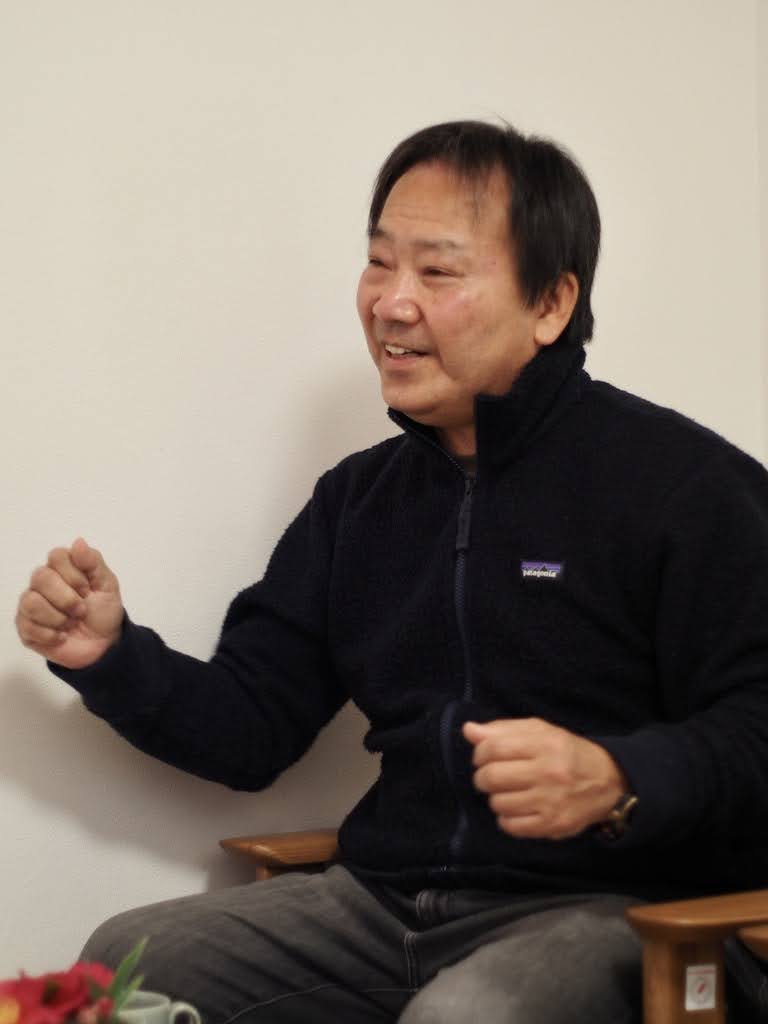
――でも、ケンジ君は不登校。教室で学び合う「一枚文集」には参加できません。どのように「生活綴方」指導をされたのですか。
まずは、教室にケンジが来てくれた時に、いつでも受け入れられるようにクラスを整えておこうと気を付けました。ケンジには関係なく「一枚文集」の授業も続けたし、ケンジの話も毎日していました。「昨日は家でこんな風に過ごしとったよ」とかね。
「生活綴方」は、日記から子どもの生活の背景を読み取り、日記に表出する子どもの心の機微を理解して、生活指導につなげていきますが、家庭を訪問することもその一環です。
ケンジは相変わらず学校には来れないけれど、とにかく毎日私の訪問を待ってくれていました。もうちょっと遊びたいなと思ってもらえる頃に約束の30分が来て、惜しみながらお別れをする。
ケンジが一番ハマったのは、将棋です。 ゲームボーイが飽きてくるとオセロになって、将棋に変わっていく。将棋はね、僕、絶対にわざと負けんかったんですよ。だからケンジは勝つことをひとつの目標にしてくれました。今みたいにAIアプリがあるわけじゃないから、あの手この手を自分で勉強してね。
一緒にバドミントンもしました。地域も歩けるようになってきて、 魚釣りに連れ出したこともありました。空き時間が2時間ぐらいあったんです。僕、「ケンジのとこに行ってきます」言うて、犬上川のとこにケンジ連れていって。今考えると、めちゃくちゃやね(笑)
日記には「釣りの話をして、面白かった」「先生が来て、バドミントンをした」「早く夏休みが来ないかなあ」とか、そういう三行日記が並んでいました。
でも、一学期はケンジが学校に来ることは、一度もなかったんです。
(続く)