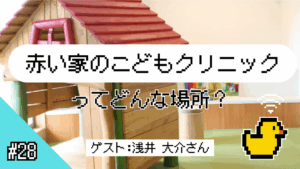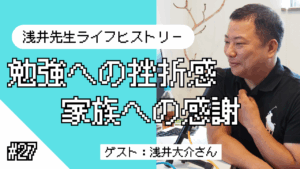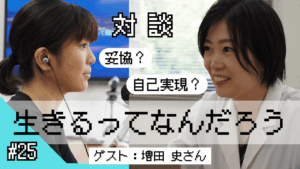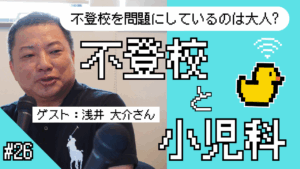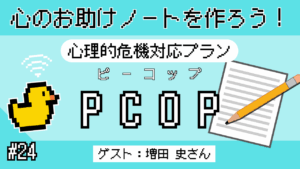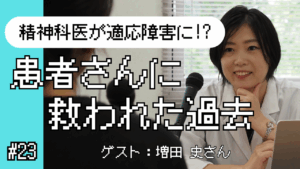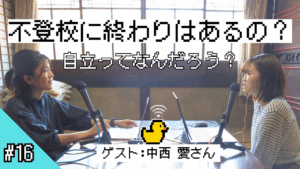本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
今回は、社会福祉士であり、市民活動団体「おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクト」の代表を務める伊藤 いつかさんをゲストにお迎えしました。伊藤さんは小学校の教員として長年にわたり不登校の子どもたちと関わってこられました。今回は、スクールソーシャルワーカーという仕事について、またその経験から感じたことについてお話を伺いました。
 井ノ口
井ノ口学校の先生の延長、というよりは親御さんや地域の方とも結構関わるような仕事なんですか?



そうですね。子どもたちと直接関わる時間よりも、環境を整えることが主な役割です。学校の先生と話したり、保護者さんの希望があれば、面談もします。ただ、スクールカウンセラーのように、寄り添って、その心を癒していくようなアプローチとはちょっと違って、その子の環境を整えるのが、私たちの仕事です。その子の健やかな成長のために何をすることが大事なのかを考えて、「ケース会議」を通じて支援の方向性を決め、足りない部分を補いながら支援を充実させていく仕事です。



なかなか、曖昧というか、複雑な内容ですね。



「曖昧」という言葉、大事だと思います。人間社会って、そもそも曖昧なことばかりですよね。子どもたちも、自分で決められないことが多くて、悩んだり傷ついたりします。だからこそ、ソーシャルワーカーは「その人自身」ではなく「環境」に目を向けて、どうしたら幸せに暮らせるかを考える仕事なんです。私は、その曖昧さに魅力を感じてこの仕事をしています。はっきりと名前のつかない、でもみんなが健やかに暮らせるように支える仕事、そんな感じですね。



担任の先生をしていた時に、スクールソーシャルワーカーさんに助けられたことはありますか?



担任をしてたとき、スクールソーシャルワーカー(SSW)さんに助けられたことは何度もあります。例えば、(前回登場した)自閉症の子の遠隔授業をしてたとき。私はできる範囲で対応してたけど、高学年になると他の先生の授業も増えて、その子が受けられない授業が出てきた。でも、自分だけでどうにかするのは限界があって、「これは制度とか学校の仕組みの問題だな」ってすごく感じたんです。
それから、近くに児童養護施設や母子生活支援施設があって、福祉的な課題を抱えてる子どもたちがいたんです。ある日、シングルマザーの家庭の子が学校に来られなくなって、私も家庭訪問したかったけど、距離的に難しくて…。そのときSSWさんが「気になってるんだけど、どう?」って声をかけてくれて、週に一回、家庭訪問してくれることになったんです。本当にありがたかったですね。
そのとき実感したのは、「担任一人で抱え込んじゃダメだな」ってこと。不登校の問題って先生だけで解決できるものじゃないし、みんなで支えていくことが大事なんだなって思いました。SSWさんがいてくれたからこそ、助かった場面がたくさんありました。



先生の仕事は、授業だけじゃないのがよく伝わります。



日本の先生って本当にすごいなって思うんですよ。授業だけじゃなくて、子どもたちの生活や家族のことまで背負ってきた歴史があって。でも、その結果、今は先生たちがパンクしちゃってる現状もあるなって感じます。昔はもう少し余裕があったのかもしれないけど、今はやることが細かく決められてて、時間もないし、休憩なんて取れないのが当たり前でした。



これって先生の力不足とかじゃなくて、そもそも先生の役割自体が変わってきてるんだと思います。



だからこそ、制度の改革は絶対必要だし、先生一人が全部やろうとするんじゃなくて、もっと周りを頼れる空気ができたらいいなって思います。学校の中だけじゃなくて、地域や保護者とも協力しながら、みんなで子どもたちを支えていく。そんな環境を作っていけたらいいですよね。



このラジオでも、そういうことを一緒に考えていけたらいいなって思いました。
まとめ
スクールソーシャルワーカーという仕事の曖昧さとその重要性についてお聞きしました。一方で、先生の仕事の大変さや、今の教育現場が抱える課題もリアルに伝わってきました。「先生一人で抱え込まない」「もっと周りを頼れる空気を作る」っていうのが大事だし、学校・地域・保護者が一緒になって子どもを支える仕組みが必要ですね。
次回は、伊藤さんが、不登校の子どもと向き合うお母さんとして経験されたことについて深掘りしていきます。お楽しみに!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本編を聞くにはこちら↓