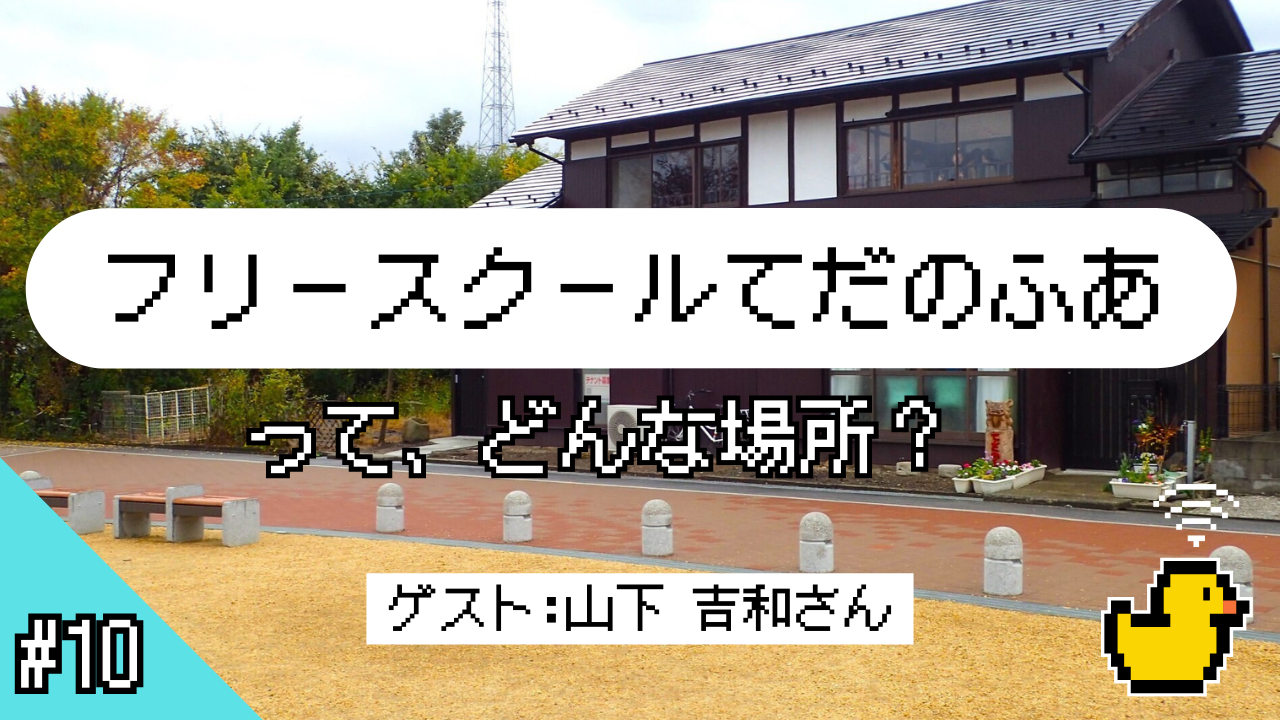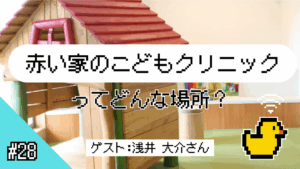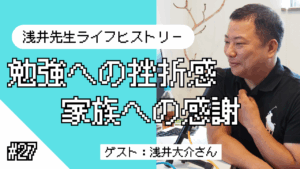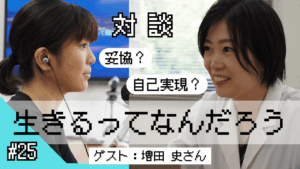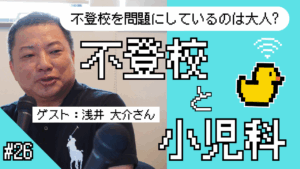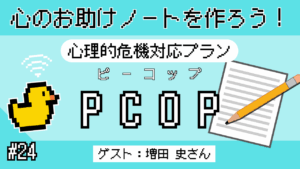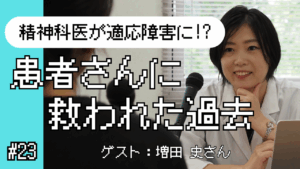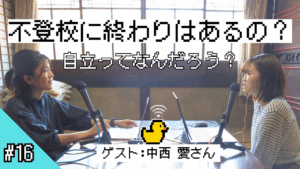本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第10回は、ゲストにNPO法人 フリースクールてだのふあの山下 吉和さんをお迎えしています。今回は、てだのふあで行っている活動や場所のこと、山下さんがてだのふあを立ち上げるまでの経緯をお聞きしています。
山下 吉和さん
NPO法人 てだのふあ 代表
1961年、長浜市生まれ。87年、滋賀県教員となり河瀬小など彦根市内の小学校に31年間勤務。「生活綴(つづり)方教育」に力を注いだ。県中央子ども家庭相談センター指導員を経て2020年にフリースクール「てだのふあ」を開校。登山ガイド資格も持つ。植物保全「伊吹山ネイチャーネットワーク」事務局長。
【NPO法人 フリースクールてだのふあ】
滋賀県彦根市のNPO法人「フリースクールてだのふあ」は、不登校の子どもらの居場所づくりに取り組まれています。 てだのふあは沖縄の方言で「太陽の子」の意味です。「しぜんな成長」を支援しようと、学習の時間やスタッフらによる絵画教室など様々な教室を用意し、登山や座禅体験などにも取り組んでこられました。 代表を務める山下吉和さんは元小学校教師。「子どもに寄り添った活動をしたい」と、2020年にてだのふぁを発足されました。向き合ってきたのは音に敏感な子や対人関係に傷ついた子……。「心身共に開放し、のびのびと過ごして」と願い、不登校の親にも寄り添ってこられました。
📌 てだのふあ公式Facebookページはこちら
 井ノ口
井ノ口ではまずは山下さんの自己紹介から、お願いします。



NPO法人フリースクール「てだのふあ」代表の山下です。よろしくお願いします。31年間、小学校教員を続けてきたんですが、そこにピリオドを打って、2020年の4月にこのフリースクールを立ち上げました。
「てだのふあ」っていうのは、沖縄の方言で「太陽の子」という意味なんです。私が学生時代に沖縄を旅した時に出会った言葉で。当時、灰谷健次郎という児童文学作家が『太陽の子』という本を出していて、それも背景にあります。



ありがとうございます。そうだったんですね、「太陽の子」って、意味を知らなかったので……沖縄の方言だったとは。
今日は私たち、彦根市にある「てだのふあ」の事務所で収録をさせていただいているんですけど、ここはもともと100年ほどの歴史があるお家だったそうですね。それを改修されたんですか?



そうですね。新しい場所を探していた時に、たまたま私がここを通りかかったんです。この古民家そのものは、もう崩れかけていて、幽霊屋敷みたいな感じでした(笑)。まわりも野原が広がっていて、何もない殺風景な場所だったんですね。でも、その「何もない」ということに私はすごく惹かれました。耐震性などの面で不安に思っていたので、オーナーと掛け合って、国や市の助成金をいただいて、全面的に改修していただいたんです。耐震性も含めて、安全で安心な建物に生まれ変わりました。
そして、もともと野原だったその殺風景な場所も、防災公園として整備されることになって、今では本当に子どもたちにとってふさわしい環境になったんじゃないかなと思っています。



そして、隣には畑もありますね。



そこもオーナーと掛け合って、ほとんど無償に近い形でお借りすることができて。そこを彦根市のロータリークラブさんが全面的に寄付してくださって、さらに休眠預金の助成もいただいて。全面的に改修して、子どもたちにとってふさわしい農園になったと思います。
遊具も、保護者の方が手作りしてくださって、ブランコも一つできて、そこで炭火でマシュマロを焼いたりして、子どもたちが集まってきて、自然に会話が生まれる場所にもなっています。



そうですね。さっき畑を見せてもらったんですけど、今は何が植わってるんですか?



今は夏野菜ですね。この間は玉ねぎを収穫して、それを焼いて子どもたちと食べたりもしました。今度のキャンプでも、その玉ねぎを持っていこうと思ってます。これからは、さつまいもも植えたいなと。焼き芋ですね(笑)。
それもまた、地域の方にも還元できたらと思ってるんです。独居老人の多い地域ですので、昔ながらの野菜の味を、今って値段も高騰してますし、少しでも地域の方に還元したいなという思いで、農園も作り、テラスも作りました。



農園は子どもたち以外にも地域の方々と一緒にやられたりするんですか?



できて1年経つんですが、今のところ、地域の方が直接関わってくださっているということはまだありません。でも、いろんなスタッフが「てだのふあ」にはいまして、農園に詳しい方もいるんです。そういう方が定期的に来てくださって、野菜作りや収穫を子どもたちと一緒に楽しんでいます。



そうなんですね!そんな素敵な「てだのふあ」のロケーションが伝わったかと思うのですが、実は、山下さんはもともと、小学校の教員をされていたそうですね。大学卒業後、すぐに教員になられたのでしょうか?



大学で教員免許は取ったんですが、すぐには教員にはならなかったんです。教育実習に行ったときに、当時の教育にすごく違和感を持ってしまって。管理的というかね。今よりずっと前のことですけど、当時からそう感じていたんです。
それで最初は学童保育所に勤めました。今みたいに公設ではなくて、自主運営の学童保育所で、保護者が出し合ったお金で指導員を雇って、という形でした。3つの学校から30人以上の子どもたちが集まってきて、アパートの2部屋の壁をぶち抜いて、そこを保育所にして、指導員は2人で見ていたんです。



でも、それでは生活は成り立たなかったんですね。



はい。当時は神戸の都心に住んでいたので、新聞配達をしながらその学童保育所を運営していました。本当に今のフリースクールとよく似てると思います。国の制度にのっていないけれど、必要だから生まれてきた。学童保育もそういう運動として始まって、今では制度化されています。指導員の身分保障もされるようになって。それを2年間やっていました。
そのままずっと続けてもよかったんですが、滋賀県に戻らないといけない家庭の事情が出てきて。それならば、教員免許もあるし、1回だけ採用試験を受けてみようと。たまたま受かったので、それから教員になりました。



私も小学校6年間、学童に通っていて、そのときはもちろん公共のものでしたけど、昔はあれが非認可、つまり民間の団体だったとは驚きました。



そうなんですよ。やっぱりそういうふうにして、生まれてくるんですよね。運動というか。最初は点にすぎなくても、それが必要だと思う人が増えてくれば、だんだん線になり、やがて面になって、国も認めざるを得なくなっていく。今のフリースクールも、まさにそういう段階にあると思います。この10年が、きっと大きな過渡期になるでしょうね。



じゃあ10年後には、フリースクールに行くっていう選択肢がもっと当たり前になるかもしれない。



そうですね。学校に行きづらさを感じている子どもたちへの理解が深まり、広がって、そこにもちゃんと予算がつくようになれば。学童保育所がすべての校区にあるように、フリースクールも、子どもたちや親が選べるほどになっていけばいいなと思っています。



では次に、小学校の先生をされていた時のことをお聞きしていきます。先生をされていた時から、不登校の子どもたちに対して、思うことはありましたか?



教員になって6年目、今からもう30年以上前のことですが、初めて「不登校」と呼ばれる子どもと出会いました。その出会いが、僕にとってはとても強烈だったんです。
当時、僕は小学5年生の担任でした。その子は4年生まで、登校はしていたのですが、教室には入れず、保健室に登校するという日々でした。その背景には、「何が何でも登校させたい!」という保護者の強い思いがありました。
その子との関わりの中で、僕は教員でありながら、「もう無理して学校に来なくていいよ」と伝えました。体に症状も出ていて、明らかに無理をしていたからです。
僕のクラスは36人いて、放課後に30分くらい、その子とだけ関わる時間がありました。毎日少しの時間ではありましたが、大切な出会いの時間でした。
でも、保護者であるお父さんやお母さんには、その子の状態への理解がなかなか得られなかった。そんなある日、その子が「こんなところで生きるのは嫌だ」と、日記に書いてきたんです。お父さんとお母さんに向けて綴ったものでした。それをきっかけに、ご両親の理解がガラッと変わりました。
そして6年生になると、その子は普通に教室に入っていけるようになったんです。この経験を通して、たとえ親であっても、子どもを理解することは本当に難しいと言うことを強く感じました。でも、子どもの「心の叫び」を受け止めてくれる大人が、たった一人でもいいからそばにいてくれることが、子どもが次の一歩を見つけるきっかけになるんだ、と。この出会いが、僕にとって「不登校」というものを考える大きなきっかけになりました。
以上のエピソードは、別の記事で詳しくインタビューをしています。気になった方は、ぜひ読んでみてください!



それで言うと、「親の会」も毎月1回、開催されていますね。



そうですね。苦しいのは子どもだけではなくて、お父さんお母さんたちもまた、相談ができない、なかなか頼れるところがない、吐き出す場所がないというのが、今の日本社会の現状だと思うんですね。あるお母さんは、「出口のないトンネルをさまよっているようだ」っていうふうに証言されましたし、「もう地獄の日々だった」って言われた方もいます。
子どもが、家でも地域でも不登校であっても、「ありのままでいられる」状態っていうのが、一番いいんですけどね。それが周りからも認められるのが本当は理想なんです。だけど、今の日本の社会では、「学校は行って当たり前」という学校中心の価値観が根強く残っていて……。だから、子どもたちも「学校に行けない自分はダメだ」と思ってしまうし、親も「学校に行かせられなかった自分は、子育てを間違えたんじゃないか」と、自分を責め続けてしまうんですね。
子どもの中にも、保護者の中にも、そうした“自己嫌悪”があって。それをどうしても払拭したいという思いで、「親の会」という場所を立ち上げたんです。そこは、本当に共感し合える、同じ悩みを抱えた人たちの集まりです。親御さん同士が、赤裸々に自分の思いをぶつけて、吐き出して……。そして「今のこのままでもいいんだな」って、「大丈夫だよ」って、安心して帰っていかれる。そんな姿を、よく見ています。



元々、「てだのふあ」を設立しようと思ったきっかけは何だったんですか?



私は教員生活31年のうち、4年早く辞めたんです。もうお腹いっぱいだったんですよ。担任も24回やらせてもらったし、組合やサークル活動、自分のやりたいこともすべてやり尽くした感があって。それで、「セカンドライフを楽しもう」と思ったんですね。
もともと山登りが大好きで、学生時代に出会ってからずっと続けていたんです。退職と同時に、「日本山岳ガイド協会」の公認ガイドの資格も取りました。それで、自分の好きな山登りを通じて、余生を楽しもうと考えていたんです。その頃、実際に海外の山にも登っていました。でも、やっぱり山登りだけでは食べていけませんよね。
そんな中で、児童相談所——正式には「子ども家庭相談センター」の一時保護所——で働くことになったんです。そこは虐待などの事情で子どもたちが一時的に保護される場所で、私はそこで指導員をしていました。
そこで出会った子どもたちは、本当に過酷な状況の中でも、前を向いて、何かを乗り越えようとしていたんです。その姿を見て、「もう一度、子どもたちと向き合いたい」と強く思うようになりました。
それなら何が課題かと考えた時に、一番に浮かんだのが「学校に行けない子どもたちの学習権」でした。一度ひきこもってしまった子たちには、学ぶ場所も、人と関わる場所もない。だったら、微力ながら自分にできることをやってみようと思ったのが、立ち上げたのがきっかけでした。
最初から大きな拠点を作ろうと思っていたわけではありません。むしろ、5人くらいでもいい、家庭のような雰囲気の中でやれたらいいと思っていたんです。スタートは週2回の活動でした。ちょうどコロナ禍になって、一人で来ていた子が3ヶ月か半年くらい続いたと思います。それが1年たつと、10人、20人と少しずつ増えていって。人数が増えるにしたがって、活動場所も変わっていきました。正直ここまで大きくしようとは思っていませんでした。本当に細々とやっていくつもりだったんです。
でも、私が思っていた以上に、不登校の子どもたちが多かったんです。そして、保護者の方たちの思いも本当に切実で…この4年間は、そのことを痛感した時間でもありました。
今は、2024年3月31日時点で登録者が40名。1日の平均通所は17人くらいでした。4月になると、進学や進級とともに学校に戻る子もいて、現在は平均14人くらい。登録者も30人ほどに落ち着いています。



そうだったのですね!そういえば、打ち合わせの中で印象的だった言葉として、「不登校は誰にでもなりうることで、他人ごとじゃないんです」っていうのがあります。



今の社会、特に日本の社会って、非常に閉塞感があると言ったらいいかもしれません。社会や学校は、決してすべての子どもにとって居心地の良い場所ではないと思うんです。居心地の良い場所ももちろんありますが、学校や社会、会社も、居心地が悪いと感じている人も少なくないと思うんですよね。
自分が居心地の悪い環境におかれたときに、「自分は強いから大丈夫」とか、「自分はこういうことができるから認められる」と思ってしまうことがありますが、僕はそれは決して正しい考え方じゃないんじゃないかと思っています。
実際、僕も教員としての経験を通してそれを感じました。どこか、みんなと一緒にやらなきゃいけないという「横並び」の感覚に押し込まれて、仕事に忙殺される中で、自分を見失いかけたこともあったんです。その時、「あれ?自分が自分を追い詰めているのかな?」と思ったことがありました。それって、倒れる一歩手前の状態になっているようなものです。
それは誰にでも起こり得ることだと思うんですよね。
強い人も弱い人も、性格に関係なく、環境がそうさせることがあると思っています。子どもたちも、学校に対する感じ方がそれと同じなんじゃないかなと思うんです。ある子にとっては居心地が良くても、別の子にとってはそうでないこともあります。先生との相性やクラスの雰囲気で大きく変わるかもしれません。だから、不登校やひきこもり、精神的に辛くなることって、実は誰にでも起こり得ることなんじゃないかと思うんです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。「てだのふあ」の建物の情景や山下さんの切実な思いが少しでも浮かぶといいなと思います。次回は自然教室など、てだのふあの素敵な取り組みについてもう少し詳しくお聞きしていきます。