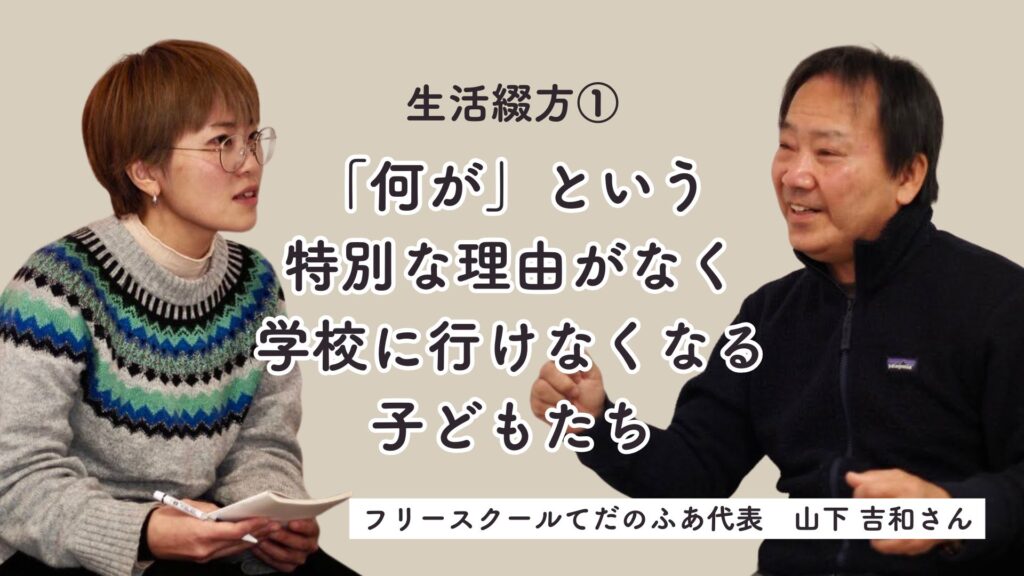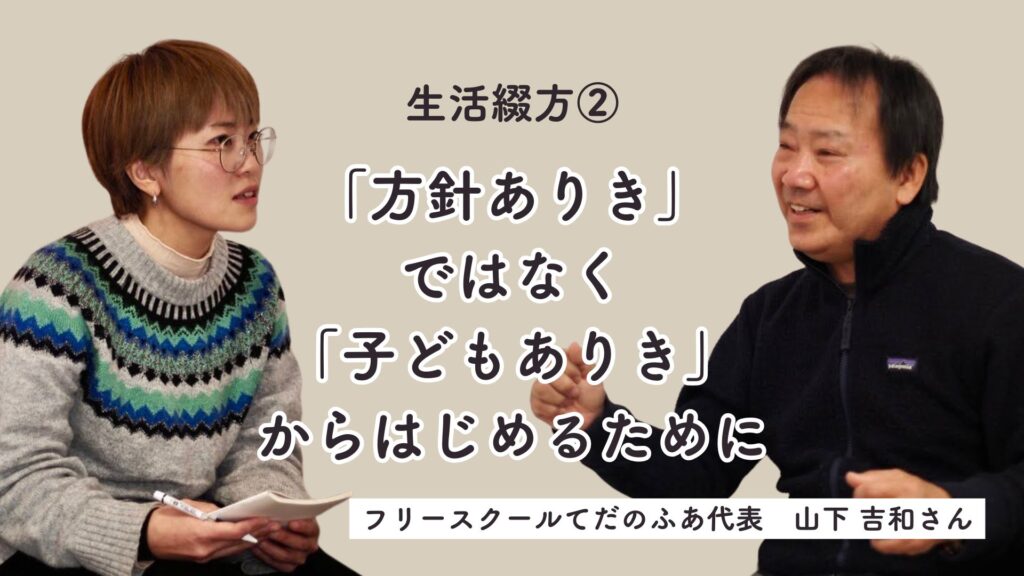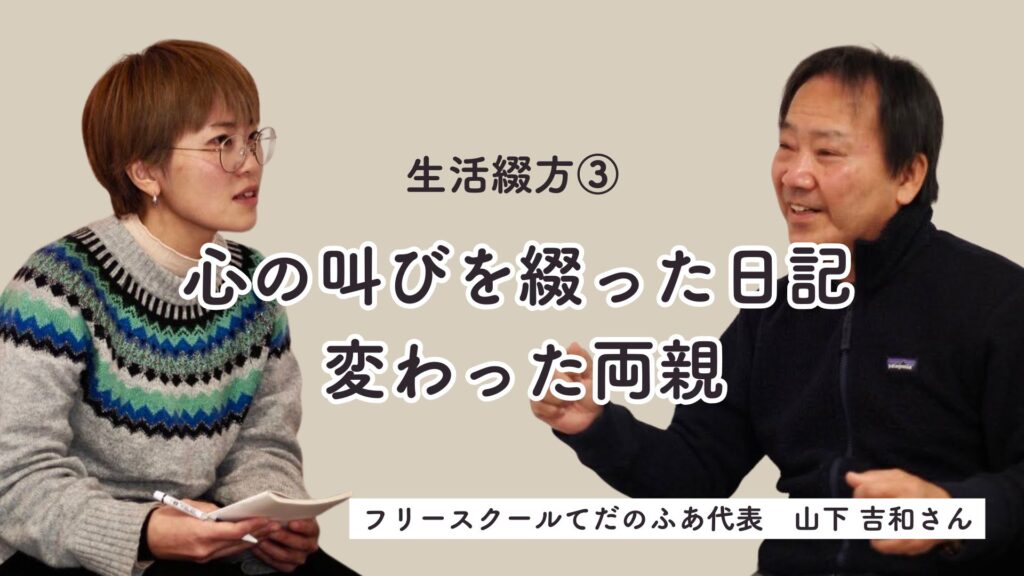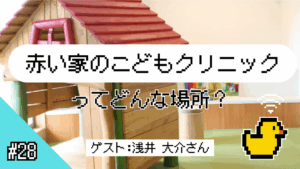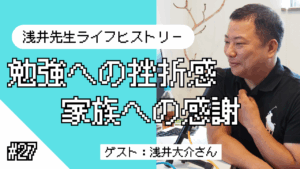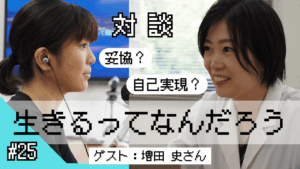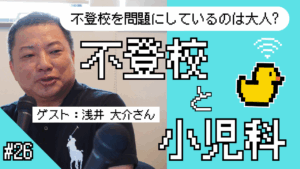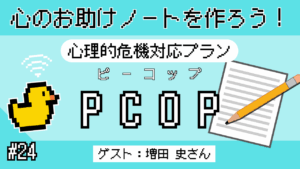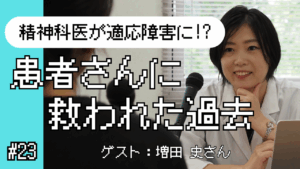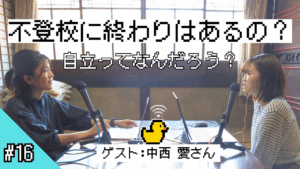本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第12回は、ゲストにフリースクールてだのふあの山下吉和さんをお迎えしています。山下さんが学童や学校の先生、そして児童相談所で働いてこられたご経験を踏まえて、今の社会にとっての学校や、フリースクール「てだのふあ」の役割についてお聞きしていきます。
山下 吉和さん
NPO法人 てだのふあ 代表
1961年、長浜市生まれ。87年、滋賀県教員となり河瀬小など彦根市内の小学校に31年間勤務。「生活綴(つづり)方教育」に力を注いだ。県中央子ども家庭相談センター指導員を経て2020年にフリースクール「てだのふあ」を開校。登山ガイド資格も持つ。植物保全「伊吹山ネイチャーネットワーク」事務局長。
【NPO法人 フリースクールてだのふあ】
滋賀県彦根市のNPO法人「フリースクールてだのふあ」は、不登校の子どもらの居場所づくりに取り組まれています。 てだのふあは沖縄の方言で「太陽の子」の意味です。「しぜんな成長」を支援しようと、学習の時間やスタッフらによる絵画教室など様々な教室を用意し、登山や座禅体験などにも取り組んでこられました。 代表を務める山下吉和さんは元小学校教師。「子どもに寄り添った活動をしたい」と、2020年にてだのふぁを発足されました。向き合ってきたのは音に敏感な子や対人関係に傷ついた子……。「心身共に開放し、のびのびと過ごして」と願い、不登校の親にも寄り添ってこられました。
📌 てだのふあ公式Facebookページはこちら
 井ノ口
井ノ口前回・前々回でもおっしゃっていたと思うんですけど、もともと学校の先生として働かれていたということもあって、学校の教育システムに対して、山下さんは強い思いをお持ちなのではと感じているんですが、いかがですか?



そうですね。教員になった頃から、学校というものを1年2年の単位で見るんじゃなくて、10年20年という長いスパンで見ていったときに、明らかに学校のシステムがかなり麻痺してきているんじゃないかと、私は感じています。もう少し具体的に言うと、管理が徹底されすぎているんです。たとえば「教員評価制度」。これは民間の仕組みを取り入れたもので、校長が教員を評価し、教育委員会が校長を評価する。評価された内容は、給料にも反映される仕組みです。でも、本来学校って「人間教育」の場ですよね?
モノづくりじゃなくて、人間を育てる営みなんです。そこに評価が入り込むっていうのは、すごく矛盾していると思うんです。その結果、教員の間でもものが言いにくい、横並びになる、自分の個性を発揮しにくい、そういう閉塞感が生まれてきているんじゃないかなと、実感しています。



つまり、先生もある意味、生徒のように「評価される立場」にある、ということなんですね。



そうですね。評価されている先生が、また子どもを評価するという構図にもなってしまっている。今の通知表を見ればわかると思うんですけど、道徳の内容まで評価されているんですよ。
子どもの心の内面、つまり人間としてのあり方まで、点数をつけるような教育になってしまっている。そして、「管理と競争の教育」。たとえば、学力テストが今も続いていることからも分かるように、子どもたちは常に比較され、競わされている。それに加えて、「同調主義」ですね。これは、子どもの中にも先生の中にもあるんじゃないかと思います。みんなと同じであることが求められる空気。それが今の学校の現状じゃないでしょうか。



山下さんご自身、子どもたちに成績をつけるときに葛藤を感じたことはありますか?



もちろんあります。まず「所見」っていうのがありますよね。子どもに返す文章。ここでは、子どもを認める視点でたくさんのことを書いてあげたい。でも、書ける文量には限りがある。
そして通知表。どういう評定にするかというのは、本当に最後まで悩みます。テストの点数だけで決められない部分もありますから。でも、どうしても「頑張ろう」っていう評価をつけなければいけない子もいる。そんなときは、「これは先生の思いやで、一緒に頑張ろうという気持ちを込めてつけてるんやで」っていう話は子どもにしていました。
それから、僕がやっていたのは、「先生の通信簿」を子どもに書いてもらうことです。学期の終わりに、子どもたちに自分自身(先生)をいろんな視点から評価してもらう。それを自分の成長の糧として、厳粛に受け止めていました。



すごい!辛辣な評価も返ってきたりするんですか?



もちろん(笑)。でも子どもって、何でも言いやすい先生には言えるし、顔色を見て言えないこともある。
僕は、子どもたちに「日記」を書かせていました。教員になってから31年間、24回担任を持たせてもらいましたが、そのあいだ毎日のように子どもに日記を書いてもらっていました。それを「一枚文集」として編集するんです。テーマを決めて、自由に書いていいし、書かなくてもいい。3行でもOK、何も書かなくてもOK。それを毎日集めて、編集して、授業の中で読み合う。
書いた子は、まずみんなから拍手をもらって、感想や質問をもらって、最後に先生がコメントをして、また拍手で終わる「書いてよかった」「授業してもらってよかった」っていう気持ちが残るんですよね。そういうことを毎日続けていくと、子どもたちの結びつきがどんどん強くなるし、先生とも信頼関係が生まれてくる。それは僕にとって、子ども理解を深める手段だったんです。
当時はそれを「生活綴方」と呼んでいました。今ではもう死語になりかけてるかもしれない。現場の多忙さの中で、日記を書かせること自体が難しい。赤ペンでコメント書くのも大変ですからね。でも、僕はそれをずっとやってきた。
今、てだのふあでは同じようなことはしていませんが、子どもが発した言葉や、きっかけをもとに表現したものは、「てだのふあ通信」などを通じて発信しています。子どもの表現を大事にするというスタンスは、今でも変わっていません。でも、そういうことが今はしにくくなっている。
上からの「やらされ感」がすごく強いんです。英語教育しかり、GIGAスクール構想しかり、「これをやりなさい」っていうことがどんどん降りてくる。先生たちは本当にやりたいことが後回しにされてしまう。だから、単に忙しいだけじゃなくて、「やらされ感」によって、先生たちが疲弊している。
教員っていうのは、本来自主的で創造的なもの。子どもと一緒にいろんなことをつくり出していく、そういう存在のはずなんです。たぶん、どの先生も、最初は「子どもたちとこんなことをしてみたい!」っていう思いで教員になっているはずなんですよ。でも、実際に教員になると、なかなかそれができない。よっぽど僕みたいに「開き直る」か、「嫌われてもいいから自分を貫く」って思わないとできない。それってやっぱり勇気のいることなんですよね。



4月にゲストでお話しいただいた伊藤いつかさんも、小学校の先生をされていたんですけど、やっぱり同じようなことをおっしゃっていました。
昔は、先生って教えるだけじゃなくて、しんどそうな子がいたら話を聞いたり、その子の家庭の事情を引き受けたり、福祉的な役割も担っていたと。今はそれがいいのか悪いのかは分からないけれど、大きく変わってしまったと感じていると。



伊藤さんが言われたような、子どもたちのケアとかサポートって、昔は私たちでも、気になる子の家に足を運んで、家庭訪問をして、宿題ができない子に教えたりしてたんですよね。
でも、今はもうそんな余力はないんです。先生方にやるべきことが山積していて、しかも先生の数が全然足りない。今の教育現場って、10しかできない仕事を、15とか20やらされてるような状態です。そこに、もう根本的なシステムの崩壊がある。
じゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱり教員の数を増やす、倍増する。20人学級にしていく。今は35人学級を進めてますけど、欧米のように20人学級にしていくのが、世界の流れです。大きく遅れているのが日本だと思います。
今、不登校の子どもたちってすごく増えてきていて、調べればすぐに分かります。それに合わせて、フリースクールを利用する子も増えていると思います。今って、学校が変わっていく過渡期で、そういう時期に、てだのふあのようなフリースクールは、社会にとってとても大きな役割があると思うんです。
社会にとってどうこうというよりも、学校に息苦しさを感じている30万人の小中学生が、「NO」を突きつけている。学校に対してね。学校が変わるのが一番なんですが、現実的には、学校に行けない子どもたちの受け皿が本当にないんです。
家にいるか、学校の別室に行くか、市がやっている支援センターに行くか。その中で「合う」環境があればいいと思っていて、別室でも支援センターでも、その子にとって「合う」環境が大切なんですよね。でも、やっぱり数が全然足りていない。
フリースクールもようやく全国的に500〜600と増えてきて、ようやくどこの地域にも、1時間圏内に1つあるかないかくらい。でも、それはとても重要なことです。
不登校になってしまうと、家から外に出るまでの「壁」がとてつもなく大きいんです。僕たちが想像する以上に、高くて厚い壁。その中で、家で過ごしていた子が「一歩踏み出したい」と思う時期が来るんですね。
でも、学校はハードルが高い。「家からは出たい、でも学校は無理」っていうときの場所が、フリースクールなんだと思います。家でも学校でもない、第三の居場所。その居場所で過ごす時間が、その子にとって本当に尊いものになっていくと思う。
人と関わったり、自然に触れたり、いろんな体験を通していろんな人と出会ったり。そういう経験が、将来社会で自立していくための土台になるんじゃないかなと感じています。



最後の質問にいきたいと思います。
山下さんのFacebookを拝見していて、すごく印象に残った投稿がありました。子どもの権利について、児童会や小学6年生の社会科で取り上げて、現実と照らして話し合ったという話です。



子どもの権利条約って、子どもの視点で書かれていて、「子どもは幸せに生きる権利がある」っていう、その視点がやっぱり大事だなと思うんです。それを子どもたちが実際に見た時に、自分たちが普段「当たり前」と思ってなかったこと、大人の権利だと思っていたことが、実は自分たちにも保障されているって気づくんですよね。
実際に条文を読んでいくと、「これ、自分たちにもこんな権利があるんだ」って驚きや感動があると思う。だからこそ、今の現実とのギャップにも気づく。今の社会が、まだ子ども視点になっていないということが、よく見えてくるんですよね。当時の子どもたちもそうでしたし、今の子どもたちにも、ぜひこういう教材を使って授業してほしいなと思います。読むだけでも、何かが変わるんじゃないかなと。



そのあとに続いていた投稿も印象的で、「ついつい子どもに口を出してしまう」「知らないうちに価値観を押し付けてしまう」「子どもと対等に話すのは本当に難しい」と書かれていました。そこについても、お聞きしたいです。



そうですね、本当に難しいです。例えばキャンプをやるんですけど、その後に「語り場」っていう時間を設けていて、夜の10時くらいに焚き火を囲んで、「来たい子は話そう」という時間をつくるんです。そんな時間、学校では考えられないですよね。
そういう時は、子どもと自然体で話せるし、意見も素直に聞ける。でも例えば、子どもたちから「この時間にもゲームをしたい」っていう要求が来たりするんです。僕はゲームそのものを否定してるわけじゃないんだけど、やっぱりリアルの時間も大事にしてほしい。
だから、昼食の時間とか「ミータイム」と呼ばれる時間では、ゲームはやめようとルールを決めているんです。でも、子どもからすれば、「ゲームってそんなに悪いの?」っていう気持ちもあって。
子どもたちからのそういう問いかけに対して、自分もすごく揺れるんですよ。わがままだとは思ってなくて、子どもからすれば筋が通ってるし、理屈も分かる。だから、子どもの意見を「聞く」っていうのは、ただ聞くだけじゃなくて、共感的に受け止める。でも、それを100%そのまま叶えるわけじゃない。どう折り合いをつけていくか、スタッフと子どもで一緒に考えていくことが大事なんだと思います。
子どもたちの願いって、本当にいっぱいあります。「聞いて聞いて」「お父さんやお母さんにこんなこと言われたんよ」って、いろんなことを話してくれる。



確かに、私自身もそう聞くと、反省しないといけないところがたくさんありますね。



子どもの声を「聞く」って、ただ耳に入れるだけじゃなくて、「傾聴」するってことですよね。耳を傾けて、ひたすら聞く。でも、それって本当に難しい。私たち、プロのカウンセラーではないから。
そういう意味で、子どもの声を最後まで聞くっていうのは簡単なようで本当に難しい。しかも、人間関係ができてなければ、子どもは本音を話してくれないと思うんですよね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
学校の先生も本当に今、大変な状況に置かれていて、てだのふあも日々試行錯誤しながらやっている。まさに、みんなが手探りの状態だということが、よく分かりました。次回はてだのふあ編最終回。てだのふあの今後のことについてお聞きしていきます。