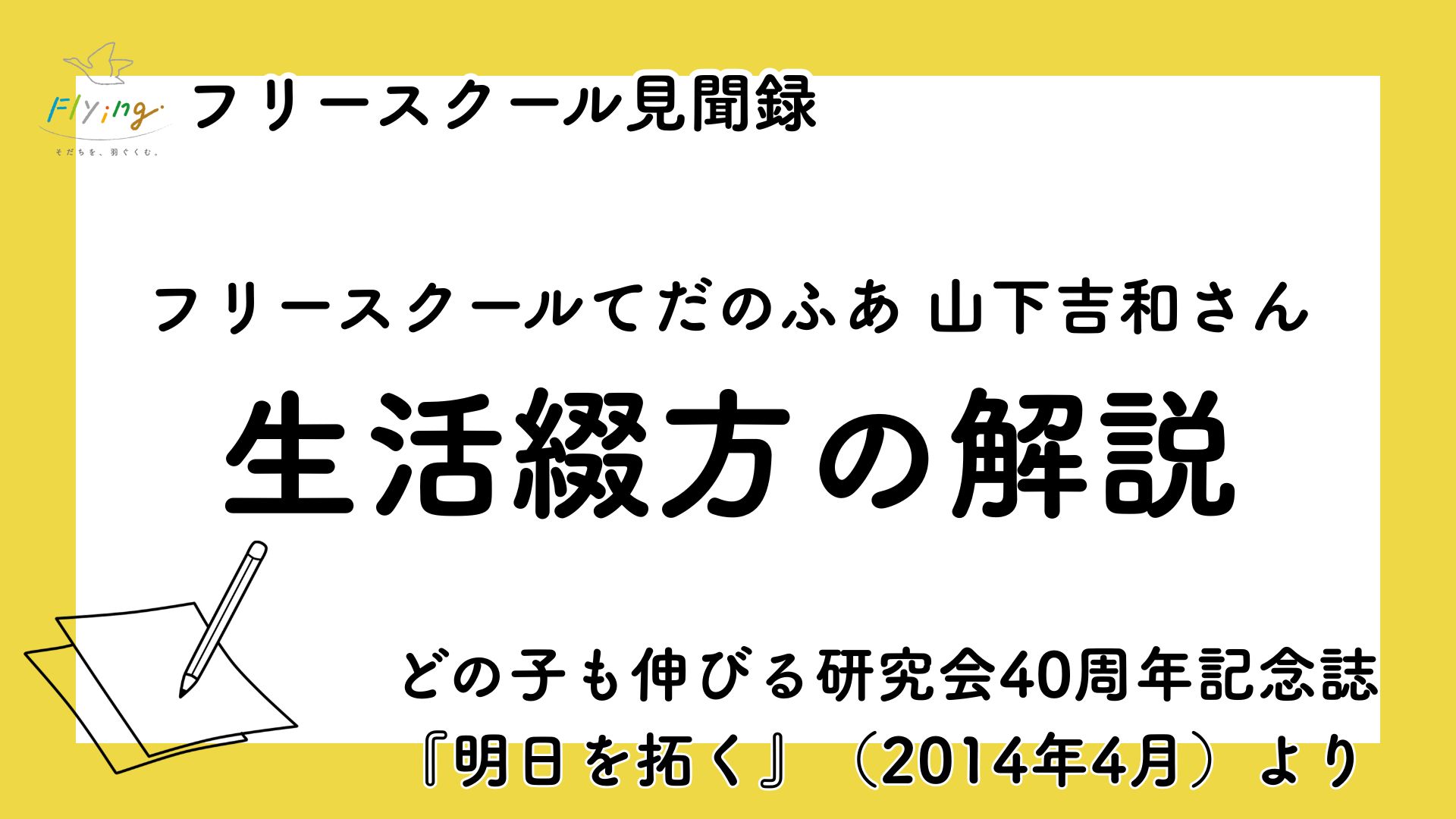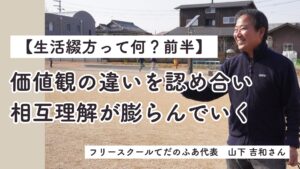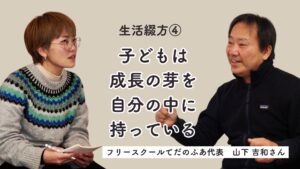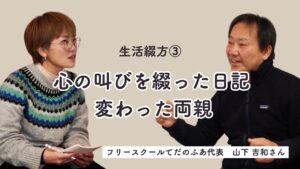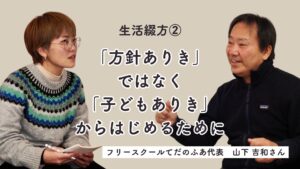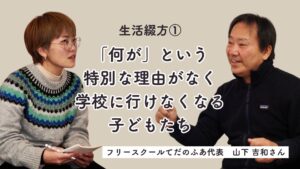彦根市京町のNPO法人「てだのふあ」は、築100年の改装された古民家で運営する不登校の子どもたちのためのフリースクール。2020年に設立され、今では小学生から高校生まで約30人の子どもたちが通います。今のフリースクールの指針にも関わっているという、教員時代に実践していた「生活綴方」について、かつて山下さん自身が記した解説をご紹介します。
どの子も伸びる研究会40周年記念誌『明日を拓く』(2014年4月)より
生活綴方実践 山下吉和

「生活綴方」は、その内容において次の三つを大切にしている。
子どもをとらえるために、生活綴方を大事にし、生かしていくこと。【子ども理解】
集団づくり、仲間づくりに活用し、役立てること。【学級づくり】
人権意識を育てるうえで綴方を大切にするということ。【人権意識の高揚】
子どもの側からすれば、次のように言い換えることができる。
自分のことをもっと理解してほしい。認めてほしい。
みんなと人間的なつながりをもちたい。うれしいことも悲しいことも共感しあいたい。
自分の人権、みんなの人権が守られている学級、学校をめざしたい。
これは、今日のきびしい世界を生きる子どもたちにとって、基本的な願いではないだろうか。現象としては、この対極にあるように見える子どもたちほど、心の奥底に「強く」 これらが潜在しているのだと考える。
生活綴方は、国語科の一領域でもあるが、子どもたちの「生活現実」を教材にした授業を創造していく営みでもある。日々の教育活動に生活綴方を生かすということは、どの子にも「主体的な生活姿勢」と「生活意欲」を育て、「書く力」を高める。学習と実生活を結合させて、生きて働く認識力を形成していくことにある。
そのための道筋は、どの子も伸びる研究会の「めざすもの」(案)には以下のように示されている。
すべての子どもに、自己表現・自己主張を保障します。
書くことを通して、くらしの事実やものごとを本気で見つめる態度を育てます。
自分のことばでありのままを綴る態度と力を育て、その中で問題を見つける力を養います。
自分のとらえた事実にもとづいて考え、事実にもとづいて認識する力を育てます。
仲間との話し合いを通して、ものの見方・感じ方・考え方を正しく伸ばし、生活を高める力として生かしていきます。
書き綴ること、読み合い話し合うことを通して、ことば・表現の力を伸ばし、豊かな感性・心情を育てます。
これらの学習を通して、同じ人間としての共通の願いを自覚し、相互に理解し合い、連帯を高めます。
以上のことを基本にすえて、次の三つの内容を特に大切にしていきます。
一つめは、子どもをとらえるために、とりわけ綴方を大事にし、生かしていくことです。子どもをとらえるとは、生活の事実を通して、その姿と心をまるごと理解することです。それは、一人ひとりのよさや可能性の発見であり、悩みや問題点、そして、願い・要求を明らかにしていくことです。ことばを変えていえば、体と心、諸能力の発達などにかかわって、人間らしく生きることが現実にどうなっているのかを具体的につかむことです。
二つめは、民主的な集団を育てるために活用し、役立てるということです。自他の人権を大切にし合う学習は、「なんでもいえる仲間」「本音がだせる集団」がなければ成立しません。ありのままを綴り、素直に語り合うことを通し、ある時は、仲間の共通の願いを、 また、ある時は、違いを理解し合っていく中で連帯と団結の意味とその重要性を発見させていくことができます。そうした子どもたちの実生活に根ざした集団づくりに生活綴方を役立たせていくということです。
三つめは、人権意識を育てる上で綴方を大切にするということです。ありのままに綴った作品を通してさまざまな生活現実にふれ、そのなかにある矛盾や不合理、悩みに気づき、 それらの原因がどこにあり、どのように発生しているのかを学び合うことができます。それは、おかしいことにおかしいと気づくことであり、それが人権へのめざめをさそう出発点となります。
(以上、どの子も伸びる研究会の「めざすもの」(案)より)
生活綴方の真髄は、自分の言葉で本音を綴ることにあると考える。子どもたちがそうであるように、綴ることには多大なエネルギーを要する。テーマを決め、 整理し、自分の考えや感じたことをぶつけていく。対象が何であったとしても、究極のところは自分自身と向き合うことになる。