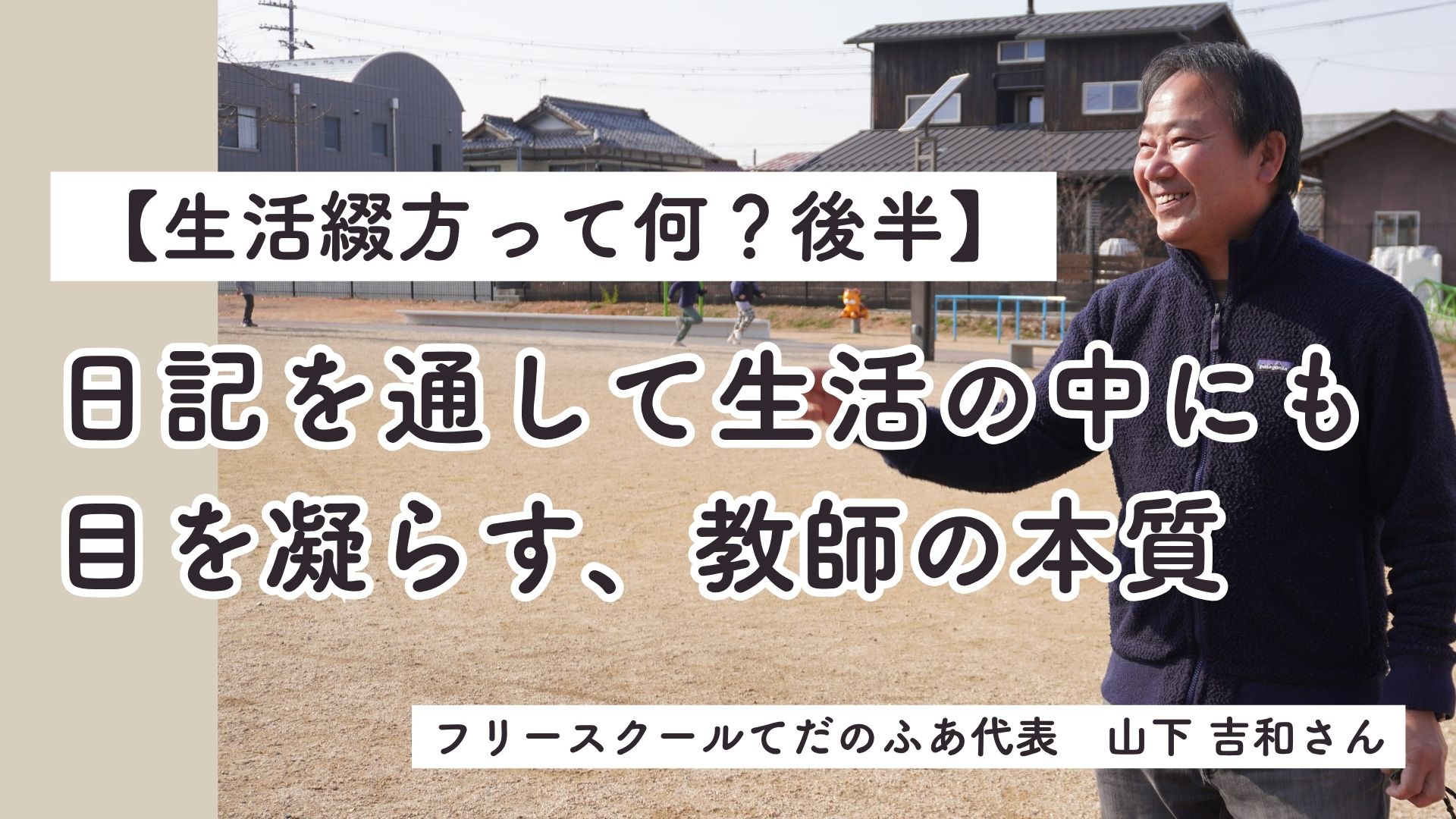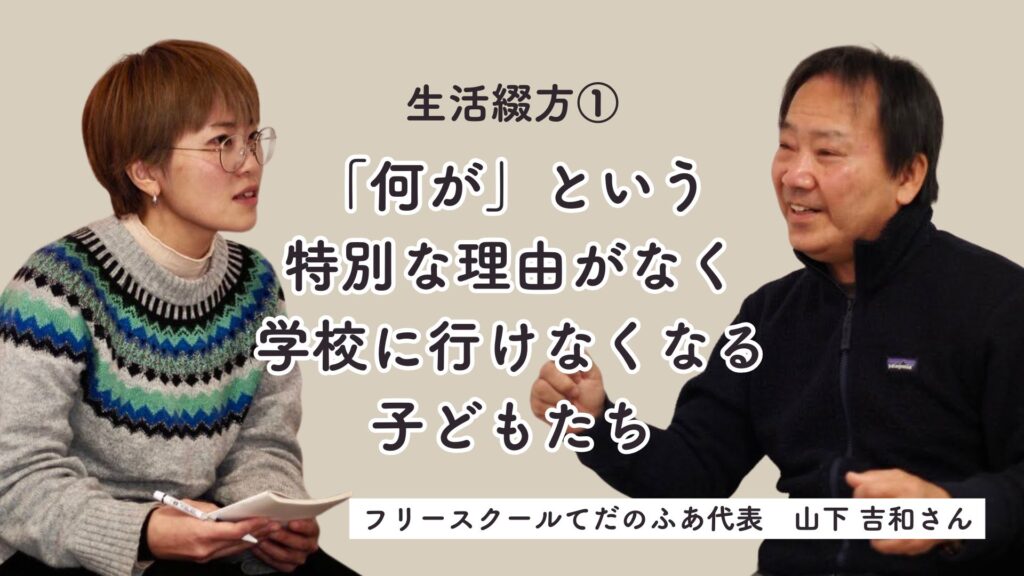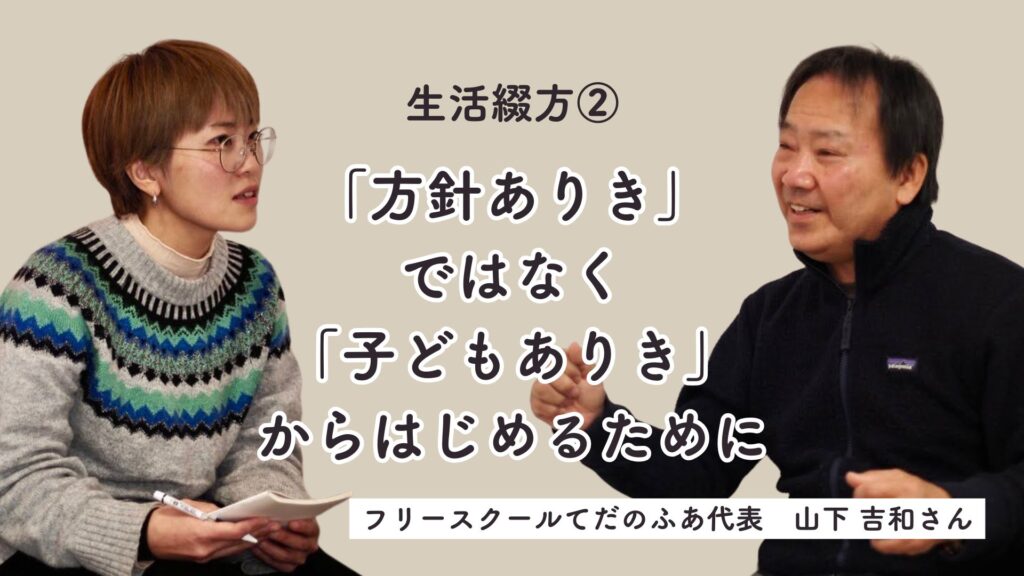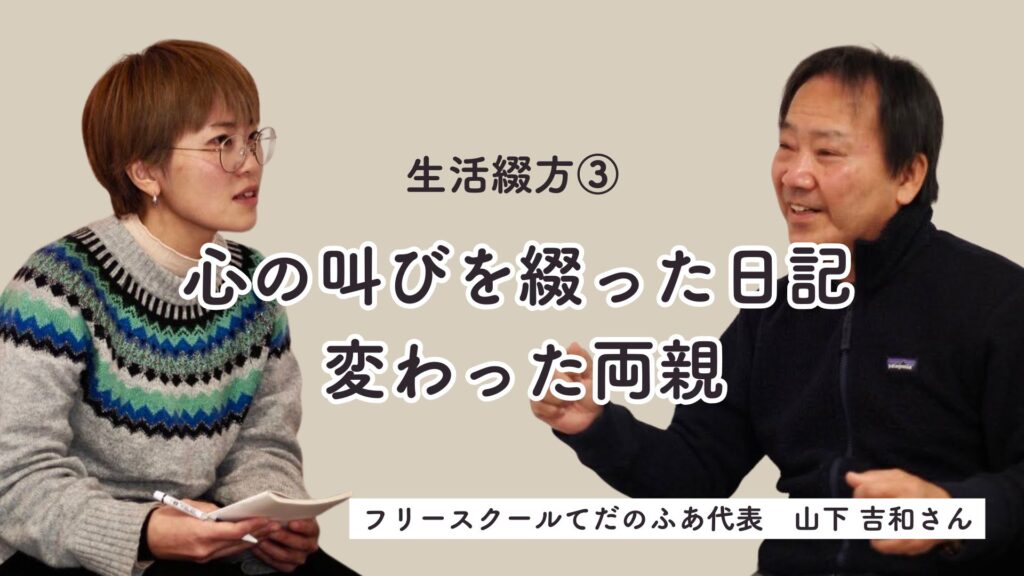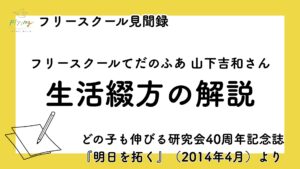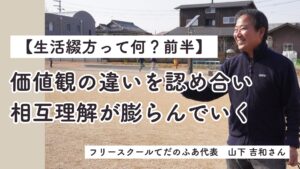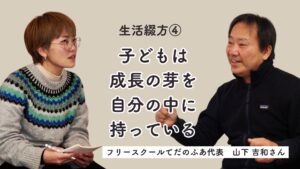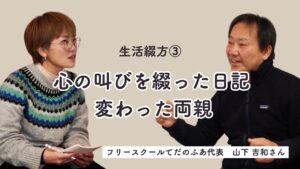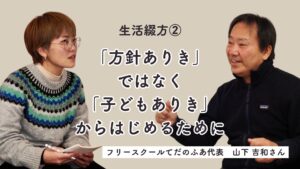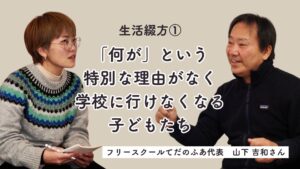彦根市京町のNPO法人「てだのふあ」は、築100年の改装された古民家で運営する不登校の子どもたちのためのフリースクール。2020年に設立され、今では小学生から高校生まで約30人の子どもたちが通います。「すべての子どもたちは成長の芽を持っている」と語る代表の山下吉和さんには、そのことを実感した体験がいくつもありました。
今シリーズでは、今のフリースクールの指針にも関わっているという、教員時代に実践していた「生活綴方」について、2回に分けて聞きました。
――生活綴方について勉強したいと思ったら、おすすめの本はありますか。
長浜に河瀬哲也先生という人がいます。僕は学生時代に河瀬先生の『人間になるんだ』という本を読んでいました。元々その本を読んでいたら、教師1年目のときに佐和山小学校の先輩から誘われて、連れて行かれたサークルに、その河瀬哲也さんご本人がいたんですよ。この河瀬先生の『人間になるんだ』の舞台が「河瀬小学校」でした。それで、僕は当時の校長に河瀬小への異動希望を出しました。それで、赴任2校目が河瀬小学校で、11年いました。

――憧れの河瀬先生と一緒にお仕事ができたんですね。
はい、一緒に仕事をしました。たくさん助けてもらいました。いっぱい教えてもらいました。一緒に働けるのは、とても嬉しかったのですが、とにかく厳しかった。
だから、それが僕の原点なんですよね。授業は、全て公開。実践を何よりも大事されていたので、どんな状況で、どんなに学級が大変なときでも、原則公開でした。僕らも文集を作ったら、自分だけで終わらすのではなく、事務職員も含めた全ての先生に配りました。読んでくれた事務の先生が、「かなちゃんの作文よかったね」などと感想を言ってくれるんですよ。「生活綴方」が校内全体の研究のテーマになっているような学校でした。
もちろん当時としても、そんな学校は他にありません。学習というよりは、綴方の実践が重視されていました。もうとにかく、子どもありき、子どもに良かれと思うようなことをどんどんしなさいと。だから、「ケンジとの実践」もできたのだと思います。
――不登校のケンジ君のほかに、生活綴方の実践はどんな形で行われていましたか?
ケンジの実践のほかにも、本当に課題のある家には足を運ぶということも大切にしていました。例えば、五年生になっても九九が全くできない子がいました。母子家庭の女の子で、ハナちゃんと呼んでいました。
ある時、 「ハナ、今日家行くからな。家にいててや」と伝えて、5時くらいに家へ行ったら、ハナはひとりで猫と遊んでいました。「お母ちゃんは?」って聞いたら、「まだやで。先生な、母ちゃんいつももっと遅いで」って言うので、「待たしてもろうてええか」と伝えて、待っている間に一緒に宿題をしていました。
でも、お母さん、7時になっても帰ってきやらん。もう8時ぐらいに帰ってきました。そこで初めてお母さんの労働を僕は知るわけです。ハナが、そういう状況の中で学校に来とるだけでもね、すごいなって思いました。子どもの生活を知って、見方がここで変わる。
河瀬先生から、「子どもを理解するには、生活を知りなさい」という風に僕らは教えられてきました。ハナの場合、家庭訪問して、お母さんの労働がわかった。その中でお母さんにね、「ハナが九九ができていません。一緒に協力するから、忙しいけど、ここだけは聞いたってください」とお願いしました。お母さんも喜んでくれて、親との関係性もできていきました。
家を訪問するというのは、こういうことなんですよね。子どもの生活の背景を知ることで、ハナへの理解が深まり、手立てを講じることができる。生活綴方の思想というのは、すごい実践やなっていう風に僕は今でも思っています。
日記から見るというのもあるし、日記から書かれた事実から、実際に訪宅などで確かめていくっていうのもあるし。生活を知るということが、子どもを知るということに繋がっていく。
――生活綴方の思想を通して、生徒の実際の「生活」の中にも先生の目が届いていたんですね。
今は、6時になったら、学校も電話が繋がらないようにしています。職員室に先生がいても電話がつながらない。働き方改革のひとつだと思いますが、僕はそれが現場の改善につながるとは全然思っていません。教師の仕事と働き方改革は一緒にしたらあかんと思っています。
だって、教師の本質じゃないですか。生産的であって、主体的であって、創造的であって、それが本来の仕事やと僕は思っています。でも、もうそこまでやる必要ないやろっていう諦め感が教師の中に広がっている。
労働時間を短縮することはもちろん大事なことなんだけど、 何を短縮するかです。次から次へと矢継ぎ早に、ギガ教育構想とか、英語とか道徳の教科化とかがいっぱい入れられています。今は、そんな労働時間が増えて、やらされ感ばかりが募る仕事が多い。だから先生たちももう割り切って働いている。働き方改革っていうのは、結局教員の仕事を奪っている、 生き甲斐を奪っているということに僕は繋がってるんじゃないかなと懸念しています。




完