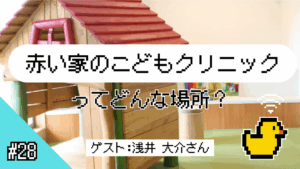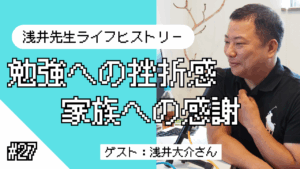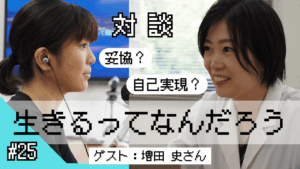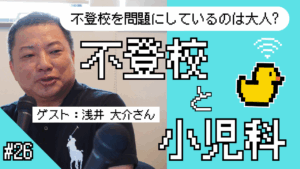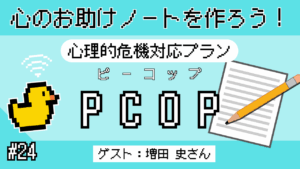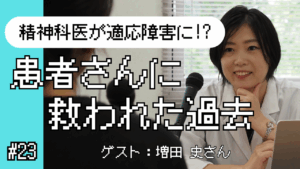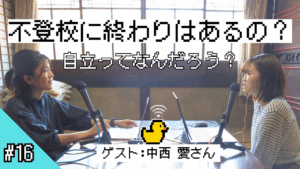本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第7回は、ゲストに日野里山フリースクールスタッフの玉崎蕗さんをお迎えしております。今回は勉強や運営のことなど、日野里山フリースクールのことを詳細にお聞きしていきます。
【一般社団法人 日野里山フリースクール】
滋賀県日野町の自然豊かな山間にある古民家を中心に毎週月〜金曜日にフリースクールの活動を行われています。対象は小学生〜中学生です。
場所:滋賀県蒲生郡日野町蔵王490
活動:月曜日〜金曜日 9:30~15:00
日野里山フリースクールのキャンプのような日常
 井ノ口
井ノ口最初に、現在のフリースクールの建物が素敵なので
その話から行きましょうか。



はい。成り行きで始めたフリースクールだったので、まずは拠点がない状態から始まりました。初めの1年弱くらいは、間借りしたカフェや公園で活動していました。その後、2022年の4月に、日野町の蔵王っていう地域の古民家をお借りさせていただくことになりました。そこが築60年の、空き家になって長い古民家でした。だから、電気だけはかろうじて来てたんですけど、水道・トイレ・ガスがないという状況でのスタートでした。



ええ!そうだったんですね!



最初はカセットコンロや薪で料理して、トイレは目の前にある公園のトイレをお借りして、その横にある、足を洗うような水道で食器を洗ったりしていました。ようやく、今年の冬からガスが来て、お湯でお皿を洗えるようになりました。でも、まだトイレはないという状況です。この先、助成金を活用して、この先2年以内にはトイレや建物も改装していく予定です。(※2025年時点では、改装が完了しているようです。)



お昼ご飯も自分たちで作るんですか?



週に3・4回は料理をして、週に1・2回はお弁当っていう感じですね。料理をする日の中にも2種類あって、自由料理の日は、一人一人が好きなものを作る日。その日の使い易い食材とか旬の食材を自由に使って料理します。料理の日は、料理当番が事前に決まっています。担当の子が何を作るのか決めて、買い物リストを作ってくれているので、例えば鶏肉って書いてあったら、スタッフが鶏肉を買ってきて、それを使ってご飯を作ります。
焚き火も自由にできる環境なので、ご飯は羽釜で炊いてみたりとかする日もあるし。この前なんか、焼き鳥をしたんですけど、代表のえっちゃんが「もう串から作ろうや!」とか言って、竹切りに行って串から作って焼き鳥をしました(笑)



え〜!子どもたちもノリノリなんですか?



「めんどくさい」って言う日もあるし、「よっしゃ自由料理や!」みたいにノリノリの日もあります。でもやっぱり、自分で料理を作れたってことが、その子の自信にもなってるみたいで。後から、「フリースクールで作ったやつを家族に作ったよ」って聞くこともあって、そういうのを聞くと嬉しいですね。
勉強はどうしてるの?



「学力の遅れが心配」っていう声もよく聞きますが…。日野里山フリースクールで、勉強する時間はあるんですか?



ここはずっと、試行錯誤を続けてきたところなんです。やっぱり、フリースクールに来ている子どもたちは、学習に対する抵抗感がすごく大きくて。すでに「勉強=嫌なもの」っていう印象が強く残ってしまっているんですね。
だから最初のころは、あえて学習っぽいことはあまりやらないようにしていました。でも最近は、「どんぐり問題」という、絵を描きながら解く算数の文章問題を取り入れていて、これはあまり勉強っぽくないので、けっこう楽しんで取り組んでくれる子もいます。
さらにこの半年ほどは、朝の時間に30分間、「自分の時間」というのを設けています。その時間は、静かにそれぞれが自分の学習に取り組んだり、学習への抵抗感が強い子は、静かにできることを選んで取り組んだりしています。たとえば、九九や漢字の練習をしたり、算数の教科書を見ながらスタッフと一緒に勉強したり。中にはプログラミングに取り組んでいる子もいたりします。



1日中勉強している学校と比べると、すごく自由時間が多いですね。



「遊んでるだけじゃないの?」とか多分疑問に思われる方も多分いらっしゃるんじゃないかなと思います。でも、私はこの自由な時間っていうのがもうほんまに、かけがえのない大切な時間やなって思ってます。
それは、私自身がこの3年間、子どもたちと関わる中で強く実感してきたことでもあります。子どもたちは、子ども同士の関わり合いの中から、本当にたくさんのことを学び、成長しています。
ある時、まるで王様のように振る舞って、周りに命令ばかりしている子がいたんですね。子どもたちは素直だからこそ、
「なんで命令されなあかんの?」
ってまっすぐに感じて、自分たちで関係を築いていくんですよね。その子はあるとき、
「このままじゃ、みんな自分から離れていってしまうかもしれない」
って自然と気づいたんですね。それから、その子は本当に変わっていきました。人に命令したり、仲間外れにしたりすることをやめて、優しくなっていったんです。
そういう変化が、ここでは日常的にたくさん起きています。これはきっと、大人との関係の中だけでは生まれにくいものだと思います。フリースクールには、情緒面に課題を抱えている子も多く来ていますが、そういう子たちにとって、社会に出てまず苦労するのは、勉強よりも情緒の面だと思うんです。だからこそ、自然にけんかしたり、仲直りしたりできる環境があるというのは、その子にとって本当に大事なことだと感じています。



なるほど…。



子どもの権利条約とか教育基本法とかにも書かれているんですけど、教育の目的って勉強だけじゃないんですね。子供の権利条約、教育の目的29条っていうところがあるんですけど、それは結構いいことが書いてあって
「教育の目的は子供の人格や能力を最大限に伸ばしていくことであり
人権や平和・多様性・自然環境を尊重する考えを育むこと」
っていうのが教育の目的やっていう風に書かれています。
そこには、日野里山フリースクールも沿った活動ができてるんじゃないかなと思っています。例えば、やっぱり自然の中でたくさん遊ぶ経験があったからこそ自然を尊重できる人になると思うんですね。大人になった時に、なんか川汚れてるなーとか、木切られてるなとか、そういうことに心が痛む人になってほしいなと。あとは海外からも、ゲストさんやボランティアさんなどいろんな人が関わってくれてるので、いろんな人と出会って話すことが、多様性とか平和とかそういうことにもつながる学びになってるんじゃないかなと思ってます。



教育の目的って、勉強だけじゃないのが衝撃です。



勉強の面で言うと、日野里山フリースクールを卒業して、今は私立の中学校に通ってる子が二人いるんです。その子たち、どちらも小学校4年生ぐらいまでは、ほとんど勉強してなかったんですよね。でも、ある時から「勉強したい」って自分で思うようになって、お家で少しずつ始めていって。結果的には、難しい受験にも合格して、ちゃんと通ってたりします。もちろん、人によって状況は違うんですけど、ある程度の年齢になったときに「小学校の勉強くらいなら追いつける」っていうのは、実感としてありますね。
とはいえ、あまりにも社会とのギャップが大きくなってしまうと、その子自身が生きづらくなってしまう可能性もあるので、ちょっとだけプッシュすることはあります。たとえば「30分だけやってみる?」とか、「九九くらいはできた方がいいよ〜」とか。そういう声かけはする時があります。
漢字の学習にしても、「なんでやらなあかんの?」って話をしたときに、
まずは「私はみんなのこと天才やと思ってるで」って伝えるんですね。
「虫博士になりたい子もおるやん? でも漢字が読めへんかったら、大学入試で答え分かってても点取られへんかもしれんよ」
とか、
「免許取りたいって思っても、問題が読めへんかったら受けられへんねんで」
とか。
そういう現実的な話をすると、「じゃあちょっとやってみようかな〜」ってなる子もいたりして。
今はちょうど新学期が始まって、フリースクールに来てた子の中で、学校に通い始めた子が少なくとも3人はいます。去年まではほとんど行ってなかったけど、「新学期やし行ってみようかな」って、何回か学校に行ってる子も何人かいて。
私たちのほうからは、「学校行った方がいいよ」なんて一言も言ってないし、親御さんも多分言ってないと思うんです。学校に行くのがいいとか、行かへんのが悪いとか、そういう風には全く思ってないけど、それだけ自信がついたってことなんかなぁ、って感じていますね。



そうなんですね!子どもが納得して、自分から動くのを待ってるんですね。



そう、だから、フリースクールがあることで「不登校が助長される」とか、「余計増やすんじゃないか?」っていうような意見もあったりするんですよ。でも、まずはエネルギーを貯めることができてくると、「行け」とも言ってないのに(学校に)通い始める子がいるって言うのもすごい面白いことやなと思います。
日野里山フリースクールの今後



最後の質問ですが、フリースクールやっていく中で、大変やなーとか、ここが難しいなって思うところがあれば教えて欲しいです。



私たちは、本当にゼロからのスタートでした。最初は何がいいのかもわからない状態で、ずっと試行錯誤を続けてきました。たとえば学習のことも、「こういうやり方がいいんちゃうかな?」と思って導入してみるけど、うまく続かなかったり…。「ああ、これはうちには合わへんかったんやな」っていうのを、何度も何度も繰り返してきました。
料理の時間やルールづくりなんかもそうで、「こうしたらいいんちゃうか?」って考えてはやってみて、また修正して…をずっと続けてきました。それは、大変だったことのひとつです。
それと、やっぱり一番大変なのは“経営面”ですね。今(※2024年4月時点)は行政などの公的サポートは受けずに運営していて、保護者さんからは1日2000円の参加費をいただいています。毎日通ったとしたら月に4万円。
日野町から月に5000円、保護者に向けた補助はあるものの、これは家庭にとってかなり大きな出費だと思います。そのことに対する申し訳なさは、私の中にずっとあります。
学校に通っていれば、子どもたちは“無償で教育を受ける権利”が保障されていますよね。でも、不登校になった瞬間、「お金を払って学ばないといけない」っていうのは、不平等だなと思います。年齢が上がるにつれて、「自分が不登校になったから、迷惑をかけてるんや」と思ってしまう子もいます。
また、日野里山フリースクール側としても、「子どもが来てくれているから運営が成り立っている」という状態になると、その子が学校に戻ろうとする時、本当はすごく応援したいはずなのに、気持ちが割り切れなくなる…という矛盾も生まれてしまいます。
だからこそ、フリースクールの運営は、行政や公的な支援で支えてほしいと思っています。これまでも町長や教育長とも話をしてきました。もちろん少しずつ動いてくださってはいるんですが、もっと進めていきたいと思っています。今後も、5月や6月に町長などと話す機会があるので、引き続き働きかけを続けていく予定です。



資金面、苦しい課題ですね。



多分、全国のほとんどのフリースクールが経営状況私たちと変わらないと思います。
まとめ
「勉強だけが教育じゃない」。
そう実感できる日野里山フリースクールの日常は、子どもたちにとって、そして関わる大人にとっても、かけがえのない学びの場となっています。
ちなみに、日野町から保護者に向けて月に5,000円の補助が出ているほか、滋賀県からも同額の助成があるそうです。地域全体で、こうした学びを支える仕組みが少しずつ整ってきているのですね。
次回は、蕗ちゃんの生い立ちに迫ります。お楽しみに!
2025年4月の日野里山フリースクールの様子
現在、休眠預金の助成金を活用し、キッチン、食堂、トイレ、図書室、学習室、スタッフルームができました。