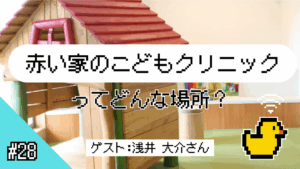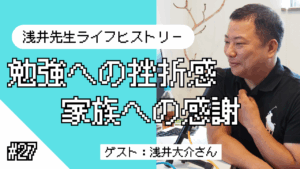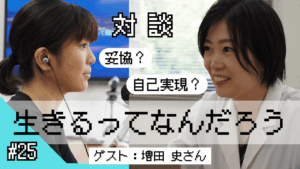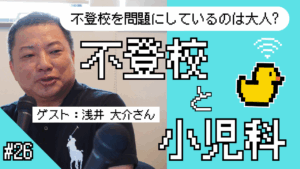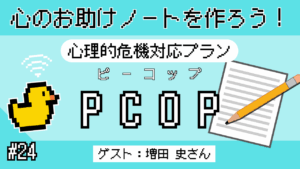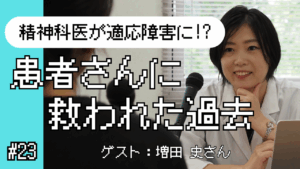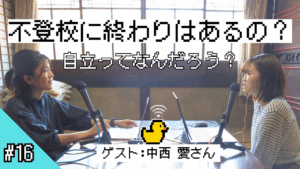本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第11回は、ゲストにフリースクールてだのふあの山下吉和さんをお迎えしています。今回は、登山ガイド資格を持つ山下さんならではの活動、「自然体験」を通して、子どもたちの世界が広がっていく様子をお聞きしていきます。
山下 吉和さん
NPO法人 てだのふあ 代表
1961年、長浜市生まれ。87年、滋賀県教員となり河瀬小など彦根市内の小学校に31年間勤務。「生活綴(つづり)方教育」に力を注いだ。県中央子ども家庭相談センター指導員を経て2020年にフリースクール「てだのふあ」を開校。登山ガイド資格も持つ。植物保全「伊吹山ネイチャーネットワーク」事務局長。
【NPO法人 フリースクールてだのふあ】
滋賀県彦根市のNPO法人「フリースクールてだのふあ」は、不登校の子どもらの居場所づくりに取り組まれています。 てだのふあは沖縄の方言で「太陽の子」の意味です。「しぜんな成長」を支援しようと、学習の時間やスタッフらによる絵画教室など様々な教室を用意し、登山や座禅体験などにも取り組んでこられました。 代表を務める山下吉和さんは元小学校教師。「子どもに寄り添った活動をしたい」と、2020年にてだのふぁを発足されました。向き合ってきたのは音に敏感な子や対人関係に傷ついた子……。「心身共に開放し、のびのびと過ごして」と願い、不登校の親にも寄り添ってこられました。
📌 てだのふあ公式Facebookページはこちら
 井ノ口
井ノ口「てだのふあ」では平日の活動に加えて月に2回、様々な自然に触れる企画「自然教室」をされているそうですね。



そうですね、月に2回ぐらい、四季折々の自然体験をしています。
たとえば夏でしたら、魚釣り、特に鮎釣りですね。ただ釣るだけじゃなくて、その場で腹わたを出して、塩焼きにして食べるところまでやるんです。命をいただくという体験ですね。あとは、やっぱり滋賀県といえば琵琶湖ですから、カヌーもやっています。琵琶湖に親しむという意味でも、カヌー体験はとても大切だと思っています。沖島まで行って、バス釣りをしたりもします。春や秋には、山登りやハイキングもやります。私は伊吹山で活動しているので、子どもたちを伊吹山にも連れて行って、夕日を見たり、星空を眺めたり。今は登山道が崩れてしまっているんですけど、以前は下から山頂まで登って、また降りてくるという本格的な登山にも挑戦していました。冬になると、スキー場でソリ遊びや雪遊びもします。
本当に、自然の中に身を置いて、海・山・川を舞台に、四季を感じながら、子どもたちと過ごしています。



事前に、山下さんが毎日Facebookで投稿されている「てだのふあ通信」を少しだけ拝見させていただきました。そこに載ってる 植物の写真が綺麗に撮られているのが印象的でした。登山も毎日のようにされているんですか?
てだのふあ通信については、以下の記事をご覧ください
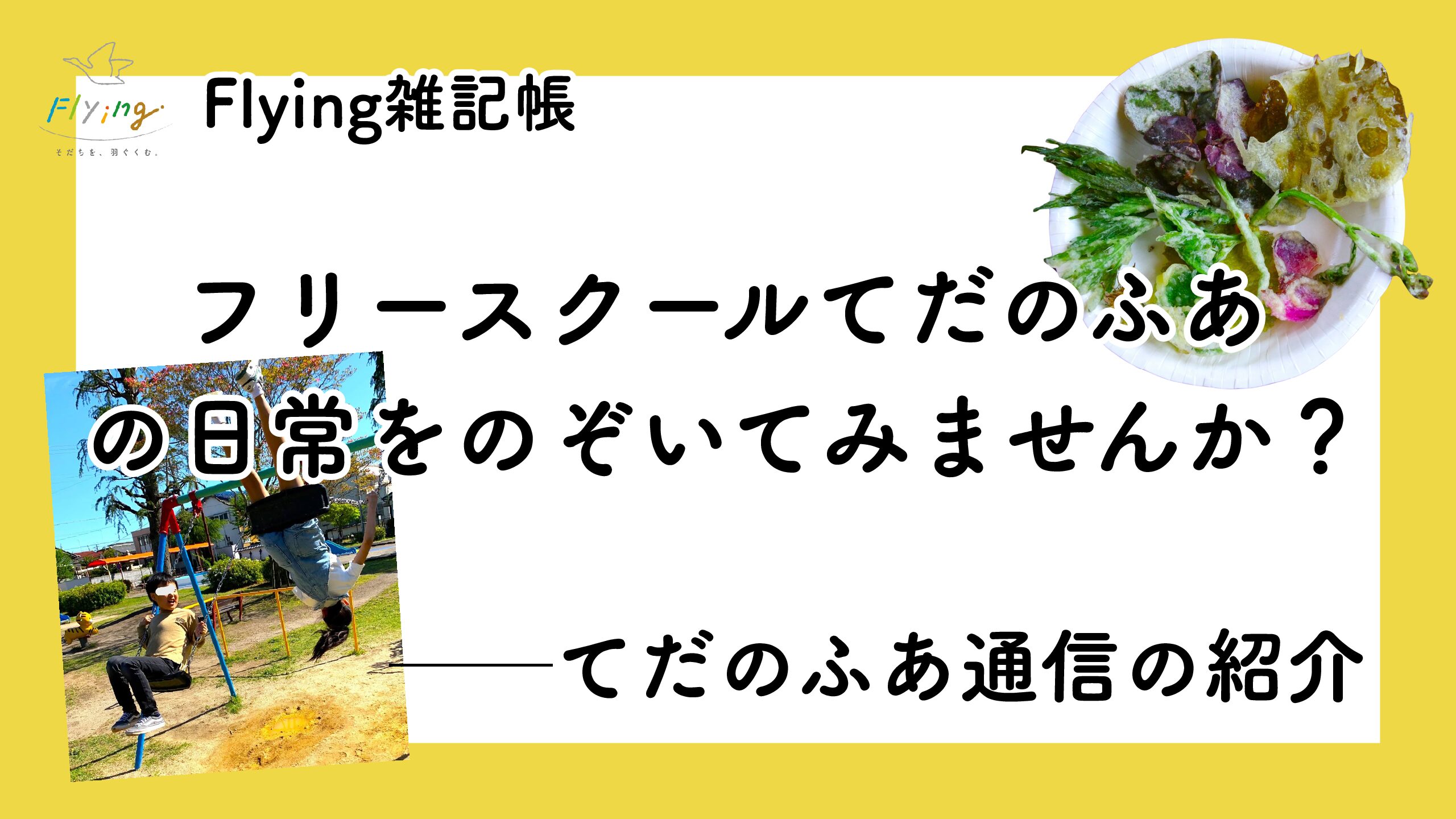
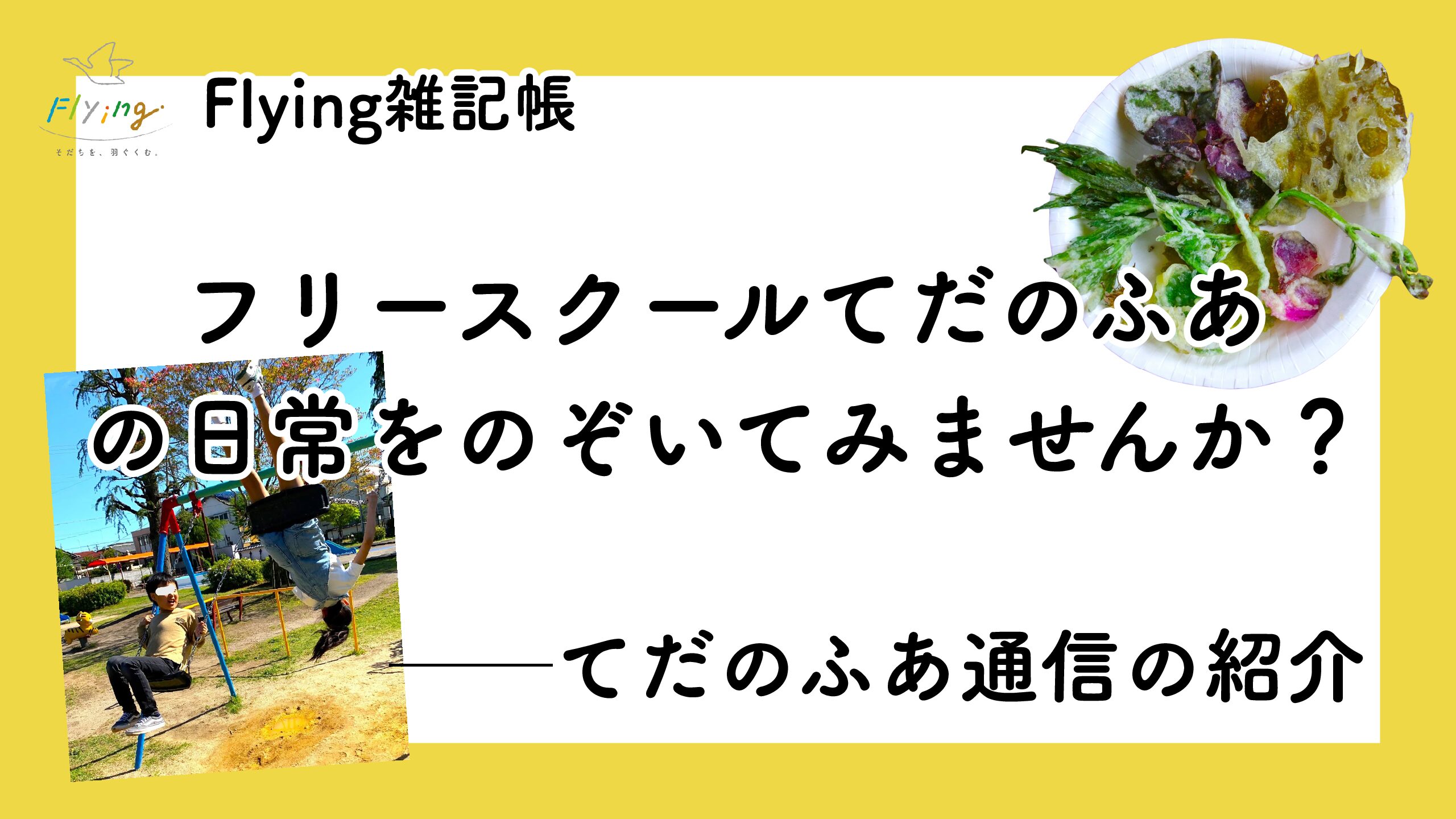



「毎日登山」と言いたいところですけど、さすがに毎日は無理で(笑)。でも、できたら本望ですね。もともと私は田舎育ちで、滋賀県の長浜市の湖北町というところの出身です。家の前には琵琶湖、裏には山があるような場所で、野原や琵琶湖で遊んだ記憶が、今でも自分の原風景として残っています。その頃の体験が、私のすべての土台になっていると感じています。
大学に進学してからは、ワンダーフォーゲル部、いわゆる登山クラブに出会って、本格的に山登りを始めました。でも、やっぱり根っこの部分にあるのは、幼少期や少年期に自然とどんなふうに関わったか、ということなんです。
五感を通して自然を感じる──たとえば、山の頂上で感じる風の音や匂い、そういう感覚が本当に大事だと思っています。そういう思いもあって、自然教室を開催するようになりました。



自然の中で子どもたちと一緒に遊ぶ中で、何か山下さんにとって印象的だったエピソードはありますか?



そうですね。まず「自然の中に身を置く」ということ自体が、とても大きな意味を持つんです。ある子どもは、「自然の中にいると会話をしなくてもいいから落ち着く」って言ってくれました。人間関係に疲れてしまった子にとって、そういう時間がすごく大事なんですよね。
ある子の話なんですが──その子は、小学5年生までは「暗黒の日々だった」と自分で言うような生活をしていて、家からほとんど出られなかったんです。でも6年生になって、てだのふあに来るようになって、自然教室で伊吹山の夕日を見る機会があったんです。その日は条件もすごく良くて、伊吹山ドライブウェイから山頂まで30分ほど登ると山頂からは、夕日が琵琶湖の対岸に沈んでいくのが見えたんですよ。
その子が次の日に書いた日記があるんです。ちょっと紹介してもいいですか?



はい、ぜひお願いします。



伊吹山の山頂に寝転び、思った。
雲一つない世界は、むっちゃ広いな。
考え方が寛容になった。
ちっぽけなことは気にせず、やりたいことをやろう。
頭のネジを頂上から捨てた。
自分は自分でいいんだ。
その子は当時、小学6年生の男の子でした。この「頭のネジ」って何?って聞いたら、「固まった考え方」って答えたんですよ。
今、この子は高校1年生になっていますけど、この伊吹山の体験は、彼にとって本当に大きな出来事だったようで。そこをきっかけに、少しずつ自分を解きほぐして、開放的になっていった気がします。



不思議ですね。そんなに長く引きこもっていた子が、夕日ひとつで変わるなんて……。



そうですね。もちろん、夕日ひとつで急に変わったわけではなくてね、その子は他にもたくさん自分の思いを綴っていたんです。彼はこんな風にも書いています。
今まで自分が歩んできた道は“決められた一本道”だった。
でも、てだのふあに来ていろんな活動をすることで、“選択肢がいくつもある道”に変わっていった。
5年間、すべてを引きこもっていたわけじゃなくて、特に5年生の時が厳しかったようです。でも、人との出会いや、自然との出会いによって、きっかけをつかむことがある。それは大人も子どもも、同じじゃないかと思います。彼にとって伊吹山の夕日は、それまで見たこともない世界で、心から感動した景色だったんでしょうね。



お話を聞いていて、学校に行って、帰りに塾に寄って、家に帰る……みたいな毎日だと、心が揺れるような景色との出会いそのものが減ってきているのかもしれないなって思いました。
だからこそ、たとえ当たり前に咲いている花とか、夕日がきれいなこととか、そういうことが本当に新鮮に映るのかもしれないですね。伊吹山、行ってみたいな。



やっぱり、伊吹山って面白いんですよ。伊吹山の話をし出すと、また長くなるんですけど……やっぱり面白い山です。
高々1,377メートルの、そんなに高くない山なんですけど、本当に条件がいいんですね。大陸からの風が吹きつける場所にあって、通り道にもなっていて。それに、寒冷な冬には雪もよく積もる。そういったいろんな条件が重なって、伊吹山には高山性の植物が本当にたくさん咲いています。山の中に入れば、まるでアルプスを思わせるような景観が広がっている。木がなくて、低い木しかなくて、草原状になっていて。これは石灰岩の土壌であることが大きいんですけど──。
本当に、僕は伊吹山にすごく魅力を感じていて。こんなに素晴らしい宝物が、こんなに身近なところにあるんだから、ぜひ子どもたちにも足を運んでほしいと思ってます。



ふと思い出したんですけど、小学校のとき、私、集団登校をしてました。すっごく車が多い地域だったんですよ。だから、毎日「分団登校」で、みんなで集まって、2列に並んで、班長さんを先頭にして通学するっていうスタイルで、6年間ずっと通ってました。
事故に遭わないように、とにかくまっすぐ前の人について歩くことを教えられました。もちろん、それも大事なことだとは思うんです。
でも一方で、「これ、あの草だ」とか、「あ、花が咲いてる」とか、そういうふうに、ある意味「注意散漫に歩く」っていう体験も、あんまりないのかなって。



昔は当たり前に、世の中にあった自然ですね。草や花が道端に咲いていたりっていうのが、今はなかなか、意識しないと見えない。
やっぱり「意識化」していくっていうのは、自然教室においても、大事にしたいことの一つかなって思います。



最後に、てだのふあ普段の1日の流れを少しお聞きしていこうかなと思います。



普段、朝はだいたい9時ぐらいから始まります。9時半から10時までは送迎タイムって呼んでいます。スクールが始まるのは10時からなんですが、9時半から早く起きて来る子もいます。
で、10時15分から「てだのふあ会議」っていうのをやっています。略して、「てだ会議」って呼んでる会議なんですけど、連絡事項だったり、子どもたちの体調のことだったり、話し合うことがあればその話し合いをしたりします。
午前中は「ミータイム」って呼んでる、自分だけの時間を過ごす時間が2コマあるんです。これは人と一緒に何かをする時間じゃなくて、自分の中でやりたい課題に取り組む時間なんですね。入って間もない子たちは、まだなかなかやりたいことが見つからなかったりするので、タブレットで何かをやったり、漫画を読んだりして過ごしています。もちろんそれもOKです。とにかく「自分で何かを進めていく」っていう時間なんです。なかなかやりたいことが見つからない子は、スタッフがサポートしながら、一緒に何かを作り出していく、そんな感じですね。
それで、お昼ご飯を食べて、午後1時からは、また「てだ会議」をやります。午後から参加する子もいるので、改めて連絡事項を確認したり、大事なことがあれば子どもたちと話し合ったりします。たとえば、「バドミントンのラケットが欲しい」っていう話が出てきたら、子どもたちと「ほんまにいらん?」みたいな感じで、話し合ったり、あとはイベントがあるときは、その準備や打ち合わせもします。
午後は「体験教室」が入ってくることもあります。ありがたいことに、元教員の仲間や山仲間がたくさんいてくれて、いろんな教室が開けるんですね。たとえば、面白実験教室とか、料理教室、木工教室、アイロンビーズ、あと華道・茶道なんかもそうですね。子どもたちは参加してもしなくてもOK。自分で決められます。なにもない日は、「フリータイム」として、思いっきり集団遊びを楽しんだりもしています。
帰りの送迎タイムは、15時から15時半までになっていて、最大で15時半ごろまで子どもたちはいます。
月曜日と金曜日は、16時から「マナビー」っていう学習支援の時間があって、これは休眠預金活用事業の助成を受けて行っています。ここに来る子どもたちは、当然、学校=勉強っていうところにすごい抵抗を持ってるんです。だから、学校みたいな勉強から出発するわけじゃないんですよ。でも、元気になってくると、「進学したい」とか「目標ができた」とかで、勉強にスイッチが入る子も出てくるんですね。そういう子たちのために、「学びのきっかけづくり」として、1時間ほどやっているんです。
だいたい常時5人ぐらいの子が参加していますかね。
それと、火曜日と木曜日は、教育相談事業もやっていて、これも休眠預金活用事業の助成を受けています。これは保護者の方向けの相談事業で、16時半から18時まで行っています。
あとは、空いている時間に何をしているかというと、スタッフ会議をしています。その日の子どもたちの様子を出し合って、子ども理解を深めるための時間ですね。なので、ほんとにあっという間に1日が過ぎていきます。



すごい忙しそうですね!自分たちで決めることも多いとのことですが、子どもたちの中で仲間割れはしないのでしょうか?



物事を決める時は、民主的な手続きを踏むようにしています。たとえば、20人の集団やと、意見の強い人に流されてしまうことってあるじゃないですか。そこで、小学生会議をする時もあるし、中学生会議をする時もありますね。そういった「手続きを踏む」と、子どもらの意見に違いがあっても、そこで対立して喧嘩になるとか、後腐れが悪くなるとか、そういったことはないかなと思っています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
自然教室を通して、子どもたちの世界観がまた一つ広がっていく様子が、少し想像できたかなと思います。次回は、山下さんが学校の先生として働いていらっしゃったご経験について、もう少し深めていきます。