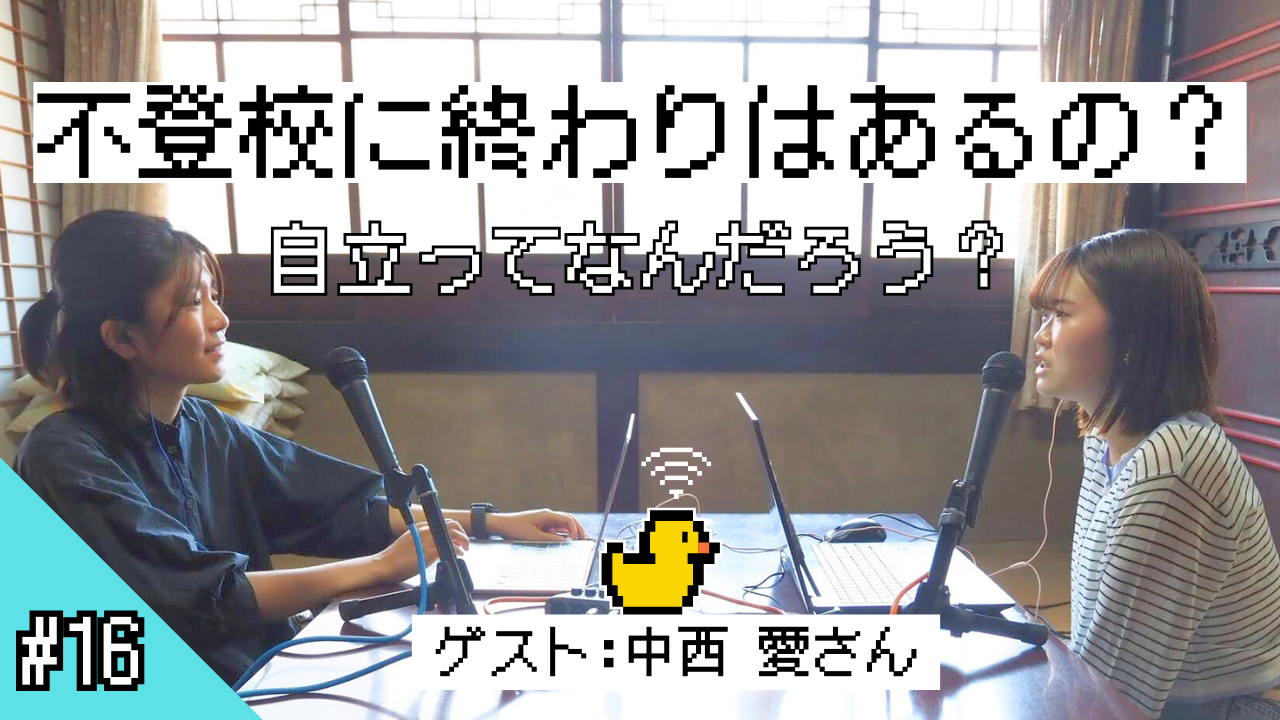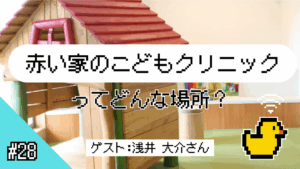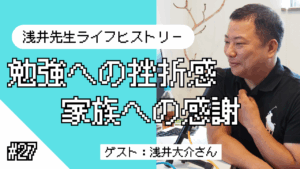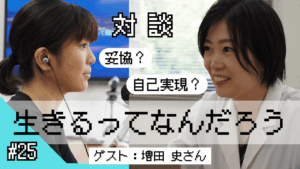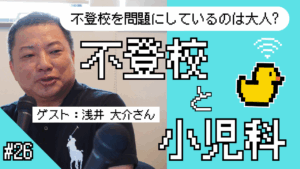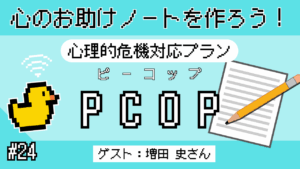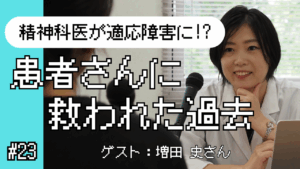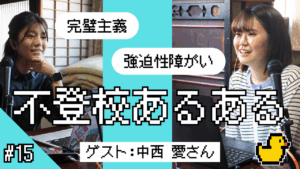本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第14回は、ゲストに滋賀県野洲市で活動する、心の居場所~toiro~の中西愛さんをお迎えしています。今回は、愛さん自身が経験した不登校について、お聞きしていきます。
中西 愛さん
学校でのトラウマ的経験や、音や匂いに敏感で、にぎやかな場所や集団行動が苦手な自身の特徴によって、小学校1年生から学校に通いづらくなる。その後、強迫性障がいなどと向き合いながら、約10年間の不登校を経験。現在は自身の不登校経験にもとづき滋賀県野洲市で心の居場所〜toiro〜を運営。
📌インスタグラムはこちら
📌noteはこちら
~心の居場所~toiro
頑張らなくてもいい、ただただ心の元気を取り戻すための場所]、でも、元気が出てきたら程よい距離感で背中を押してくれる人がいる。という愛さん自身が必要としていた場所を形にした居場所。時間はかかるかもしれないけれど、一歩ずつでも、いま困っている子たちのために伝えていければいいな、という思いで、月に1~2回開催している。いつかは、不登校の子どもも親御さんも、周りにいる人たちも支援者も、み〜んなの心が楽になる世の中になるように、アプローチができたらいいなと考えている。
不登校という言葉について
 井ノ口
井ノ口カモラジオでは「滋賀県の不登校について」ってオープニングで言ってるんですが、実はこれまでのゲスト3人の方が、みんな無意識に「不登校」という言葉を避けているように感じるんです。
例えば、いつかさんは「学校に行きづらさを感じる子ども」と呼ばれていました。そこで愛ちゃんに聞きたいんですが、「不登校」って呼ばれることについてどう感じていますか?



はい、私の場合は、不登校って言われても特に違和感を感じないですね。
私自身も抵抗なく「不登校」という言葉を使っています。今の私にとっては、もう「不登校」という言葉は必要不可欠なんです。これがないと私じゃない、みたいな感じで、便利な言葉としても使っています。
やっぱり、学校に行けなかった過去は私の人生の中で本当に大きな出来事なので、その過去があるからこそ今の自分がいると思っています。だから、逆にそこで不登校を否定されたら、私自身を否定された気持ちになってしまうんです。だからこそ、あえて使っていますね。
もう「不登校はダメ」って言わないためにも、学校に行かないことをダメって言わないためにも「不登校」って使っています。当事者からすれば、もうそれは事実なんですよ。「学校に行ってない」っていう事実だし、それよりももっと大事なことがあるので、そこに目を向けてほしいなっていう気持ちでいます。



なるほど



「不登校」という言葉は、大人にとってやはり分かりやすいですよね。私が「不登校だったんだ」と言うと、「ああ、なるほど」とすぐに理解してもらえる。だから、理解してもらおうと思えば思うほど、その言葉を入口として使わないと、私にはちょっと難しいんです。そんなに言葉を上手に使えるわけではないので、あえて「不登校」という言葉を使うようにしています。
それに、今toiroに来ている子どもたちも、「不登校」という言葉を使って普通に話していますよ。「愛ちゃんって不登校やったんよな〜?」とか!



子どもたちも、自分で自分のことを不登校というのは、意外でした。



そうですね、当事者からすると、そこまで深くは考えていないのかなという気はします。ただ、やはり親御さんや支援者の方からすると、そう思われがちなのかな、というのはありますよね。
でも実際、私としては、もう「不登校の子」って見てもらった方が、逆に力になるんです。もう、人生の中で過去があるのは当たり前というか、消えないものだから。そこをいかに上手に、うまく付き合っていくか。そして、それを活かして生きていくか、ということが大切だと思って生きています。



うん、なるほど。そうか。でも、「不登校」って、やっぱり学校に行くことを前提に作られた言葉だなっていうのは思いますよね。



そうなんですよね。でも、私たちが生きている間に「学校に行くのが当たり前」という前提を変えるのは、たぶんまだまだ難しいことだと思うんです。
だから、今生きている自分を、今の社会の中でどう成り立たせようかと考えると、やっぱりそういう言い方しか今のところ本当にないのかなって思っています。
何かを大きく変えようとするよりも、今を地道に生きている方が楽な気もするんですよね。たぶん、しんどいことしなくていいから。



ちょっと、不登校という言葉を使うのが楽になりました。 ありがとうございます。
学校の競争って、良いこと?悪いこと?



はい、では次のテーマに移ります。
これは、前回のゲストである山下さんから、私が個人的に受け取った宿題のようなものなんです。山下さんは先生をされている中で、「成績をつけなければいけない」ということに葛藤を感じていたとおっしゃっていました。特に道徳のような、その子自身の本質的な部分にまで成績をつけなければいけない、というのがすごく葛藤だったと。
そのラジオを何回か聞く中で、「学校における競争、というか優劣をつけることって、どれくらい重要なんだろう?」ということを愛ちゃんと話してみたいなと思っています。
愛ちゃんは、そういった成績や優劣で苦しんだ経験はありますか?



確かに、私自身が学校に行ってないから、みんなより成績もそんなに良くないだろうし、学校って「選ばれる」っていうのがすごくあるじゃないですか。運動能力が高い子が大会に出るとか。私、それこそ学校に行ってないから、そういうのに選ばれないのかな、みたいなこともありました。
この話を聞いた時に、どう言ったらいいだろうって思ったんですけど、私的には、別に競争が絶対的に悪いことだとは思わないんです。オリンピックだってあるし、そういうところに関してはいいと思うんですよ。自分が理解して、納得した上でそういう場に出ているならいいと思うし、何かに向かって頑張ってる過程もすごく大事なことだと思うから。
でも、学校っていう、みんなが「入れられた場所」で、自分が納得もしてないのに競争させられるのは、ちょっと嫌かなって。そう、自分はそんなに争うつもりないのに、っていうのはありますね。
あと、最近ちょっと支援とか、そういう立場に回った時に思うのは、その人が頑張っている基準をみんな一緒にしてはいけないなって思っていて。頑張ってることの基準って人それぞれだから、何かができることが頑張ってることの基準にもならないし、それまでの過程だったり、その人の頑張りの量を見てほしいなっていうのは、やっぱり思います。学校って、それがすごく少ないんですよね。



めっちゃ遡るけど、人間が狩猟採集民族だった頃からある本能というか、動物を捕まえなきゃいけないからやっぱり早く走らなきゃいけない、みたいな。そう、なんか競争する力みたいなのは大事というか、もう最初からあるっていうのはありますよね。
そうだと思うんだけど、でもだからと言って、それが全てではないっていうのはすごく思う。あのスマブラって分かります?私、スマブラがめっちゃ下手で。
すぐ負けるし、昔は、「自分ってこんなに弱いんだな」って悩んでたんですよ。でもある日ふと、「ちゃうな」って気づいて「そもそも、自分、戦いたくないな」って。
スマブラの世界ではもう戦うことを前提にゲームが始まるから、うん、勝つか負けるかの思考になっちゃうんだけど、いや、「違うな」みたいな。「スマブラ、別にしたくないな」みたいな。 そういう何か、前提として、戦わなくていい土壌があるといいなと思いました。



そうですね。人と比べる競争が多いから、そうじゃなくて、その人、その一人ひとりの頑張りをどれだけ見てあげられるかがやっぱり大事だなって思うんです。
だから、学校ってやっぱり「みんな一緒」を求められたり、「みんなで仲良くしなさい」とか、同じであることが良いみたいな。競争ってそういうことだと思うんですよ、逆に言ったら。「みんな同じで、みんな同じところに向かって目標があって、向かいなさい」みたいな。
いや、そうじゃなくって、一人ひとりが目標に向かって自分との戦いでいいと思うんです。だから、小学校でそういう同じことに向かって「よーいドン」で戦わなきゃいけないっていうのは、ちょっとしんどいなっていうところは私もやっぱりありますね。
不登校に終わりはあるの?



はい、では最後のテーマに移りましょう。これは「不登校に終わりはあるのか」というテーマです。



まず、当たり前のことかもしれませんが、不登校には終わりが来ます。義務教育を終えれば、学校に行かないという選択肢以外にも、たくさんの道が開けますから、自然と「不登校」という人ではなくなります。
ただ、その子が抱えている「しんどさ」には、終わりが来るのが難しいですね。心の傷というのは、なかなか消えるものではありませんから。私自身も学校から離れて、今は「不登校」という立場ではなくなりましたが、まだまだ回復途中ですし、しんどいこともたくさんあります。だから、いろんな人に助けてもらいながら生活しています。
学校という場所は、勉強を含めて社会で生きていくための術を学ぶ場所だと私は思っています。だからこそ、子どもが学校に行けなくなると、親御さんは「この子の将来はどうなるんだろう」って不安になりますよね。そこで私がすごく考えるのが「自立」についてです。
「自立」って「自分の足で立つ」と書くじゃないですか。その意味で認識されていますけど、私はこれに違和感を抱いています。なぜかというと、人間は一人では生きていません。誰とも関わらずに生きている人なんていませんし、人と人とが助け合って生きているんです。いろんな人との関わりがあるからこそ、生きていけるんだと私は思います。
だから、本当の意味で自分の足だけで立てている人なんて絶対いません。人間にとって本当に大事なことって、「人に助けて」と言える力だと思うんです。特に不登校や生きづらさを抱えている子どもたちこそ、誰かに頼れる、助けてと言える力が本当の意味での自立だと私は考えています。
これって、決して特別なことじゃなくて、学校に行っている人も、仕事をしている人も、みんなそうやって生きているんです。
居場所を運営できているのも、いろんな人に助けてもらっているからこそですし、私のプライベートの生活を見ても、本当にいろんな人に助けてもらっています。
自分の足だけで立とうとするんじゃなくて、いろんな人に「助けて」と言いながら人に頼れる力って、すごく良いことだと思うんです。本当にすごいことだし、そうやって頼られて嫌な人ってそんなにいないですよね。だって自分も頼っているわけですから。そうやって人と人とが助け合って生きていけばいいんじゃないかなって思うからこそ、不登校の子が特に「助けて」と言えた時には、めちゃくちゃ褒めるし、「言えたね」って伝えています。
不登校って、そうやって本当に終わりが来ないように見えるかもしれませんが、そうじゃなくって、いかにそれをうまく使って、人に「助けて」と言えるか。それが大事かなと思っています。



本当にそうですね。よかった。なんか、カンニングってあるじゃないですか? 人の答えを見ちゃいけないっていうルール。私、カンニングができる社会だったらいいのになって思うんです。(笑)
「私、分からないから、教えてくれない?」 ってみんなが答えを共有できたらいいのに〜って。
確かに、自分で問題を解く力っていうのもすごく大切だとは思うんです。
でも、本当に分からなくても、みんなで助け合って、それで「これでいいや」って気づけたら合格、でもいいじゃんって。



そうなんですよね。だからこそ、「助けて」と言える人が、まず行動を起こして、周りに働きかけるような、そんな社会にしていければ良いなと思います。難しいことではありますけどね。
でも、本当にこの世の中には、「助けて」と言ったら助けてくれる人がたくさんいます。たぶん、もし一人、助けてもらえなかった人がいたとしたら、その一人が自分の中で大きく感じてしまうんですよね。「この人に助けてもらえなかったから、みんな助けてくれないだろう」って思いがちですけど、そうじゃなくて。
例えば、いろんな人に言ってみれば、もしかしたら10人中9人は助けてくれるかもしれないんです。大多数の人が助けてくれるってことは大いにあり得るんですよね。私もやっぱりそうでした。一人ひとりの人間関係で「ダメだ」ってなったこともあったけど、他の人を見てみれば、すごく温かい人も多いし、助けてくれる人がいっぱいいるんだって。この社会も捨てたもんじゃないな、って思ったりします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回も本当にたくさんの気づきをありがとうございました。「1人で生きていくことはできない」——当たり前のことだけど、忘れてしまいがちです。自立しなきゃと焦っていた自分に、少し立ち止まる余裕をくれた時間でした。
次回は、愛さんが運営されている「心の居場所~toiro~」について、さらに詳しくお話を伺います。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。それではまた来週、お会いしましょう。