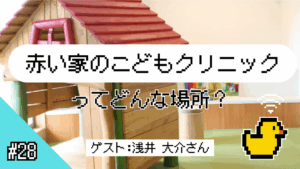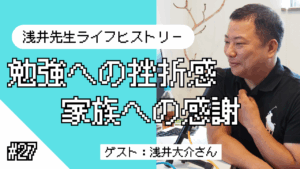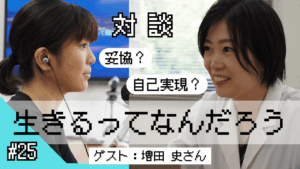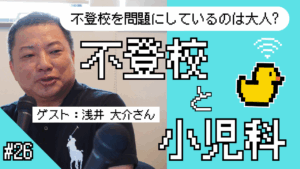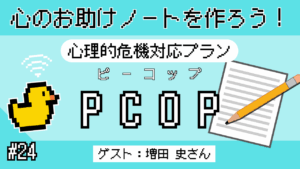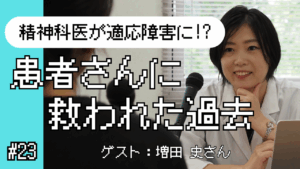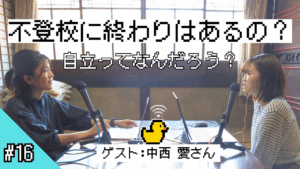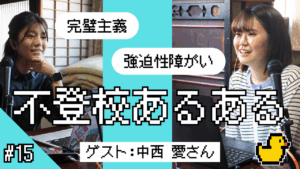本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第17回は、ゲストに滋賀県野洲市で活動する、心の居場所~toiro~の中西愛さんをお迎えしています。今回は、愛さんが運営されている心の居場所~toiro~についてお聞きしていきます。
中西 愛さん
学校でのトラウマ的経験や、音や匂いに敏感で、にぎやかな場所や集団行動が苦手な自身の特徴によって、小学校1年生から学校に通いづらくなる。その後、強迫性障がいなどと向き合いながら、約10年間の不登校を経験。現在は自身の不登校経験にもとづき滋賀県野洲市で心の居場所〜toiro〜を運営。
📌インスタグラムはこちら
📌noteはこちら
~心の居場所~toiro
頑張らなくてもいい、ただただ心の元気を取り戻すための場所、でも、元気が出てきたら程よい距離感で背中を押してくれる人がいる。という愛さん自身が必要としていた場所を形にした居場所。時間はかかるかもしれないけれど、一歩ずつでも、いま困っている子たちのために伝えていければいいな、という思いで、月に1~2回開催している。いつかは、不登校の子どもも親御さんも、周りにいる人たちも支援者も、み〜んなの心が楽になる世の中になるように、アプローチができたらいいなと考えている。
 井ノ口
井ノ口今、実はこのインタビューも、toiroの活動場所「豆吉」さんで収録させてもらっているんですが、和室で、すごくほっこりする空間ですね。



そうなんです。ほんとにリラックスできて、自分の家のように過ごせる場所です。
目指すのは、「学校復帰」ではなく、「心の元気を取り戻す」こと



学校とは違う雰囲気で、安心感がありますね。あらためてお聞きしたいのですが、toiroはどんな目的で運営されているんですか?



「学校に戻ること」を目指すんじゃなくて、「心の元気を取り戻す」ことを目的にしています。不登校の子も、学校に行き渋ってる子も、来てねって伝えています。何らかの理由で心が傷ついて、不安でいっぱいになってる子どもたちって、本当に疲れてるんです。だから、「不安を安心に変える場所」でありたいと思っていて。ここは、心を休ませる場所なんです。



愛ちゃん自身も、「安心がなくなると、”まぁいっか”ができなくなる」ってさっき言ってたけど、そういう愛ちゃんの実体験から来てるんだろうなって感じます。



そうですね。私自身も中学生のとき不登校で、居場所が見つからなくて、本当に困っていました。スマホで探して親に「ここに電話して」って頼んでも、「学校からじゃないと受け付けられません」と言われて断られたりして…。
そのとき、私が関わっていた先生や親、カウンセラーの先生たちが、「あの頃から愛ちゃんは、自分でそういう場所を作りたいって言ってたよ」って教えてくれたんです。私は覚えてないんですけど(笑)
大学生になって、また学校に行けなくなって、「あ、今やれるかもしれない」と思って始めたのがtoiroです。自分のためでもあり、同じように困っている誰かのためでもある居場所です。
私が感じていたのは、支援する人が元先生だったり、親だったりすると、どうしても「大人目線」になりがちなんですよね。それが悪いわけじゃないけど、「当事者目線」で寄り添える人が少ないなと感じていて。だからtoiroでは、当事者としての自分の経験をもとに、できるだけ近い立場で寄り添うことを大切にしています。
「自分が欲しかった居場所」をそのまま形にしたのが「toiro」なんです。



ある意味、「toiro」を作ることって、自分のためでもあったんですね。



そうですそうです! 自分が働く場所も、ないんちゃうかなって思ってたときに、ちょっと「練習」みたいな感じで始めたっていうのもあるし。自分にとっての居場所でもあるし、子どもたちや親御さんにとってもプラスになるなら、それは素敵やなって思って作りました。
toiroの活動内容:愛ちゃんの子どもの向き合い方



toiroには、今どのくらいの子が通ってるんですか?



今はだいたい4人くらいですね。来たり休んだり、その子のペースで参加しています。ほんとに小人数でのびのびやってますよ。
活動は月に2~3回。間が空きすぎないように調整しながら開催しています。



子どもたちは、どんなふうに過ごしているんですか?



ほんと自由です(笑)。来てすぐゲームを始める子もいれば、「話そう」って一緒に話す子もいたり。お菓子作りしたり、たこ焼き作ったり、公園に行ったり、コンビニにお散歩行ったりもします。
大事にしてるのは、無理強いせずに、その子が「楽しい」と思えることを、安心してできるようにすることですね。



子どもたちと関わる中で、印象的なことってありますか?



うん、なんか……めっちゃあります。
お子さんがふと口にする言葉が、すごくピュアで、きれいなんですよ。なんていうか、私でも言い切れへんことを、ぽろって言うんです。
たとえば、「マジカルバナナ」ってあるじゃないですか。
マジカルバナナで「人の名前」となったときに、私が「人の名前といえば愛ちゃん」って言ったら、次の子が「愛ちゃんといえば、友だち!」って言ってくれたんですよ。もう、めっちゃかわいいと思って。「ありがとう」って言って。
そういう素敵な感覚というか、そういうのが私にとっても学びになるし、私もすごく得るものがあります。この居場所で、朝ちょっと疲れてても、子どもらが「おはよう」っていう声だけでも、すごい元気になります。
私が何か提供してる、パワーを出してる、っていう面もあるかもしれへんけど、もらってるパワーのほうがやっぱ大きくて。そこはほんまに、子どもたちにも、お母さん方にも、「ありがとう」って思ってます。



そうか。愛ちゃんにとっては「子どもたちを支援している」っていう感覚よりも、愛ちゃん自身がそこで元気をもらってるっていうところが大きいんですね。



はい。その面もありつつ、やっぱり、「支援」っていうか、「手を差し伸べなあかん面」はバランスを見て、要点を押さえているところもあります。



torioの紹介文のところにも書いたんですけど、「がんばらなくてもいい。ただただ心の元気を取り戻すための場所」でも、「元気が出てきたら、ほどよい距離感で背中を押してくれる人がいる」という言葉が印象的でした。
もちろん、「好きに過ごして安心する場所」っていうのは大前提としてあるけど、子どもたちにとって「ここは応援してほしい」っていうタイミングもきっとあって。
そのときに、愛ちゃんの大事にしてること――支援というか、あり方というか――が、すごく詰まってるんやろうなと思います。



うーん、なんて言ったらいいんやろな。
不登校とかって、やっぱり一回しんどくなっちゃってるから、できなくなってることが出てくるんですよね。不安が強いがゆえに、今までできてたことが、ちょっとできなくなる。それ、私自身にもあったんですよ。
そういうときに、「できるようになることを目指す」っていうのももちろん大事やけど、そうじゃなくて、一回止めて、その子が“安心でいっぱいになる”まで、もう満足するまで待つ。
そこから、「もう一回挑戦してみたい」ってなったときに、「じゃあどうやったらできるかな?」って一緒に考える。その手助けはするけど、やってあげる支援じゃなくてね。その可能性は無限大やから、そこは潰したくない。ほんまにちょっと手助けするぐらいでいいと思うんです。
私、安心になるまでは、結構手助けをします。おもちゃをそのままポイってしてても、私が片付けたりとか。それでいいと思ってて。子どもって、「やってもらった満足感」っていうのが、あとになってパワーになるんですよね。
でもそのうち、「あ、片付けてなかったな」って自分で気づいたりする。
そうやって、自分でできる力が湧いてくる時を待つ。「待つ」っていうのも、大事かもしれないです。
それに、toiroって“保護者支援”も大切にしています。親御さんにとっても「一緒に待てる存在」でありたい、って思いがあって。「いつまで待ったらこの子元気になるの?」って、すごいあるじゃないですか、



子どもが大切ゆえに、ね。



そう、ゆえにね。
「行くって言ったのに、行かへん」っていうことが続いたりして、なんかモヤモヤした時期を、親御さんがひとりで抱えないように、「一緒に」って。
子どもたちが芽を出してくるのを、見守ってるというか。ゲームをずっとしててもいいし、忘れ物しててもいいし、「靴下履かせて〜」って言われたら、履かせてあげます。(笑)
でも、やってもらった経験って、やっぱり“満足”につながる。満足したら、子どもたちは自然と離れていく。逆に、離れていかへんっていうのは、まだ満足してないってことやと思うんです。だから、そういう意味での“手助け”は、ちょっとだけしてます。
ゲームはあり?なし?



ゲームについても聞きたいです。フリースクールによってはゲーム禁止の場所もありますが、toiroではゲームOKなんですよね?



はい、OKです。私も一緒にやります(笑)ゲームって悪いものじゃないと思ってます。
私自身、ゲームすらできないほどしんどかった時期もあって、起き上がる力もなかった。だからこそ、「やりたいことがある」っていうのは、それだけですごいことやなって思ってます。
「ゲームはダメ!」って頭ごなしに言うのは、やっぱ違うと思ってて。一緒にやるし、「教えてな〜」って声かけて、一緒に楽しみます。
……ただ、ついていけないときもあります、最近のゲームは(笑)
器用やな〜って思うんですよ、ほんまに。だから逆に、賢いんです。例えば、ゲームの中で自然と漢字を読むようになるんですよ。勉強よりも、ゲームで漢字を覚えたっていう子が多くて、「それでええやん」って私は思ってるんです。
でも、ゲームから離れられない背景には、不安や葛藤から逃げているという面もあるので、大人がちゃんと理解しようとする姿勢が大事やなと思います。満足するまで待ってあげること。それができると、自然とゲームから離れられるようになったりもします。
“大丈夫”を伝えていくこと



最後の質問です。
不登校の子のそばにいる大人たちに、伝えたいことはありますか?



私は、いろんな大人に傷つけられたこともあったし、でも逆に、大人に助けられたこともあったんです。
でも、その助けてくれた大人たちって、別に「すごいこと」をしてくれたわけじゃなかったんですよね。何かって言ったら、「大丈夫」って言ってくれた。それも、ただ言葉だけじゃなくて。「大丈夫」っていう気持ちを、抱きしめてくれたり、私が泣いてたら背中をさすってくれたり、そういう、ほんまに身近にあるような愛情で伝えてくれてたんです。それがあると、安心感ってどんどん増えていくんですよね。
だから、そういう「身近にできる愛情の表現」って、実は子どもたちにとってめちゃくちゃ大事なことやと思うんです。私の周りにいた人たちって、ほんまにそれを自然にやってくれてたんですよ。
私に会ったら「ギュッとしよう〜!」っていう感じの、そんな何気ないことでいいと思うんです。本当にその子に向き合って、「大丈夫だよ」って伝えてあげる。それって、言葉だけじゃなくて伝わるものやと思うし。
私はそれが、ほんまに嬉しかったし、すごく安心したんですよね。
私の大好きな先生って何人かいるんですけど、みんな共通して「ギュッ」てしてくれるんです。みんな、ハグしてくれる。それって、スキンシップが苦手な子もいるから無理にする必要はないけど、できる子には、満たされるまでしてあげたらいいと思うんです。
私はほんまに、toiroの子でも「ギュッ」てしてます(笑)。男の子は嫌がるけど、女の子はギュッとしてくれるから、めっちゃしてますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?第17回でも、「子どもたちが一歩踏み出すのを待つ」という言葉が出てきましたが、
やっぱり対話においても、それは同じなんだなと実感しました。
自分が話すこと以上に、相手が話し出すのを“待つ”というのは、簡単なようで、すごく難しいことだなと思っています。これからもっと、“待つ”ということを意識して、大切にしていけたらなと思います。
さて、来週からは、なんと栗東市の教育委員会の方々にご登場いただきます。これまでは、4・5・6・7月と、学校以外で不登校に向き合っておられる方々へのインタビューを続けてきましたが、ついに今回は、「学校現場」で行われている取り組みにスポットを当てていきます。
学校で、どんなふうに不登校の子どもたちに向き合っているのか。新しい視点でのお話を、どうぞ楽しみにしていてください。