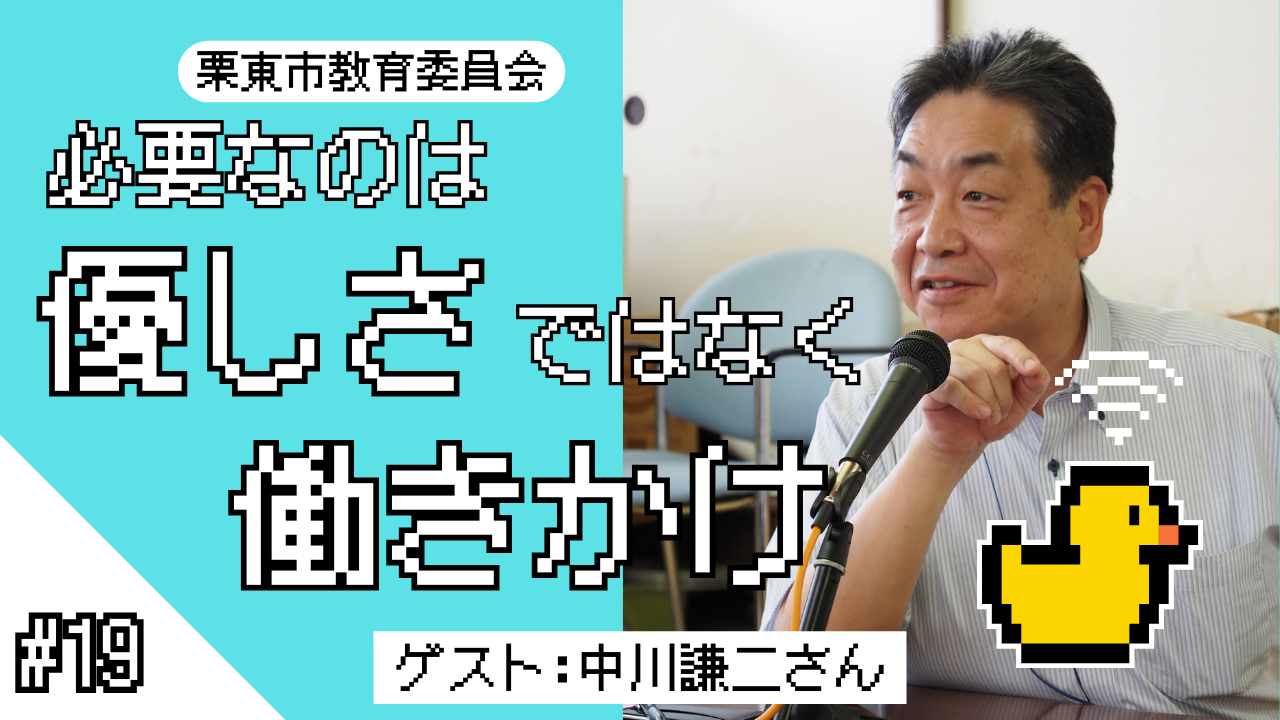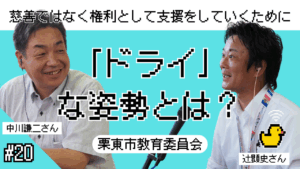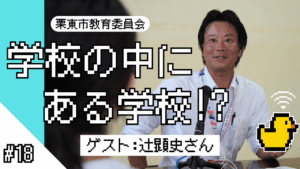本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第19回は、ゲストに栗東市教育委員会の中川謙二さんをお迎えしています。今回は、中川先生が教員時代に皆さんで作られた「ハーバールーム」(校内教育支援センター)という教室のことをメインに、中川先生の不登校の子どもたちへの考えをお聞きしていきます。
ハーバールームについて
(1)なぜハーバールームが必要なのか?
子どもたちは、学校で教科の学習や学級活動、行事、あるいは部活など通して、様々なことを学び、成長して いきます。 そして、学校が用意したカリキュラムだけではなく、学校に集まった多くの人との交わりを通して、人格を鍛え、社会の一員として活躍するすべを身につけていきます。 確かに人と共に何かを成し遂げること、人と共感し合うこと、それは”ひとり”では 味わうことのできない大きな感動とよろこびを与えてくれます。
しかし、未熟で思春期にある子ども同士のふれあいは、時には、繊細な心を傷つけることや、かけがえのない個性を排除すること、そして苛酷な努力や変化を教師以上に期待することもあります。一旦傷ついてしまった子どもたちは、まさに荒波の中を航海し続ける一般の船のようです。帆がおれても、船体に穴があいても、航海し続けるしかありません。本校では、そんな子どもたちのために、港(ハーバー:harbor )を用意しました。そこは“ドック”のように大々的な修理をする場所ではありません。しばし、荒波から逃れ、新たな航海に向けて、本来の力を回復させ、新たな航海に向け て態勢を整えるためのささやかな入り江…それがこの「ハーバー・ルーム」なのです。
私たちは、これまでのハーバールームでの働きかけを通じて、子どもたちは、
1.プレッシャーや集団から解放されるだけで、本来の明るさを取り戻すこと、
2.最終的には孤独ではなく、適度な人とのふれあいを求めること、
3.適切な教師の働きかけやルームメイトとのふれあいによって、コミュニケーション能力を高めること、
に気づきました。
(2)ハーバールームの使命と活動
ハーバールームの使命(目的)は、教育活動の一環として、個々の生徒の特性に応じた支援を行い、将来的な自立に向けて力を高めることです。そのために、ハーバールームでは、以下の取り組みを進めます。
1.登校から下校まで、一人ひとりの学校生活を見守ります。
2.個別の学習や活動の場を保障しつつ、ルームメイトのふれあいの機会を設けます。
3.生徒支援部が必要な支援や課題を考え、日々の運営はサボート支援員が行います。
4.全教職員が、利用生徒の教科指導(一日2時間)を分担して受け持ちます。
5.利用生徒と担任の絆をサポートします。
6.利用生徒へのカウンセリングやSSTをSCが行います。
7.いじめや暴力被害にあった子どもの安心安全を守ります
※『栗東市立栗東中学校 校内支援教室「ハーバールーム」 利用のしおり』より抜粋
“生徒指導”の先生が、不登校の担当の先生に!?
 井ノ口
井ノ口第19回はゲストに、栗東市教育委員会の中川謙二さんをお迎えしております。前回は辻先生に、ハーバールームでの現場の様子についてお伺いしました。
今回は、ハーバールームができた背景をお聞きしながら、学校という枠を超えて、不登校の子どもに限らず、子どもたちが育つ環境について考えていきたいと思います。私自身を含め、子どもの周りにいる大人たちが、どのような存在であるべきか、どのような振る舞いが大切か——そんな部分にも迫っていけたらと思います。それではまず、中川先生、簡単に自己紹介をお願いします。



はい、よろしくお願いいたします。
私、中川と申します。現在は栗東市の学校教育課に勤務しております。昨年までは市内の中学校で校長を務め、この4月から現職に就いております。
自己紹介といっても、前回の辻さんのように話題性のある経歴があるわけではなく、わりと地味な日々を送ってきました。小さい頃から振り返ると、「ちょっと変わった子」という印象を持たれていたかもしれません。
人前で自己紹介する際によく話すのですが、私はあまり夢がなかった子でした。家庭の事情もあり、「将来何になりたい?」と聞かれるたびに、どこか後ろめたさや空虚感のようなものを感じていた記憶があります。大工や新聞記者など、いろいろな職業を口にしてはいましたが、本当にやりたいことは特になかったように思います。
ただ、教員になろうと思ったときに浮かんだのが、「自分にはやりたいことがない代わりに、やりたいことを持っている人を応援したい」という気持ちでした。人の夢を一緒に見させてもらえる仕事になりたい——そんな思いから、教員を志したのだと思います。
また私は、うまくいかないことがあると、それを一度家のどこかに隠してしまうクセがありました。一方で、不具合や壊れたものに出会うと、「なぜだろう?」と原因を知りたくなる性分もありました。これは、後ほどお話しする不登校や不適応の対応においても、自分の中で活きているクセなのかもしれません。



ありがとうございます。中川先生は美術の先生をされていたんですよね。



先ほども申し上げたように、実は「教員になりたい」という思いが先にあったんです。そのための手段、あるいはツールとして、何を使おうかと考えたときに、美術を選ばせていただきました。そういう意味では、図工や美術をずっと熱心に取り組まれてきた方の前に出るのは、正直、非常に気恥ずかしい気持ちがあります。(笑)



そうなんですね!(笑)
次に、ハーバールームを立ち上げる前のお話を聞きたいなと思います。 中川先生は、学校で先生として働かれていた時から、不登校の子どもたちと接する機会はあったんですか?



そうですね、どこからお話しするのがいいか少し迷うのですが……。私が教員になったのは平成2年頃、もう35年ほど前になります。
その頃から、不登校の問題は確かに社会の関心を集めていたと思います。ただ当時は、1つの学級に1人か2人いるかどうか、という割合だったように思いますね。
前回お越しいただいた辻さんが、もしWindows 11のような最新型だとしたら、私はWindows 95の時代の古い仕組みの話をしているようなものです。そんな昔の話をして意味があるのかな、と少し心配にもなります。
それでも、辻さんが語ってくれたハーバールームの発想や理念は、実はずっと以前に、いろんな人と一緒に作り上げてきたものが土台になっている——そう思うと、少しうれしい気持ちになります。



ハーバールームのもととなる「校内適応指導教室」は、いつ頃から大切だな、と感じられていたのですか?



後ほど詳しく理由はお話ししますが、実は当時、私たちは「適応教室」や「適応指導教室」という言葉を絶対に使わない、とメンバーで申し合わせていました。代わりに「支援室」という表現で作ろう、という構想が生まれたのが、今からおよそ24年前、2000年頃のことです。
その頃の私は、辻さんと同じく生活指導を担当していました。当時は栗東市内の学校を何年かごとに持ち上がっていくような時期で、保護者と一緒に子どもの更生について考え、話し合う日々を送っていました。
そんなある日、私の上司にあたる生徒指導主事の先生と車の中で話していたときのことです。彼女は、辻さんも話していたように、当時から「生徒支援」と「生活(生徒)指導」を合わせて“生徒指導”と呼び、やんちゃな子の対応も不登校の子の対応も含めて一体的に進めていこうという考えを持っていました。
そして彼女は本当に子どもや保護者に寄り添う人で、夜7時8時まで別室で話し続けるような方でした。そんな彼女が、ふとこんなことを言ったのです。
「生徒支援って、怨念のたまり場やな」
強烈な言葉でした。どういうことか尋ねると、こういう説明でした。
──子どもは、みんなの中に入れなかったり、学校に行けなかった悲しみをここに置いていく。
──親は、一生懸命生きてきたのに、なぜ子どもが立ち止まってしまったのかという自責や、学校への「もっと支援してほしかった」という願いを置いていく。
──学校の先生も、「これ以上何をすればいいんだろう」という思いを置いていく。
関わる人みんなが、その悲しみや思いをそこに置いていく——彼女はそれを“怨念”と表現したのです。
そんな彼女が突然、「来年、この生徒支援を担当してくれへんか」と言いました。私は3月まで生活指導をしていて、4月から加配という形で生徒支援に入ることになりましたが、最初は何をしていいか全くわかりませんでした。
しかし徐々に見えてきたことがありました。当時の私の印象では、生徒支援には「優しい」というイメージがありました。ただ、それは必ずしも褒め言葉ではなく、人から評価されにくい、見えにくい仕事だという意味でもありました。生活指導は、落ち着きを取り戻したり成果が見えたりすると評価されますが、生徒支援は心配や課題が集まるばかりで、成果が形になりにくい。
その現状を変えたい——そんな思いを持ち始めた頃、ちょうど国の不登校政策も大きく舵を切り始めた時期でした。



なるほど…!



平成15年、文部科学省から「今後の不登校対応のあり方」という通知が各校に出されました。そこには、「積極的支援に乗り出せ」という明確なメッセージがありました。これは、平成13年に行われた不登校児童生徒の追跡調査が背景にありました。調査の結果、中学時代に不登校だった子の多くが、「当時は嫌だったけれど、あの支援があって良かった」と感じていることが分かったのです。
私にとっても、この「積極的支援」と「社会的自立」という二つの言葉は非常に新鮮で、印象深いものでした。当時、市の中で生徒支援を担当する仲間と話していても、「これからは積極的支援の時代だ」という熱気がありました。
そこで私は、「優しいだけの支援」から、「働きかける支援」へと変えていきたい、と校内で言い始めました。具体的に何をするのか、何が必要とされているのかを見える化する——その第一歩として着手したのが、別室の環境改善です。
当時の多くの別室は、物置部屋のような場所でした。机を二つ置いただけの狭い空間で、「快適にすると教室に戻れなくなる」という理由から、意図的に居心地を悪くしている場合も少なくありませんでした。私はこれを大きく変えたかった。
そこで活用したのが、学校にあった「放送室」でした。といっても、朝の放送をする小部屋ではなく、かつて放送局として使われていた、教室の1.5倍ほどの広さがある本格的なスタジオです。防音仕様になっており、廊下の喧騒が入らない——これは、不登校の子どもたちが安心できる環境を作るうえで理想的でした。
「ハーバー」も「ポート」も港を意味しますが、あえて「ドック(修理工場)」ではなく「港」という言葉を選びました。それは、壊れたものを直す場所ではなく、羽を休める場所——船がしばし波を避け、船体をゆっくり置いておくような場所——というイメージを大事にしたからです。
中学校で子どもたちを見ていると、普通の学校生活を送っているように見える子でも、実は心の中では大変なことがたくさんあります。友達の中で言いたいことが言えない、面白くなくても笑わなきゃいけない、興味がなくてもノリに合わせなきゃいけない……。そんな波にもまれている子どもたちが、少しでも休める場所でありたい——その思いが、名前のきっかけになりました。



ハーバー、とは、「休む場所」という意味だったのですね…!



部屋づくりと並行して取り組んだのが「生徒支援システム」です。
それまでも、不登校の保護者との懇談や週1回の会議(部会)はありましたが、それらを体系的につなぐ仕組みはありませんでした。そこで、各段階に名前を付けて整理しました。
最初の相談 → 「初回相談」
継続して行うもの → 「継続相談」
といった具合に、全ての支援を名前でつなぎ、流れを可視化したのです。
当時流行していたPDCAサイクルになぞらえて、支援もマネジメントサイクルとして位置付け、ツールとしてハーバールームやポートルームを組み込みました。
従来は、不登校が起きてから「どうするか」を考える受け身の対応でした。しかし実際には、不登校はある日突然発生するわけではありません。当時の学校でも、毎年ほぼ同じ規模の子どもが存在していました。
ならば、あらかじめ定員8名の支援室を作り、増える時期が分かっているなら、その時期に合わせて教員が相談できる習慣を作るべきだ——そう考えたのです。
こうして、「場所(ハーバー・ポート)」と「仕組み(生徒支援システム)」の両輪で、不登校支援をアクシデントではなく“予定されたイベント”として学校に組み込む試みが始まりました。
だからアクシデントじゃなくてイベントとして、不登校問題を取り入れる。そんな発想なんかも混ぜながら、作っていたものなんです。



うん、なるほど。ちょっと今、内容がいろいろ整理できてないんですけど、不登校の問題ってずっとあるのだから、最初から仕組みとして用意しておく、っていうのはやっぱり大事だと感じました。
ハーバールームは、「0から1でぱっと、新しく突然始まった取り組みで生まれたもの」だと思ってたんですけど、実はその背景には、先生たちの長い葛藤や思いがずっとあって、それがあってこそハーバールームという場が作られたんだな、と。
やっぱり学校が「一人の先生が多くの子どもを相手にする空間」である以上、そういう仕組み化をすることや、経営とどううまくかみ合わせるか、っていうことを考えるのはすごく大事で。つまり、綺麗ごとだけじゃ収まらない部分が確実にあるんやな、っていうのをすごく感じましたね。



あの、辻さんっていう方。前回カモラジオに出てくれたんですけど、僕、大好きなんですよ。
彼がね、僕が別の学校に行ってる間に、生活指導から生徒支援に変わったって聞いて、「あぁ、すごいな」って。僕もずっとそれがいいなと思ってたんです。
で、その生徒支援に辻さんが入ってくれたっていうのは、本当に嬉しかった。
なんていうかね、彼はすごく熱くて、いろんなことやってくれる人なんですけど、僕がもうひとつ惚れ込んでるのは、そのクールさなんです。半年後とか来年のことを子どもたちとすぐ話すんですよ。それに、ここを頑張らせるために、あえて別のところに働きかけるとか。
まるでビリヤードの玉を打つみたいに、この玉を使ってあれを動かす、そうやって子どもを変えていく力がある。そういうクールさを持ってる人に、ぜひ成長支援をやってほしいなって思ってました。
ちょっと話は変わるんですけど、打ち合わせのときに「保護者と学校が和解する」っていうテーマにすごく興味があったんです。きっかけがね、夏休みのはじめごろのことなんです。職員室をふらっと歩いてて、ふと先生の机の上にあった葉書を見たんですよ。暑中見舞いの葉書で、「先生、覚えておられますか?」って始まっててね、最後は「うちの子どもはまだ先生の学級の子どもですよね」って終わってた。
何の変哲もない暑中見舞い…なんですけど、読んだ瞬間、スーッと冷たいものが流れたような、ちょっと怖い感じがしたんです。だってこれ、卒業生の親からの手紙じゃなくて、まさに今、教室に行けない子の親が夏休みに書いたものなんですよ。
多くの保護者って、子どもが学校に行けなくなると、自分の子への関わり方とか、生き方まで反省する場面があるんです。そして繰り返し考えて、やっぱり「学校、ちょっと助けてくれよ」って思う瞬間が必ずある。でも、学校がその声に応えられない。そうすると、どんどんきれいなことばかり言う教員への不信感が募っていくんです。
本来は、子どもが親と学校をつないでくれる。でも、その子どもが不在になると、間は開く一方で、不信感も積もっていく。だから、「子ども抜きで、親とつながれる仕組み」を作りたいと思ったんです。
ただね、電話一本とっても、相手のことを思ってかけられなかったり、せっかくかけてくれた電話に出なきゃと思って無理したり、そういう遠慮や負担があるわけです。短期間ならまだしも、長期的な支援をするなら、大人が疲れ切ったら意味がない。
そこで作ったのが「申し合わせシート」です。連絡の頻度はどのくらいにするか、学習はどれくらい注力するか、最初からお互いに決めておく。担任や関係者に「第三者からどんな話をしてもらうと助かるか」とか、「言いにくいことは何か」を聞き取って、それを形にしたんです。
これはハーバールームやポートルームと並んで、不登校支援全体で使える仕組みになりました。



このお話を聞く前、「優しい」のが私はむしろすごく大事やなって思ってたんですよね。
不登校の子どもに対しては、優しくないといけないし、寄り添ってあげないといけないし、とにかくその子の立場に立って「よしよし、大事大事」ってすることが大事や、と。
でも、その辻先生や中川先生に感じる、ある種のドライさ、クールさっていうのが、申し合わせシートであったり、仕組み化する部分で実は重要な役割を果たしていて。
もちろん、「大事にする」タイプの人も必要なんですけど、そうやって頑張る基盤を作ったり、安心できる環境を整えたりすることが、社会的自立の基盤になるんやな、と。
そういう意味で、学校っていう場所自体が、働きかける場としての役割も持たせる必要があるんやなっていうことを、二人の話を順番に聞いて、知ることができました。
まとめ
いかがでしたでしょうか? ちょうど盛り上がってきたところで時間が来てしまい、次回へと続く形になってしまいました。
言わずもがなですが、中川先生のお話って、想像力にすごく働きかける話し方をされるんですよね。私は正直、論理的な話とかが少し苦手なんですけど、不思議とスッと入ってくる。
「さすが先生やな」と感じました。
そして次回は、今回の続きから──なんと前代未聞のアドリブ収録で、第18回のゲストだった辻先生と中川先生、それに私の3人でお届けします。どうぞお楽しみに。