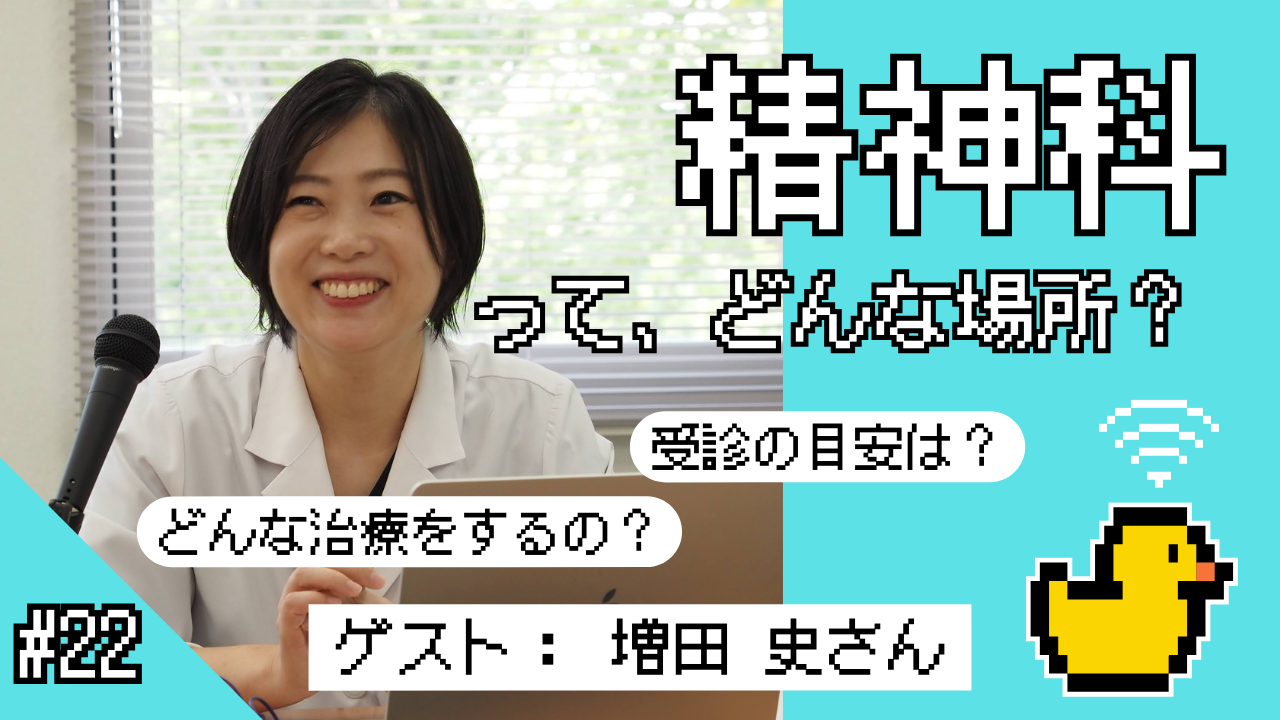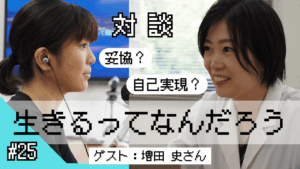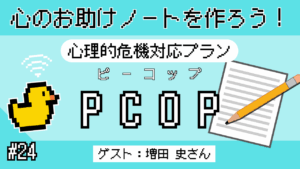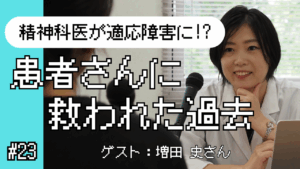本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第22回は、ゲストに精神科医で医学博士の増田史先生をお迎えしております。今回は、精神科のお仕事についてお聞きしていきます。
増田 史(ますだ ふみ) さん
精神科医、医学博士。2010年に滋賀医科大学医学部卒業後、初期研修を経て、2012年に滋賀医科大学精神医学講座に入局。脳波を用いた脳機能研究に取り組んでいたが、徐々にうつ状態となり、精神科を受診。適応障害と診断される。休職やカウンセリングで少しずつ回復し、今も回復途上。2021年より滋賀医科大学精神科助教。脳機能研究や児童思春期を中心とした臨床を行うほか、精神疾患に対するスティグマ(偏見)解消にも取り組んでいる。2児の母。出産と育児、また仕事との両立は「想像をはるかに超えてしんどい」。
参考:10代から知っておきたいメンタルケア〜しんどい時の自分の守り方 増田史 ナツメ社 2021年9月1日初版発行 2022年7月1日第3刷発行
本編の前に…
 井ノ口
井ノ口増田先生は、実はカモラジオを、出演する前から聴いてくださっていたそうで…本当にありがとうございます。



いえいえ。第1回のゲスト、伊藤いつかさんから番組のことを聞いて、それ以来ずっと聴いていました。もともとポッドキャストが好きで、面白そうだと思ったんです。



ありがとうございます。心に残った回などはありますか?



そうですね。特定の回というよりも、このラジオのコンセプト自体が新鮮でした。ゲストのパーソナルなストーリーが見えてくるのがとても面白いです。皆さんが「王道」や「既定路線」から外れた形で、自分を認めて生きている姿を聴けるのは、すごく貴重な体験だと思います。人の生き方を分けてもらえる感じがいいですね。



ありがとうございます。私も「正解がないメディアにしたい」という思いがあって。自分から遠い考え方だったとしても、その背景や文脈を知れば、違った見方ができる。そんなメディアに育てたいと思っています。



それはとても大事だと思います。人間の想像力には限界があります。自分の想像の範囲だけで語ることがいかに浅はかだったか、私自身30歳前後でようやく気づきました。だからこそ、自分の想像を超えた世界があると考えることが大事だと思っています。



本当にそうですね。今はインターネットが普及して、世界で起きていることが一目でわかる時代です。カモラジオのように、気軽に情報発信できる時代だからこそ、より一層そういう想像力が大事になりますね….余談が長くなってしまいました。
精神科ってどんな場所?



今回は、精神科を知るきっかけになるような回になればと考えています。まず最初に、精神科はどういう人が受診するでしょうか?



精神科どんな人が受診するか。そうですね。一言で言うとやっぱり心のつらさがあった場合に受診をしていただくということがいいかなと思います。
直接心、例えば気分が落ち込んだり、逆に元気すぎて困ったことが起きたり、不安が強かったりする場合もありますし、眠れない場合もあります。あとは体の症状がすごくつらくて続いているけれども、内科や外科で見ても理由がわからないという場合に、気持ちの方も一緒に見ていきませんかという形で、内科や外科の先生から紹介をいただくこともあります。



もしこのラジオを聞いていて、つらい気持ちがあって精神科を受診しようかなと思っている人の中で、「こんな小さいことで相談するなんて甘えなんじゃないか」「自分が弱いからなんじゃないか」と思う方もいるかもしれません。そういう気持ちは持たなくても大丈夫ですか?



はい。「そんな程度で来て…」などと思ったことはないですね。やっぱりお話を聞くと、それぞれに「大変やったよな」ということがあります。だから「困ったな」と思って相談してくれたこと自体が嬉しいですし、ありがたいなと思います。



ありがとうございます。とはいえ今、精神科ってすごく忙しいと打ち合わせでもお聞きしました。初診まで1ヶ月以上かかることもあるんですよね。



そうですね。1ヶ月でも進まなくなってきていて、申し訳ないという感じです。



でも苦しい気持ちに関する相談は精神科だけでなく、他の機関にも頼れる場所がありますよね。不登校に関することだったら電話相談の窓口もあります。メール相談もありますし、警察にも相談窓口がありますよね。(詳しくは記事の最後を参照)



はい。相談窓口だけではなく、例えばお子さんでしたら学校を通じてスクールカウンセラーさんやスクールソーシャルワーカーさんに相談できることもあります。
市町の発達支援室や発達支援センターも力になってくれます。臨床心理士や公認心理師の先生方も非常に力になってくれますので、お近くのカウンセリングルームなども活用していただけるといいと思います。



ありがとうございます。実際に先生の診療の中で、不登校のお子さんが来られることはありますか?



はい。ありますね。私の初診枠はほとんどが10代の方で、中高生が多いです。その中で「学校がしんどい」「行っていない」という方もしばしばいらっしゃいます。



もし不登校のお子さんを持つ親御さんがこのラジオを聞いていたら、精神科などを頼る目安になるものはありますか?



そうですね。病院を受診する目安として、まず「食べられない」「体重が減ってきた」という場合は、小児科でもいいのでぜひ受診してほしいです。中高生はまだ成長期なので、体重減少は強い心身の影響がある可能性が高いです。
他の相談機関に相談するタイミングは早ければ早いほどいいと思います。病院を受診することで選択肢が広がることもあります。例えば気分の落ち込みや涙が何週間も続いている、強い不安で外に出られない、自分ではコントロールできない考えが次々に浮かんでくる、怖い声が聞こえる・何かが見えるといった症状がある場合は、病院の力になれる部分があります。
いずれの場合も、環境の見直しや調整も大事になってきますので、そこも一緒に考えていけたらと思います。



なるほど。ありがとうございます。では次の質問に移ります。精神科を受診するときに、具体的に診察がどのように進んでいくのかをお聞きしたいと思います。まず初診と呼ばれる一番最初の診察の流れから教えていただけますか。



そうですね。初診のときは大体1枠で30分から1時間半程度お時間をいただき、お話を伺うパターンが多いと思います。
病院によっては、先にソーシャルワーカーさんや看護師さんが、これまでの経緯や今困っていることを聞いて、その後に精神科の医師が改めてお話を伺う場合もあります。最初から医師がすべて聞く場合もあり、そこは病院によって異なります。基本的には「どんなことに困っているのか」「そこに至るまでの状況」を伺うことになります。



その後、第2回目の診察から具体的な治療が始まるのですか?



そうですね。初診の中で「今何が起きているのか」という見立てと、「どんなアプローチが選択肢としてあるのか」という話をすることが多いです。それに沿って2回目以降の診察に来ていただき、試したことがどうだったか、状況がどう変わったかを伺います。
ただ2回目以降は、どこの病院でも時間がかなり限られていて、10分程度のところがほとんどだと思います。そこが精神科医療の課題の一つですね。



やはり先生ご自身も診療の中で葛藤はありますか?



ありますね。申し訳ないですがあります。本当はもう少しお話を伺いたいのですが、お薬の説明だけで終わってしまうこともあります。
また、ご家族の中で食い違いがある場合などは、時間を別にとって少し長めにお話を聞くこともありますが、それも限られています。そのため、どうしても診察時間が慌ただしく感じられる方もいらっしゃるのではと心配しています。



なるほど。ありがとうございます。イメージですけど、精神科の治療って普通の病気や怪我のように薬を飲んで症状を治す方法と、心理学的なアプローチの2つがあるという理解で合っていますか?



はい、合っています。
しっかりお話をする中で、自分の物事のとらえ方を見直したり、新しい選択肢を持てるようにする「心理療法」が必要な場合があります。また「この症状には効くと言われている薬がある」という場合には「薬物療法」も選択肢になります。
大きく分けると、薬物療法と精神療法が2つの柱になります。
精神科でないとできないことは、薬物療法と診断・診断書の作成です。心理療法に関しては、カウンセリングという枠組みで1枠50分ほどかけて面接を行うところが多いです。精神科とカウンセリングルームが並行して協力することもよくあります。



では、最後の質問に移りたいんですけど。史先生は、もともと脳の研究をされてたんですかね。



(苦笑い)…そうですね。



うつ病ってここ50年ぐらいの新しい病気なのかな、とか思ったりしていて。ずっと長い間、幻覚が見えたり聞こえたりすることを「妖怪が取りついた」とか、祖父母世代だと「気持ちが弱いからだ」「甘やかしてるからだ」と捉えることもあったと思うんです。今はさすがに少ないかもしれませんが、まだ残っている部分もあるのかなと。その精神病というのは、認知の歪みみたいなものなんでしょうか。



そうです。なるほど。脳の研究で笑ってしまったのは、自分が端くれ者すぎて、というだけなんですが。(笑)
うつ病や双極性障害、統合失調症などでは、脳の中の伝達物質のバランスが崩れることが起きている、という点はおおむねコンセンサスがあります。心の病気と呼ばれる一方で、脳へのアプローチも有効で、お薬の開発も進んできています。
精神病というと、いわゆる幻覚(幻視や幻聴)や妄想と呼ばれる現実と違うタイプの考えを持つ症状を指します。今は広い意味では「精神疾患」という言い方をするのが一般的です。



精神疾患、ですね。ありがとうございます。



ちなみに、幻覚や妄想といっても、感じている方にとっては幻ではなかったり、妄想と呼ばれてもその人にとっては当たり前の感覚であることも多いんです。そう考えると、私たちがつけている名前自体、当事者の方を尊重できていない部分もあるのかもしれません。
最近、当事者の方が精神疾患についての教科書を出版され、その中にもそういう指摘がありました。なるほどと思わされましたね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は少し補足を三つお伝えします。
一つ目は、精神科以外の場所に頼るのも一つの選択肢だということです。本編でも触れましたが、学校であればスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーに相談してみるのもよいかもしれません。
二つ目は、本の紹介です。
一冊目は増田先生の著書『しんどいときの自分の守り方』。とても面白いのでぜひ読んでみてください。
二冊目は、本編の最後に出てきた当事者による教科書『生きづらさを紐解く私たちの精神疾患』です。詳しくは以下にリンクを載せていますので、チェックしてみてください。
三つ目は、精神科以外に頼れる連絡先や電話番号を以下にまとめていますので、必要なときに活用していただければと思います。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
【本編に出てくる本】
1.「生きづらさをひも解く私たちの精神疾患」 YPS横浜ピアスタッフ協会 , 認定NPO法人地域精神保健福祉機構 , 蔭山正子 /認定NPO法人地域精神保健福祉機構 https://www.comhbo.net/?p=39059
2.「10代から知っておきたいメンタルケア〜しんどい時の自分の守り方」 増田史 ナツメ社 2021年9月1日 https://www.natsume.co.jp/books/15323
【相談窓口】
◉全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110 最寄の法務局につながります。
◉法務省子どもの人権110番
電話:0120-007-110 いじめや虐待などについて相談できます。
◉警察庁 ヤング・テレホン・コーナー
最寄りの相談窓口の電話番号が掲載されています。
◉子どもの人権SOS eメール