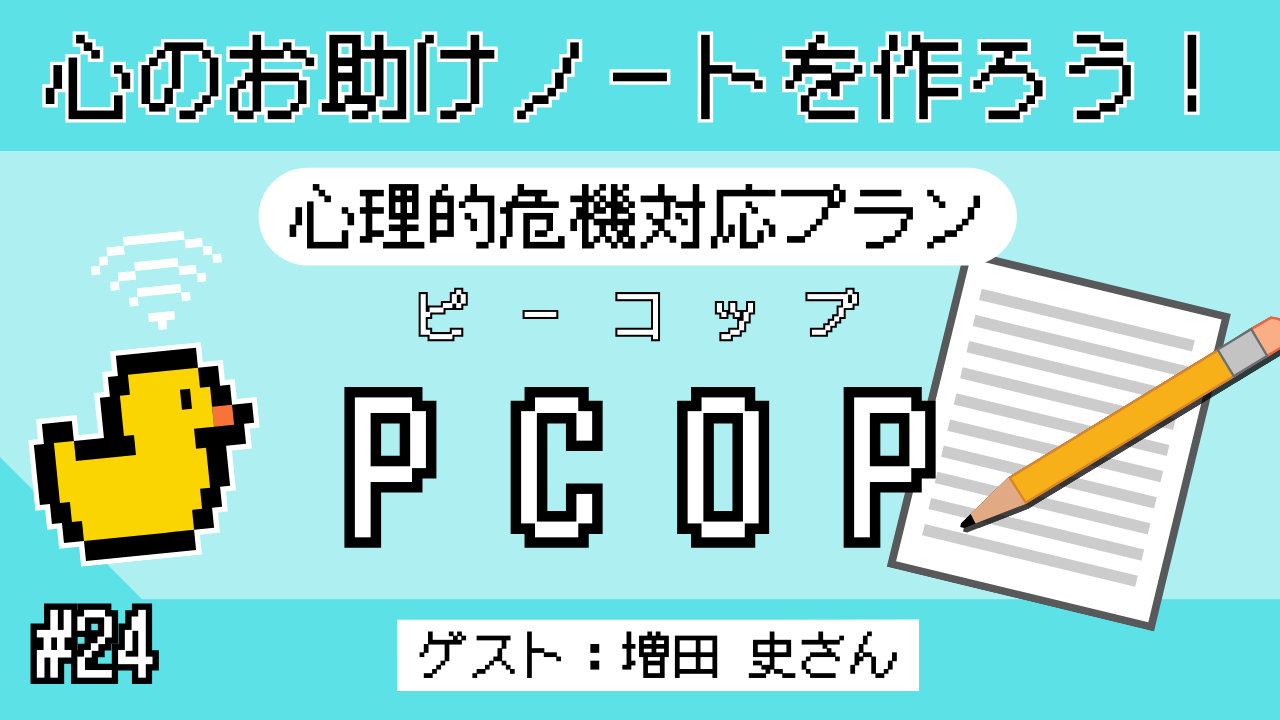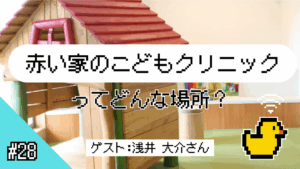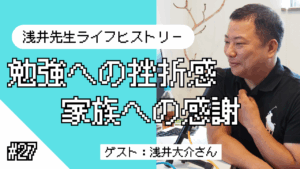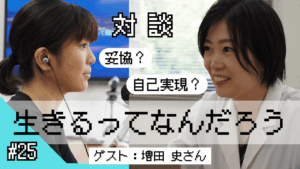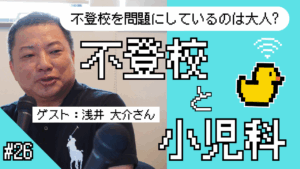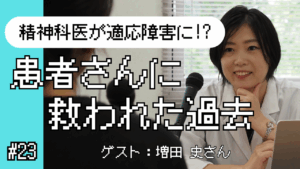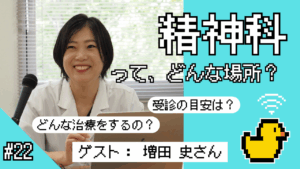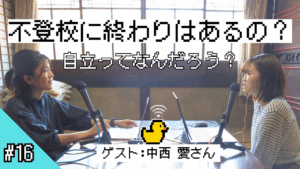本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第24回は、ゲストに精神科医で医学博士の増田史先生をお迎えしております。今回は、PCOPという、「心のお助けノート」の作り方についてお聞きしていきます。
増田 史(ますだ ふみ) さん
精神科医、医学博士。2010年に滋賀医科大学医学部卒業後、初期研修を経て、2012年に滋賀医科大学精神医学講座に入局。脳波を用いた脳機能研究に取り組んでいたが、徐々にうつ状態となり、精神科を受診。適応障害と診断される。休職やカウンセリングで少しずつ回復し、今も回復途上。2021年より滋賀医科大学精神科助教。脳機能研究や児童思春期を中心とした臨床を行うほか、精神疾患に対するスティグマ(偏見)解消にも取り組んでいる。2児の母。出産と育児、また仕事との両立は「想像をはるかに超えてしんどい」。
参考:10代から知っておきたいメンタルケア〜しんどい時の自分の守り方 増田史 ナツメ社 2021年9月1日初版発行 2022年7月1日第3刷発行
心理的危機対応プラン「PCOP」(ピーコップ)ってなに?
 井ノ口
井ノ口この回の配信予定の月が、9月なんですよね。9月といえば、夏休みが終わって2学期が始まる時期。気持ちがブルーになる方も多いと思います。よく言われるように、若い方の自殺が増える季節でもあります。
今回は、そういう「本当に苦しい」「本当につらい」という気持ちを抱えている人に向けて、心のお助けの糸口になるようなお話を届けられたらと思います。ではまず、 PCOPについて、増田先生にご説明いただけますか?



「PCOP」というのは「Psychological Crisis Coping Plan 」の略で、日本語にすると「心理的危機対応プラン」です。つまり、ものすごくしんどいときにどう対応するかを考えるためのプランですね。
もともとはアメリカで開発された認知行動療法のひとつで、軍人さん向けに作られたものなんです。戦争から帰ってきた軍人さんの中には、トラウマ反応から自殺企図が非常に多いことが問題になっていました。
そこで臨床心理学の先生が「短時間で実施できるプログラム」を考案した、というのが始まりです。
実際に取り入れてみると、半年後の自殺企図が、ピーコックを使ったグループでは8割近く減った、という効果が実証されています。
そこで、「日本でも広めよう」という話になりまして。評論家の荻上チキさんが最初に声を上げてくださり、私にも声をかけていただきました。一緒に作成者として、日本版を作ることになったんです。
PCOPは無料で使えるので、ぜひ検索してみて下さい。
STEP1&STEP2 心のお助けノートを作ってみよう!



では、早速PCOPを実践していこうと思います。私と増田先生も、事前に「お助けノート」を作ってきましたので、それを紹介しつつ作り方を説明します。
まずステップ1、紙とペンを用意しましょう。



そうですね。紙とペンを用意しましょう。スマホのメモ機能でも大丈夫です。私はそうしています。
もともとの原文には「オリジナル感を出して愛着を持てるように」と書かれていて、飾り付けたり、お気に入りのノートを使うのもおすすめだと紹介されています。



はい。ではステップ2、5つの項目を記入していきましょう。
1つ目は「警告サイン」です。



はい。警告サインとは、自分の心がしんどくなっているときのサインのことです。
PCOPの例には「自罰的な考えが止まらない」「後悔ばかり浮かぶ」「自傷行為をしてしまった」「上司を見かけたとき」などが書かれています。
「これがあったら危ない」という、自分なりのサインを考えて書き出します。



心・体・状況に分けて考えると分かりやすいですよね。
私の場合、心のサインは「みんなが自分の悪口を言ってる気がする」とか、「ジロジロ見られてる気がする」です。
体だと「肩が凝る」。
状況だと「ゼミが終わった後」です。発表が終わると“ああすればよかった”と落ち込みやすくて…。



なるほど。私は「過食をしてしまった時」とか、状況だと「気圧が低いとき」ですね。これ、多いと思います。私もすごく気圧にやられるタイプです。



わかります…。
では次の項目に移ります。
2つ目は「セルフマネジメントの方法」、コーピングレパートリーとも書かれています。



はい、ここが一番大事な部分です。
セルフマネジメント=対処行動、あるいはコーピングとも呼ばれます。
警告サインが出たときに、自分がとれる行動の選択肢を増やしておくこと。この数をなるべく多く用意しておくのが、PCOPの肝になります



なるほど。私は「YouTubeを見る」とか、特に「ぽいんてぃ」というYouTuberの動画を見ること。
それから「首をぐるぐる回す」「寝る」とかも書きました。



いいですね。
資料には「プチプチをつぶす」「トイレにこもる」「ぬいぐるみを抱きしめる」などの例も載っています。
PCOPの紹介PDFの最後には「コーピングレパートリー」としてリストがあり、前半は行動、後半は考え方(認知)の例になっています。
行動と認知、両方をバランスよく持っておくといいですね。
行動の例なら「動画を見る」「ネイルをする」「運動する」「お茶を飲む」「自然に触れる」など。
認知の例なら「今こういう考え方になっているときは、こう考えると抜け出せるかも」という自分の言葉を書いておくことです。しんどいときは思考が狭くなって思い出せなくなるので、元気なときに「自分を励ます言葉」を書き残しておくのが大事なんです。



はい。では次に移ります。
3つ目は「生きる理由」です。



そうですね。「生きる理由」と聞くとすごく大げさに感じるかもしれませんが、ほんの小さなことで大丈夫なんです。
「とりあえず今日は死なないでおこう」とか、「明日までは生きてみよう」とか、それくらいでもいい。
私は自分に「今生きてるのはおまけ・余生」って書いたりします。昨日の自分より少しでも成長していたらOK、というふうに考えるようにしてます。



うん、なるほど。私は「ガチョウを飼いたい」とか(笑)。
あと、ゲームの『あつ森』ってあるじゃないですか。私はやったことないんですけど、人生でいつかは挑戦したいなと思ってて。「それをやるまでは死ねへん」って書いたりしてます。



めっちゃいいですね!素敵です。



ありがとうございます(笑)。



私が言った例は、どちらかというと認知のコーピングに近いかもしれません。厳密には「生きる理由」じゃないかも、ごめんなさい。



いやいや、大切なのは“質より量”ですからね。



そうそう。必要なだけ書いておけば大丈夫です。



次に行きますね。4つ目が「サポーター」です。



サポーターですね。これは、思い浮かべたときにちょっとでも心が楽になる人や物のことです。キャラクターとかでも大丈夫ですよ。



あ、そうなんですね。



実際に連絡が取れる人でもいいですし、取れない人でもいいんです。



なるほど。今って「推し活」とかすごくあるし、推しの名前を書いておくのでもいいですね。



いいと思います!推しを隅から隅まで(笑)、全部書いておいて大丈夫です。そして、推しが増えたらどんどん追加していくといいと思います。



ですね!じゃあ最後、5つ目が「緊急連絡先」ですね。



はい。緊急連絡先は、ここまでやってみても「どうしてもうまくいかない」っていうときに頼れる先を書いておくことです。



なるほど。



たとえば通院している方なら、病院の夜間連絡先とか。もちろん日中の番号も書いておくと安心です。最終的には救急車を呼ぶこともありますよね。PCOPの紹介PDFにも「119に電話」と書いています。
それから「心の健康相談統一ダイヤル」とか「よりそいホットライン」といった相談窓口もあります。LINEでもつながれるので、そういう番号をひとつ入れておくといいですよ。
【相談窓口】
◉全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110 最寄の法務局につながります。
◉法務省子どもの人権110番
電話:0120-007-110 いじめや虐待などについて相談できます。
◉警察庁 ヤング・テレホン・コーナー
最寄りの相談窓口の電話番号が掲載されています。
◉子どもの人権SOS eメール
STEP3 心のお助けノートに書いたことを実際に試してみよう!



はい。これで一応PCOPは完成ですね。ステップ3では、「その中のどれかを実際に試してみましょう」と書いてあります。



そうですね。元気なときに一度やってみるのが大事です。



避難訓練みたいな感じですね。



そうそう。実際に危機的な状況になったとき、「じゃあ上から順番にやってみよう」と試すイメージです。それに、生きる理由やサポーターを思い浮かべる中で「あ、この人も入れよう」と思ったら、どんどん追加していいんです。
緊急連絡先も、「ここなら頼れそう」という場所を見ながら、ちょっとシミュレーションしてみるのがおすすめですね。



ありがとうございます。これでPCOPの紹介は一通りできたかなと思います。
……今ふと浮かんだんですけど、PCOPってもともと戦争を経験した兵士のために作られたってお話でしたよね。なんだか私たちの日常も、人によっては戦争と同じくらいのプレッシャーを抱えて生きていることがあるなと。学校も、人によっては戦場みたいに苦しい場所になってるんじゃないかなと感じました。



そうですね。「複雑性PTSD」という言葉があります。
通常のPTSDは、事件や事故、あるいはそれを目撃したといった単発のトラウマから起きるものです。フラッシュバックや不眠、気分の落ち込みなどが長く続く状態ですね。
一方で複雑性PTSDは、戦争、虐待、いじめなど、長期にわたるトラウマ体験によって起きるものです。厳密に言うと、単体のトラウマでも、複雑性PTSDは発症します。
特徴としては、通常のPTSD症状に加えて「自己組織化障害」と呼ばれるものが出てきます。
1つは感情のコントロールが難しくなること。気持ちが急に落ちたり、逆にカーッと怒りが湧いたり、テンションが急に上がったりする。
2つ目は、人間関係が安定して築けなくなること。
3つ目は、自分を尊重できず、自分で自分を見る目がとても否定的になることです。



なるほど。



そう言う意味では、いじめや学校での体験も、戦争に匹敵するくらい深刻な影響をもたらし得るんです。とてもつらいことですよね。



本当にそうですね。では最後にまとめとして――。
PCOPをやっても、もちろんこれで全員が治るわけではありません。どうしてもしんどくて耐えられないときは、身近な大人に頼ったり、精神科を受診することも大事だと思います。



もちろんです。



はい。そこは強調してお伝えしておきたいと思います。
まとめ
はい。いかがでしたでしょうか?
ぜひPCOP、実践してみてください。辛くなくても、試してみると「自分ってこうなんだ」って新しい発見があって面白いのでおすすめです。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
それではまた来週お会いしましょう。