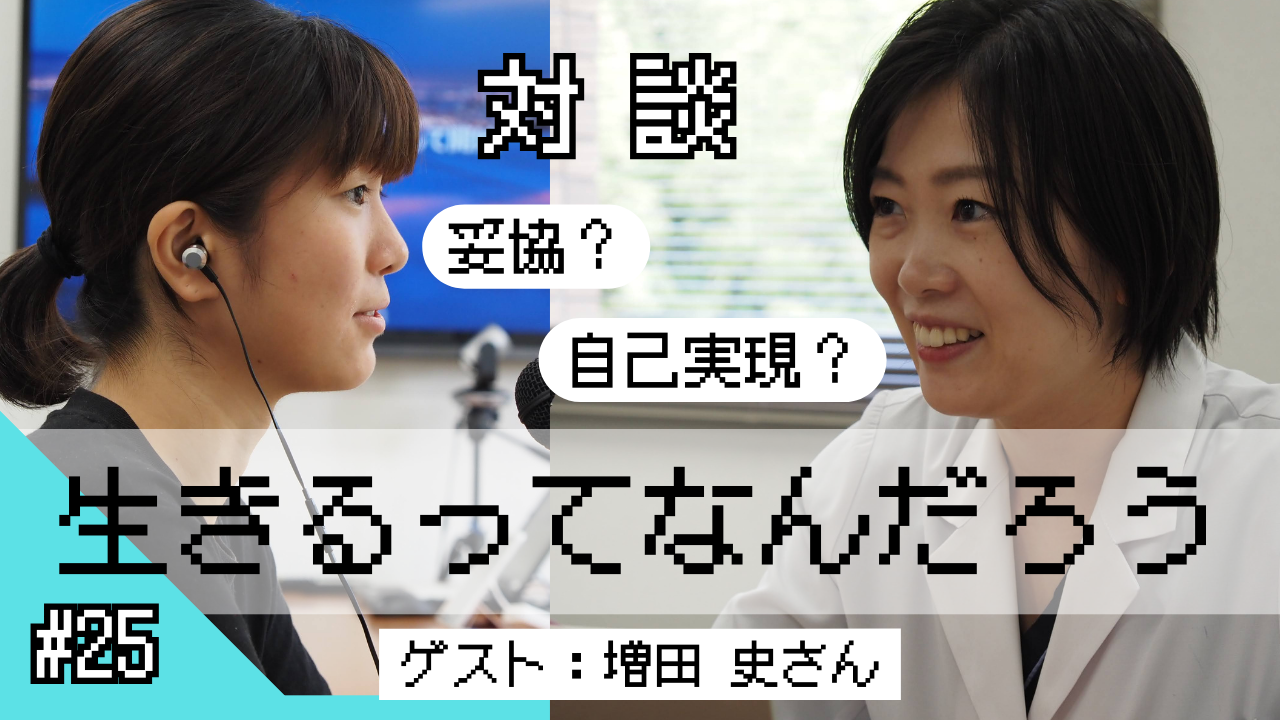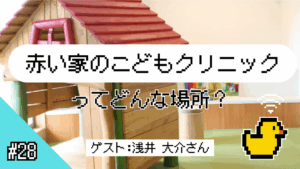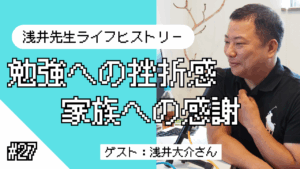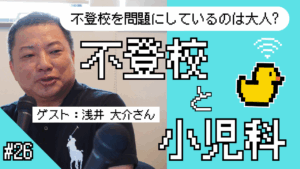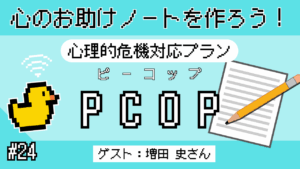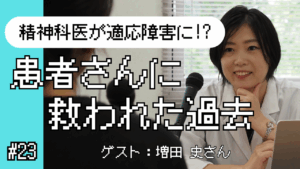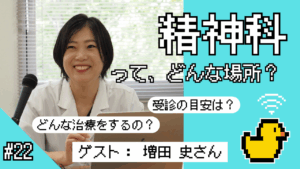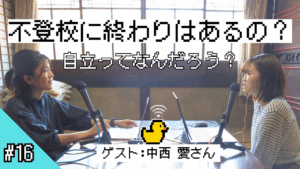本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第25回は、ゲストに精神科医で医学博士の増田史先生をお迎えしております。今回は、精神科の枠を超えて、学校や地域のメンタルヘルスについてお聞きしていきます。
増田 史(ますだ ふみ) さん
精神科医、医学博士。2010年に滋賀医科大学医学部卒業後、初期研修を経て、2012年に滋賀医科大学精神医学講座に入局。脳波を用いた脳機能研究に取り組んでいたが、徐々にうつ状態となり、精神科を受診。適応障害と診断される。休職やカウンセリングで少しずつ回復し、今も回復途上。2021年より滋賀医科大学精神科助教。脳機能研究や児童思春期を中心とした臨床を行うほか、精神疾患に対するスティグマ(偏見)解消にも取り組んでいる。2児の母。出産と育児、また仕事との両立は「想像をはるかに超えてしんどい」。
参考:10代から知っておきたいメンタルケア〜しんどい時の自分の守り方 増田史 ナツメ社 2021年9月1日初版発行 2022年7月1日第3刷発行
MBTIやHSP、いろんな情報に溢れる現代
 井ノ口
井ノ口精神に関することって、身近にいろいろ情報が流れてると思うんです。例えば最近やったら、MBTIってご存知ですか?
性格診断みたいなものです。あとはHSP(Highly Sensitive Person)とか。HSPやMBTIは、また精神科とはちょっとジャンルが違うんかなと。



そうですね。精神について私の知る範囲ではですけれども、HSPに関しては今採用されている診断基準ではないんです。
ですので、HSPという診断の方が例えばどのくらいいらっしゃって、どういうふうなケアをしていくのがいいかっていうのは、体系だって今コンセンサスがあるものではないのかなと。
人生の選択に正解はある?



なるほど。医学的なコンセンサスはないけども、そういうのが流行っているのは、ある種「生きづらさを抱えてる人が多い」とか、「自分自身を知りたい」という思いから来るのかなと思います。
私自身も、生きづらいなっていう気持ちになることが多くて。その中で私がどうやって生きづらさを解決するかというと、しんどい気持ちの理由を、社会構造を学んだり、本を読んだりして、「だからしんどいんや」って理解することで楽になった、という経緯があります。
例えば「あなたはあなたのままでいいんだよ」とか、そういう言葉をかけてもらえることが救いになることももちろんあったし、それも大事やなと思うんですけど。
でも、実際目の前に置かれてる状況を見たときに、いくら「自分らしく」とか「気持ちを強く持とう」としても、今月の家賃どうするんですかとか、卒業後奨学金をどうやって返していくんですかとか、そういう現実があったときに、気持ちの持ちようだけではどうにもならない場合ってすごく多い。子どもでもそういうことって多いと思います。
子どもに対しても、これは自己反省的に思うんですけど、カモラジオでも「子どもはもっと自由にあるべきだ」とか「尊重されるべきだ」っていうことを言うのは大事だけど、結局は「いい大学に入ること」とか「校則を守ること」とか、そういう評価軸で判断されて苦しんでる子はまだ多いんじゃないかなって。
その中で私がどうやって折り合いをつけてるかというと、結構「妥協する」っていうのが大きいかなと。きれいごとじゃなくて。自分の譲れないところは譲らないけど、具体的に言うと私は「大学を卒業する」というのが一つ大きなターニングポイントでした。
私は1年休学を挟んでいて、大学2年生のとき本当に大学に行きたくないって気持ちがすごくあって、親にも「やめたい」って泣きながら相談して、ほぼケンカみたいになったことがあったんです。
でも親としては「大学は卒業してほしい」と。学費も出してもらってるし、結局通うことになったんです。
そこから「大学を否定するのはやめよう」と思って、真面目に通い始めました。しんどいなと思うこともあったけど「もう行くって決めたんやったらちゃんと行こう」と。そうしたら楽しいこともあったし、通わなかったら出会えなかった人たちにも出会えた。今になって思えば結果オーライかなと。
…こんな感じです。史先生はどうですか?



そうですね。今のお話を聞いて、環さんは「妥協」って言われましたけど、生きてると「こっちを選んだ方がよかったかな」とか、「選ばなかったからこうなったな」とか、選択を迫られることって多いじゃないですか。
日々の小さなことでも、「今日パン買っとけばよかったな」とか、「あの靴履いて出かけたらよかったな」とか。選択しなきゃいけないことって多いと思うんです。
で、「こっちを選ばなかったらどうしよう」とか、不安もあるんですけど。でも、どっちを選んでもいいんじゃないかなと。
たとえ「あっちを選んでたらこうだったな」と思っても、「そう思ったな」と受け止めて、また次の選択に進めばいい。
結局、行った先には必ず変化があって、そこでまた新しい選択をすることになる。
環さんが言った「結果オーライ」って、すごくよかったなと思います。
でも、もしあのとき大学をやめてたとしても、そこにはそこなりの変化があったと思うんです。どっちを選んでも「結果オーライ」と思えるのが大事なんじゃないかなと。
楽観的にそう思えることが、自分自身にとってもいいし、そして社会もそうであるといいなと思います。



うん。確かに。私の中で「これが正解の選択」というのが先にあって、その正解から自分がどれだけ遠ざかってるかで、自分の選択を解釈してたなと。



私もすごく「社会規範」とか「社会で望ましいと思われてる部分に添えるかどうか」で、自分をジャッジしてたので。
でもそういう社会規範って、いつまでもついて回りますよね。結局、求められてるすべての声に耳を傾けていたら「ここだ」っていう道はないんですよね。
びっくりするほどないんで、やっぱりもう自分でやるしかない。
「あなたのままでいいよ」というよりは、「あなたでしかいられないから」。だから自分でやっていかなあかんなって、思ってます。
ちなみに私、『あなたのままで大丈夫』っていう本を出してるんですけど。
前書きを読んでいただくとわかるんですけど、「あなたであることを引き受けないと始まらない」っていう内容で。実はちょっとタイトルはミスリードかも…って思ってます。(笑)



「大丈夫」って言われないと、自分が自分であることを受け入れにくい世の中やなって思うんです。
「自己実現」って言葉ありますよね。あれ、すごく変な言葉やなって。自分って自分でしかないのに、あたかも「今の自分じゃない自己」に向けて達成していかなきゃいけない、みたいな。就活講座とかで特に言われるんですけど。
そう。だからめっちゃ二極化してるなって思ってて。
「自分は自分のままでいいんだよ」っていう思いと、「もっと成長しなきゃ駄目だよ」という思い。両極の考えがある気がします。



なるほど。なんかどっちも「外から言われること」な気がしますね。
子どもって、邪魔がなければちゃんとエネルギーをためて、自然に変わっていくんですよね。
でも「ほっとくと怠ける」「甘える」って思ってる大人が多いから、「頑張らせなきゃ」ってなってしまう。そこから「自己実現しろ」みたいな話になるんだろうなって。
でも私はもっと楽観的でいいと思うんです。やりたいことあったらどんどんやっていく子の方が多い。
逆に「自分にふたをしたまま自己実現に突っ走る」と、私みたいになったり、支配する側になったりもする。
だから「自分で大丈夫」「ここにいていい」って思えることが大事で、それが結果的にその子なりの成長につながるんじゃないかなって思います。
幸せは現実に宿る



確かに。私、「自己実現」って言葉を聞くだけでアレルギー反応があって(笑)。「頑張らなきゃ」って強く思ってしまう。
でも今のお話で、「やりたいことを素直にやった先に成長がある」というのがすごく腑に落ちました。それが「自己実現」なら、ほんまにそうやし、そういう社会になってほしいと思います。



就活とか企業だと「目標を決めてそこを達成する」っていう思考にならざるを得ないのかもしれないけど…。
でも、それってすごくしんどいと思います。



ほんと、しんどいですよ。



私自身、全然そういうの合わなくて。子どもの体調次第で予定が全部変わったりするし。結局「毎日の積み重ね」しかないんですよね。
一番しんどかったときは「何年後に何してるか決めろ」って言われてたんですけど…。



あ、それめっちゃわかります。実は私のパソコンのデスクトップ、今「10年後の自分がどんな姿になりたいか」っていう表なんですよ。(笑)



すごい!それが合ってる人もいますよね。
でも私は「生きてるか死んでるかもわからんのに」って思っちゃうタイプで。(笑)
だから私は「それは私には合わなかった」と思うんです。今は「現実の中に幸せが宿るんじゃないか」って思っています。



なるほど。ありがとうございます。最後、この4回を通しての締めとして、最後の質問なんですけど──史先生にとって、生きる意味って何でしょうか?



生きる意味、なんでしょうね。それこそ、生きる意味についての言説って、世の中に結構飛び交ってるじゃないですか。
私、中学生ぐらいのときに、それでめちゃくちゃ悩んだんですよ。「生きる意味」とか「生まれてきた意味」とか。
でも、どれもしっくりこなかったんです。
「何かを成し遂げるため」とか言われても、そんな人になれるとも思えなかったし。だって、何十億年後かには地球は太陽に飲み込まれてなくなるわけですから。
最終的には何も残らないし、意味もないわけです。
そのときに「意味はない」ってハッキリ書いてある本に出会って。私はそれを読んで、「あ、嘘つかないで言ってくれる人がおった!」ってすごく救われたんです。
中学生のときの私のバイブルは、その人の本でした。でもね、そこで私は納得しちゃったんですけど、実はその先があって。
「意味はない」って言ったあとに、「でも一つ一つの命がここにあること自体は奇跡だ」って書いてあったんです。大人になってから、その続きがあったことを知ったんですよ。
だから「意味はない」っていうとこだけで終わらないな、って今は思っていて。意味、意味っていうと大げさですけど……。さっき「現実に幸せは宿る」って言いましたけど、私の望みとしては、一つ一つの瞬間が本当に愉快であること。それが大事だと思ってるんです。
たとえば今、こうやって環さんと話してる、この一瞬一瞬でも。
それが愉快であること。それでいいんじゃないかなって。
本当に一つ一つを愉快にできたら、それはなんて素晴らしいことなんだろうって、最近は思ってます。
……まあ、でも10年後ぐらいに聞かれたら「何言っとんじゃ」って思うかもしれないですけどね(笑)。



そうですね。なんか……打ち合わせで先生が「畑したら人類みんな幸せになると思うんですよね」っておっしゃってたんですけど、今のお話ってそこに繋がったりするんですか?



そうですね。あ、すいません、毎日暑い中で畑をされてる皆さんに申し訳ないんですけど(笑)。
でも最近のメンタルヘルスの不調の一つに、「お金の不安」──つまり将来への不安、がありますよね。大学に入って、その先ちゃんと就職して、お金を稼がないといけない……そういうのが至上命題のように輝きすぎてるんじゃないかって思うんです。
でも結局、どんな道を選んでも「ご飯が食べられる」っていうのは、すごく大事なことだなって。
だから、自給自足みたいな暮らしにちょっと憧れたりもするんですよ。……まあ、実際には私、そんな体力も知識もないので、偉そうなことは言えないんですけど。
決して「畑をやれば楽ちんに暮らせる」なんて思ってるわけじゃないんですけどね。



そうですね〜私も畑したいです。ありがとうございます!
まとめ
はい。 いかがでしたでしょうか? これで増田史先生編、完結となります。
増田先生に、「生きる意味なんてない」と思っていたときのバイブルをお聞きしたんですけど、それが永井均さんの「翔太と猫のインサイトの夏休み」という本だそうです。 ぜひ読んでみてください。
それではまた来週お会いしましょう。 さようなら。