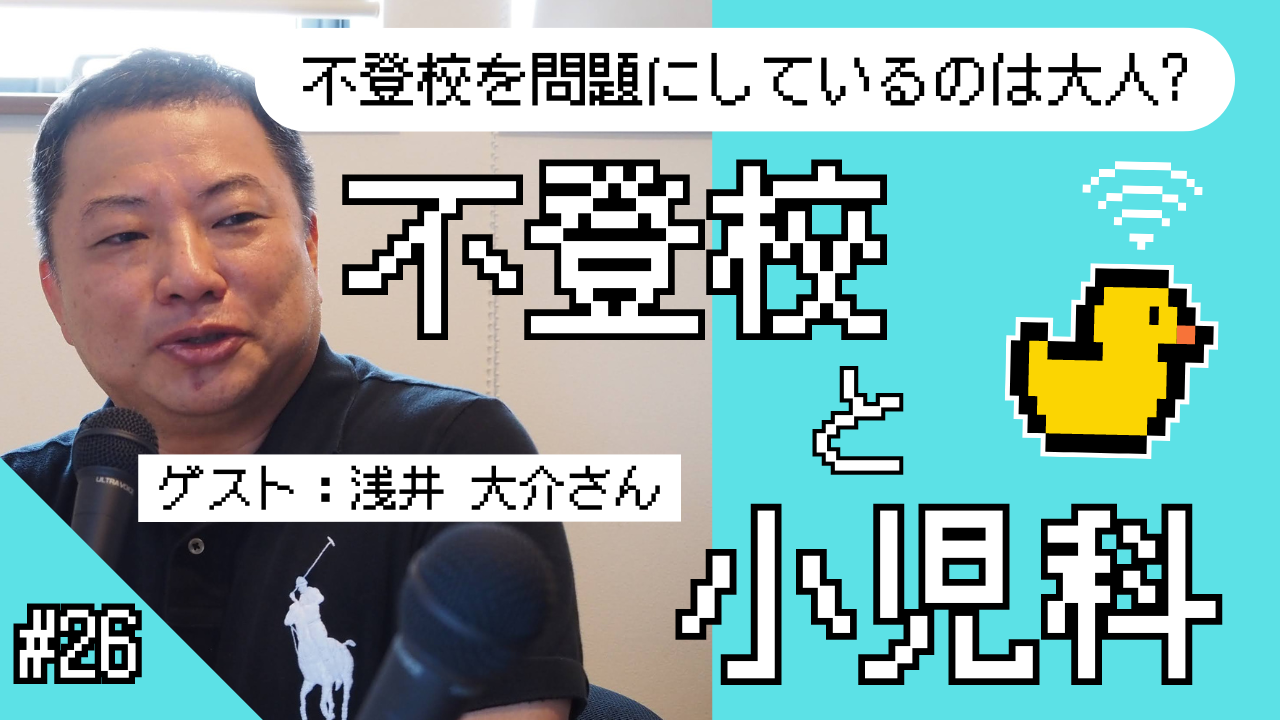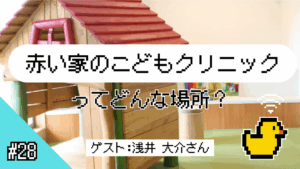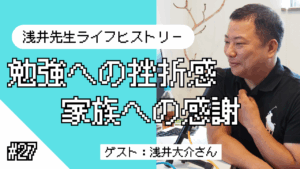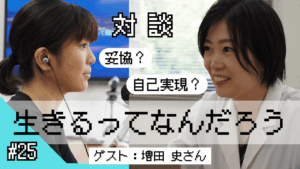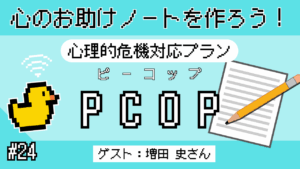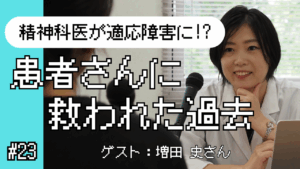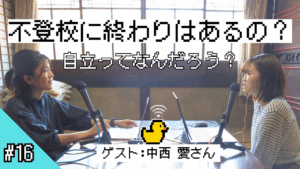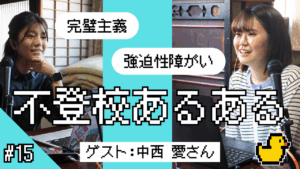本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第26回は、ゲストに小児科医の浅井大介先生をお迎えしています。今回は、浅井先生が不登校の子どもたちとどのように向き合ってきたか、子どもたちや親御さんにされている声かけについてお聞きしていきます。
浅井 大介 さん
小児科専門医、血液専門医。京都府立医科大学、京都第二赤十字病院などで小児科医として従事。2018年にあさいこどもクリニック(現:あかい家のこどもクリニック)を開院。診療のかたわら、国内の災害医療支援や海外の小児医療支援にも携わる。
参考:あかい家のこどもクリニックHPより
子どもを不登校にしているのは大人!?
 井ノ口
井ノ口第26回は、小児科医の浅井大介先生をお迎えしています。今回は、浅井先生が不登校の子どもたちとどのように向き合ってこられたのか、その経験などをお聞きしていきたいと思います。浅井先生、よろしくお願いします。



よろしくお願いします。



まず最初に、浅井先生は小児科医として、不登校の子どもたちと、どんなきっかけで関わるようになったのですか?



そうですね。小児科医って基本的には「体を見る」ことがメインなんです。たとえば感染症や風邪、お腹の痛み、食欲がない、どこかが痛い――そういった身体的な問題で来られる方が多いです。
不登校の子も「学校に行けない」だけじゃなくて、実際は「頭が痛い」「吐き気がする」「めまいがする」といった身体症状を訴えて来られることが多いんです。
よく聞くのは「朝起きられない」という訴えで、その原因のひとつに“起立性調節障害”という自律神経の不調があります。
これは不登校の子どものうち、半分弱くらいが持っていると言われています。そうした検査も小児科でできるので、受診されることが多いんですね。



なるほど。



でも実は、僕自身は“不登校”というのは「病気」ではなく、「現象」だと思っているんです。
学校に行けないという“状態”はあっても、それを病気として扱うのは少し違うかなと。ただ、残念ながら学校や行政など、社会全体がその子を拾い上げる仕組みをまだ十分に作れていない。
その結果、医療につながることが多いんです。でも医療の中でも“不登校を診る医者”ってほとんどいないんですよ。児童精神科の先生も、滋賀県内や京都でも本当に少ない。
なので僕のところに来てくださる方も多いんですが、僕自身も専門というわけではなくて。いろんな経歴の中で、心の問題や体の不調に向き合うようになり、結果としてそういう子たちが来てくれている、という感じです。
だから僕は、「不登校を病気にしているのは、社会とか大人なんじゃないか」と言いたいんです



確かに、「病院」と聞くと“治療する場所”というイメージがありますよね。でも不登校には、もう少し違う向き合い方が必要なのかもしれません。先生は、そういう子どもたちにどんな関わり方をされているんでしょうか?



不登校って、100人いれば100通りの理由や背景があると思うんです。
だから僕はまず「掘り下げて聞く」ことを大切にしています。
初診のときは1〜2時間かけて、家族関係や学校の様子、周囲の環境などを丁寧に聞きます。
先ほども言った通り、不登校は“現象”や“症状”なんです。だから、その背後に何があるのかを見ないといけない。
もちろん、子ども自身の体に貧血や甲状腺の問題、発達特性などが隠れている場合もあるので、そこは医学的にチェックします。
でも、そういう異常がないケースも多い。そのときに特に大事なのは「家族」と「学校」の二つ。この二つを聞かずに、子どもだけにアプローチしても意味がないと感じています。
たとえば高血圧や糖尿病って、薬で数値を下げても根本の生活習慣を変えないと治らないですよね。
それと同じで、学校に行けるようになったからといって「健康」になったわけではない。現象だけに目を向けるのではなく、その状態を作っている生活環境や心のあり方、人との関係性にアプローチしないといけないと思っています。



なるほど。不登校の状態だけを見るのではなく、その背景をしっかり見ていくということですね。



僕自身、昔ラグビーをしていて肩を痛めたことがあるんですけど、整骨院の先生に「マッサージだけしても治らない」って言われたんです。
結局、姿勢とか運動不足とか、日々の過ごし方が大事なんですよね。
それと同じで、子どもたちの「朝起きられない」とか「頭が痛い」という現象ばかり見ても仕方がない。
僕は不登校を「歯車の噛み合わせ」みたいなものだと思っていて、大きな学校という組織と、子どもという小さな存在。その噛み合わせが合わなくなったときに、必ず小さい方、つまり子どもの方が壊れてしまうんです。
だから、頭痛や吐き気、めまいといった症状が出る。その関係性を一旦切って、距離をとることが大事なんです。
医学的に言えば、これは「適応障害」に近い状態。適応障害の治療法には、薬物療法やカウンセリング、周囲のサポートなどいくつかありますが、一番大事なのは「ストレスとなっている環境から一度離れること」です。
だから僕は、子どもや保護者に「休むことは悪じゃない」「休むべき状態なんです」と伝えています。
保護者へかける言葉



打ち合わせのときにもお話しされていたんですけど、「朝起きられない子に、“朝起きること”を目標にするんじゃなくて、まずは“パワーを溜めること”に集中してごらん」って声をかけておられるって聞いて、なるほどなって思いました。
その一方で、子どもへの支援だけじゃなくて、先生は親御さんへのサポートにもすごく力を入れておられますよね。それはどういう思いから始められたんでしょうか?



そうですね。僕自身、今54歳なんですけど、医者として、またクリニックの経営をしていく中で感じてきたのは、「ものの考え方」とか「解釈の仕方」がすべてやなっていうことなんです。
そして、その“考え方の癖”みたいなものが、子どもの心と体にいちばん大きな影響を与えているのは、やっぱり“親”なんですよ。特にお母さん。お母さんの物事の受け止め方や言葉の使い方が、子どもに本当に鏡のように映るんです。



うんうん。



人間って「幸せになるために生きている」と思うんですよ。幸せの定義は人それぞれですけどね。お金を稼ぐことだったり、家族と過ごすことだったり、趣味に没頭することだったり。
でも、そもそも学校も“幸せになるため”に行く場所のはずなのに、学校に行くことで体調を崩したり、不調になるってことも多い。じゃあそれって本当に“幸せ”に繋がってるんですか?ということなんです。
そんなふうに、社会全体が「学校=幸せ」という前提を見直すことができたら、きっと大きく変わると思うんです。



たしかに……すごく耳が痛い話ですけど、私自身も反省しますね。
子どもにどう向き合えばいいか、って考える前に、自分がまず「学校には行くべき」とか「不登校はよくない」とか、そういう価値観を持っている限り、子どもを変えようとしても無理だなって。
結局、自分の中の「学校観」みたいなものを変えていかないといけないんだなって思います。



社会が僕たちをどう見るか、ではなく、僕たちが社会をどう見るか、も大事なんですよね。
この前、横浜の公立中学校で宿題をなくしたことで有名な工藤勇一先生の講演を聞いたんですけど、そこで言われていたのが「日本の教育には“主体性”と“当事者意識”が決定的に欠けている」ということだったんです。
日本の子どもたちは、問題を自分で考えて解決するというより、「誰かが何とかしてくれる」っていう構図になっている。親や先生が全部解決してくれる社会。会社でも同じで、「上司が何とかしてくれる」「社会のせいだ」って他人事になってしまう。



なるほど……。



しかもね、「不登校」という言葉自体が、実は日本特有なんですよ。韓国に少し似た概念はありますけど、欧米では「行かないなら行かなくていい」という感覚が普通です。
たとえばアメリカなんかでは、ホームスクーリングや地域活動など、社会とのつながりさえあればOKなんです。
僕もこの1年で、インド、フィジー、クロアチア、アメリカ、シンガポールを回ったんですけど、不登校という言葉すらほとんど聞きませんでした。
子どもたちは学校以外の学び方も普通にしていて、誰も「学校に行かない=問題」とは思ってない。
でも、いまはその価値観を変えていく時期にきてると思います。人口も減って、外国の方も増えて、多様な価値観の中で「どう生きるか」が問われている。その変換期に、子どもたちがいちばん影響を受けて、しんどい思いをしているんじゃないかと思うんですよ。
あと、小中高の受験がここまで厳しいのも日本くらいなんですよ。韓国も大学受験はすごく厳しいけど、小学校から夜10時まで塾に行くなんてほとんどない。
この前イギリスの人に言われたんです。「なんで日本はこんなに塾が多いんですか?」って(笑)。



確かに……塾だらけですよね。



そう。みんな夜遅くまで勉強して、「1点でも多く」って。
でも海外の受験制度って全然違ってて、「あなたは社会の中でどんな活動をしてきましたか?」を問われるんですよ。カナダに留学してる高校生が、ロボットコンテストで世界一になってたけど、それが評価される。
つまり、“何を主体的に選び、どう当事者意識を持って社会に関わっているか”が問われるんです。
だから、これからは「1点でも多く」「欠席を減らす」という横並びの価値観じゃなくて、「自分は何を大事にして、どう社会に関わるか」という方向にシフトしていく必要があると思います。
3つのM・まゆみの法則



先生は、お母さんたちに対しても「学校に行かせましょう」というより、もう少し違う視点で声をかけておられますよね。
特に、「学校に行かせなきゃ」と思っているお母さんたちに対して、「三つのM」と「ま・ゆ・みの法則」という2つをお話しされているのですよね?



ああ、そうですね。僕はよく「学校に行く・行かない」ということを考えるときに、外側に原因を求めすぎないようにって話をするんです。「担任が合わない」「友達とうまくいかない」「席を離された」——そういう理由でお休みすることもあるけど、それをずっと繰り返していると、キリがないんですよね。
中学に行っても高校に行っても、社会に出ても、嫌な人や合わない人は必ずいます。だから、外に原因を探してばかりだと、ずっと悩みが続いてしまう。



なるほど。確かに、どこに行っても「合わない人」っていうのはいますもんね。



だから大事なのは「自分が学校をどう考えるか」。行くほうがいいのか、行かないとどうなるのか——。それをじっくり話し合うことなんです。
で、その中で僕がよく紹介しているのが、ハーバード大学の研究にも出てくる「三つのM」。
※「3つのM(move/make/meet)」は、ハーバード大学出身の心理学者ショーン・アコール氏のポジティブ心理学の考え方をもとに紹介されることがあります。



「三つのM」って、どんなものなんですか?



英語の頭文字を取っていてね。
一つ目が「Move」、二つ目が「Meet」、三つ目が「Make」です。
一つ目の「Move」は「動く」こと。
人間は生き物ですから、動かないと気持ちも身体も滞ってしまう。だから学校に行かなくても、動いてほしい。
例えば近くを散歩するとか、イオンを歩くとかね。実はああいうショッピングモールって、歩きやすいように少しずつカーブしてるんですよ。まっすぐだとしんどくなるけど、曲がってるから自然と遠くまで歩ける。
そういう場所をうまく使えば、気分も変わります。
二つ目の「Meet」は「出会う」。
人との出会いが人生を変えるんです。誰と出会うか、どんな本・音楽・映画と出会うか——。そういうものが自分を作っていく。
そして三つ目の「Make」。これは「つくる」「創作する」こと。
悩んでいるときこそ、何かをつくるのが大事なんです。
僕、以前に「悩みはペットボトルの水みたいなものだ」って聞いたんですよ。5分くらいなら持っていられるけど、1時間持ってると腕が疲れるでしょ?悩みも同じで、考え続けるほどしんどくなる。だから、手を動かして何かをつくることで、悩みとの“接触時間”を減らすんです。
僕はコロナのときに料理を始めたんですけど、材料や分量を考えたり、食べる人のことを思ったりしてると、自然と悩みから離れられる。離れるって大事なんですよ。
大事なのは、子どもではなくお母さんに対して、執着しすぎないように、と言っています。例えば、1年前の今日のことって覚えてる?



いや…覚えてないです。



でしょ。たとえば、「1学期の成績が取れへんから、2学期やる気出ません」って言う子がいてね。
で、「その悩みって、来年も続きますか?」って聞いたんです。それと一緒で、「去年の悩み、今も覚えてる?」って
で、ふと思ったんです。人間って、どうでもいいことにけっこう執着してるなって。「こうでないとあかん」とか、「こうあるべき」って自分で決めつけて、そこに縛られてる。
でも実は、それって本当はどうでもいいことやったりするんですよね。
僕自身も、この歳になってようやく気づいたんですけど、もう54歳にもなると、「そんなこと言ってるうちに人生終わるかもしれへんな」って思うようになって。
だからもう、他人がどう言うとか、そういうのは本当にどうでもよくなってきたんです。それよりも、自分のことを慕ってくれる人とか、頼りにしてくれる人とか、そういう人たちを大事にしたいなって、心から思うようになりました。



なるほど〜。



「ま・ゆ・みの法則」は、「待つ・許す・認める」っていう姿勢なんです。あるエステ経営者の方が言ってた言葉なんですけどね。
※「まゆみの法則(待つ・許す・認める)」は、今野華都子氏が紹介・提唱された自己成長/人材育成の考え方です。
「待てない・許せない・認めない」と、お互いすごく苦しくなる。
甘えさせるっていうことじゃなくて、「時間をあげる」っていうのがすごく大事なんちゃうかなと思うんです。
僕もね、自分で子どもを育ててみて、本当に思うんですけど、うちは4人いて、それぞれまったく違うんですよ。性格も違うし、処理の速さとか、理解のスピードも全然違う。だからこそ、「待ってあげる」「許してあげる」「認めてあげる」。そういうことを、特に子どもに対してしてあげるのが、すごく大事やと思うんです。
よく「小1ならこれくらいできる」とか「10歳ならこれくらい」とか言われますけど、僕が見てても、10歳くらいまではほんまにまだ不安定やし、個人差がめちゃくちゃ大きい。
小3くらいまでは、心も体もすごく揺れる時期です。だからこそ、子どもたちには「待ってもらう」「許してもらう」「認めてもらう」っていう経験をしてほしい。
「何歳やからこうしなきゃあかん」って決めつけてしまうと、かえってしんどくなってしまうんですよね。
それに、体格も心の成長もほんまに個人差があります。後からぐんと伸びる子もいっぱいいる。
でもね、ここで大事なことがあるんです。
それは、「他人にやる前に、自分にやらないとあかん」ということ。
自分のことを待って、許して、認めてあげる。
それができへんと、他人にもできないんです。
結局、すべての問題って自分にあるんですよ。僕、経営者ですけど、職場でトラブルが起きたら、9割は院長である僕の問題なんです。スタッフ同士のことでも、患者さんとのことでも、結局は僕の対応が足りてない。
だから「問題がある」ってことは、「自分が成長するチャンスをもらってる」ってことやと思ってます。
他人がどうとか、学校がどうとか、先生がどうとか言いたくなるけど、
本当はその問題を通して「自分はどう対応するか?」って問われてるんですよね。
僕は、問題っていうのは天から与えられた“成長のための課題”やと思ってます。いろんなトラブルも、乗り越えるための試練なんです。
だからこそ、お母さんたちにはぜひ、自分自身を待って、許して、認めてあげてほしい。お母さんって、ほんまに一生懸命で、子どもとの距離も近くて、つい抱え込みがちですけど、少し距離を取って、「これは誰の課題なのか」って考えてみてほしいんです。
アドラー心理学でいう「課題の分離」っていう考え方があって、子どもの課題は子ども自身が取り組むべきもの。親が全部背負い込む必要はないんです。
たとえば「学校に行きにくい」「行けない」っていうのも、それは子どもの課題であって、子ども自身がどう考えて、どう行動するかが大事。親はそれを「待って」「許して」「認めて」あげることが大切やと思います。
まとめ
はい、いかがでしたでしょうか。浅井先生のお話からは、「主体性」という言葉をとても大切にされていることが伝わってきましたね。カモラジオでも、子どもたちが自分の力で考え、選び、動いていけるような、そんな“主体性”を育む環境づくりを、これからも大事にしていきたいなと思いました。