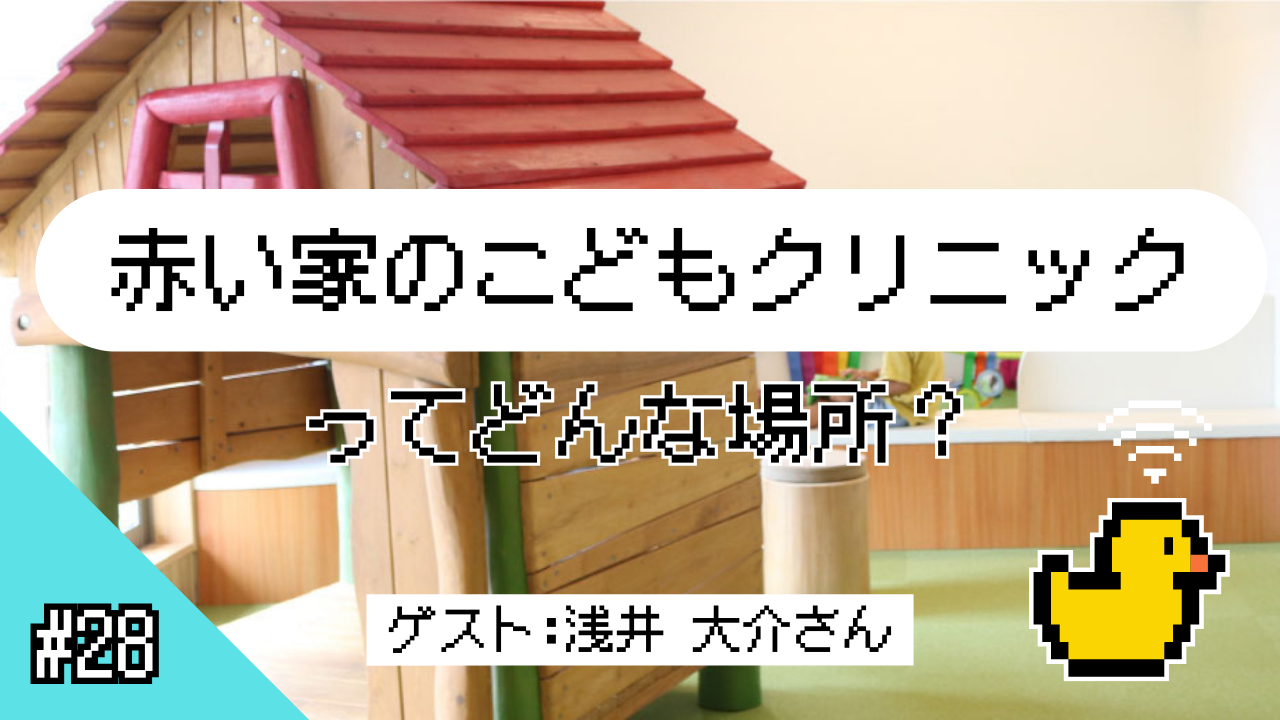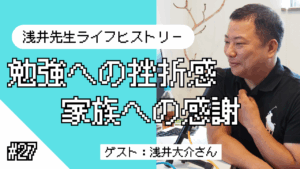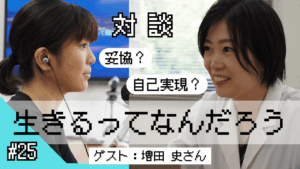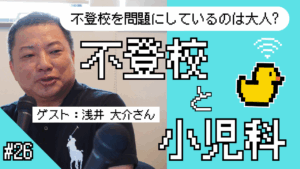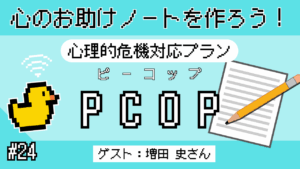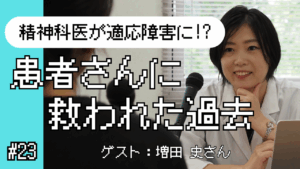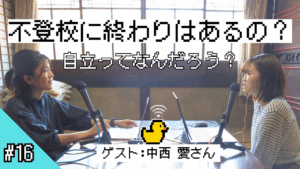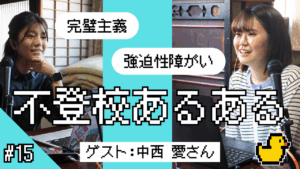本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第28回は、ゲストに小児科医の浅井大介先生をお迎えしています。今回は、浅井先生が運営する診療所、「赤い家のこどもクリニック」についてお聞きしていきます。
浅井 大介 さん
小児科専門医、血液専門医。京都府立医科大学、京都第二赤十字病院などで小児科医として従事。2018年にあさいこどもクリニック(現:あかい家のこどもクリニック)を開院。診療のかたわら、国内の災害医療支援や海外の小児医療支援にも携わる。
参考:あかい家のこどもクリニックHPより
赤い家の子どもクリニックができる経緯〜人に頼る大切さ〜
 井ノ口
井ノ口先生はこれまで診療の仕事をずっと続けてこられた一方で、病院経営にも力を入れていらっしゃいます。個人的にその経営の考え方がとても響いたので、今日はそのことについてお聞きしたいと思います。
まず、開院するまでの経緯についてお聞きしたいです。病院を立ち上げようと思ったとき、どんな心境だったんですか?



僕はもともと医者になった目的が、人の役に立ちたいというのと、海外途上国で医療支援をしたいという夢があったんです。
実際にアフリカやカンボジア、タイ、ベトナムにも行って少しずつ活動していました。でも、まとまった時間を取るのが難しくて、子どもも4人いるので、なかなか大変でした。
そのとき、妻から「海外の人を助けるのもいいけど、地域の人の役にも立つことも大事じゃないですか」と言われたんです。
それで地域のためにやってみようと決断したのが、今から7〜8年前くらいです。家の近くで開業し、最初は僕ひとりで診療していました。でも、やっぱり体を壊してしまって…。
ここで、不登校の話にも通じるんですけど、人に頼ることが本当に大事なんです。しんどいときは「しんどい」と声を上げて、助けてもらうこと、任せること。努力や根性だけでは、心や体が壊れてしまうことがあります。実際、周りでもそういう人が多いです。
特に、赤ちゃんを育てているお母さんたちは、今ほんとうに孤立しやすい。家の中で一人で抱え込んでしまって、「しんどい」って声を上げにくいんです。
日本の社会って、どうしても、子育てや介護は「家族がやって当たり前」っていう前提がありますよね。
海外ではそんなことなくて、ベビーフードを使うのも当たり前なんです。
日本だと「全部手作りじゃないとだめですか?」って聞かれることもあって、「そんなことないですよ、全然使ってください!」って答えるんですけどね。なんか、“手作り信仰”みたいな文化がありますよね。介護も同じで、「家族がやるのが当たり前」という考えが根強い。
そのために、妻が休日に、”困る前に繋がる”という、フィンランドのネウボラという出産・子育て支援システム、をもとに子育て支援をしています。



日本は手作りや家族の役割を重視する文化ですよね。



何でも自分ひとりで抱え込む必要はないんです。頼ることも大事。僕自身も院長として、医者として「人に頼ってはいけない」と思うことがありましたが、体を壊してから考えを変えました。
今は医者たちに業務を委任しながら、助けてもらうことを大事にしています。仲間に助けてもらうのは、人生において本当に大切です。
インドにはこういうことわざがあります。日本では「迷惑をかけずに生きなさい」と教えられますが、インドのことわざは逆で、「あなたもどうせ人に迷惑をかけるから、人に迷惑かけられなさい」というそうです。
旅行で行きましたが、人々があっけらかんとしていて楽しそうで、でも優しく応対してくれる。すごく好きな国の一つです。
日本も少しずつ緩んでいいと思います。頼ったらダメ、自己責任、だけではなく、しんどいときはしんどいと声を上げていい。子育てでも不登校でも、周りに頼ることは恥ずかしいことじゃない。お互いさまです。
勉強方法から学び直した浪人時代



組織の中で働くときって、立場によって見えているものが全然違いますよね。浅井先生は、一度すべての役割を自分でやってみて、そこで疲れたことで気づいたことがあったとおっしゃっていましたが、そのあたりをもう少し聞かせてください。



そうですね。第27回のときにも話しましたけど、「勉強の仕方を勉強しないとダメ」と同じように、経営も「経営の仕方を勉強しないとダメ」なんですよ。
それに気づいてから、経営塾に2年間通いました。
1年目の途中から、毎月東京にも通って、いろんなことを学んだんです。
その中で教えられたのは、「物の見方・考え方」がすべてだということ。
ある方向から見ればこう見えるけど、逆から見たら全く違う景色に見える。上から見るのか、横から見るのかでも、全然違ってくる。
だから、見方を変えることが本当に大事なんです。僕から見たクリニックと、患者さんから見たクリニック、そして一緒に働いてくれているスタッフ――うちでは“パートナーさん”と呼んでるんですけど――彼らから見えるクリニックの景色って、全部違うんですよね。でも、それぞれの立場で「自分の方が正しい」と言い合ってもきりがない。どちらも事実なんです。だから衝突することもある。
一度、そういうことを改めて感じたくて、日曜診療を自分ひとりでやってみたことが2回ほどあります。
会計から処方箋の準備、検査結果の説明、電話対応まで、全部自分でやってみたんです。そうしたら、「ああ、みんなこんなにいろんなことをしてくれてるんやな」って、心の底から実感しました。
1人で診療していた時に、妻も見かねて手伝いに来てくれたんですけど、ちょうど赤ちゃんが嘔吐したんです。本当に「人に助けてもらえるって嬉しいな」と思いました。



その“パートナーさん”という呼び方も素敵だなと思っていて。打ち合わせのときに先生が、「うちのパートナーさんには、仕事より子育てを大事にしている人も多い。だからこそ、自分もその子育てを大事にしてあげたい」とおっしゃっていたのが印象的でした。



そうですね。うちはパートさんがほとんどで、9割ぐらいの時期もありました。社員は1〜2人だけ。今は少し増えましたけどね。
僕は、パートさんもお金をもらって仕事をしている以上、みんな“プロ”だと思っています。でもやっぱり、子どもが小さい方が多いし、優先順位が違うこともある。
経営塾で学んだことの一つに「最高価値」という考え方があるんです。人はみんな、自分が一番大事にしている価値があって、それに関われないと強いストレスを感じる。
だからこそ、自分の最高価値を知ることが大事なんですが、それと同時に――特に経営者や夫婦の関係でも――「相手の最高価値にアプローチする」ことがすごく大事なんです。
たとえば、うちのパートさんの中には、「仕事よりも子どもや家族を優先したい」という方もいます。そういうときに、こちらがそれを理解して、配慮してあげること。これが本当に大事だと思うんです。
もちろんみんな仕事は一生懸命やってくれていますが、子どもが熱を出したり、急に休まないといけなかったりすることもある。そういうときに、こちらがどうサポートできるか。それが組織にとっても大事なことなんです。
経営者の自分はどうしても「仕事が優先」になりがちだけど、そうじゃない人もいる。それを理解して、お互いが歩み寄る。
たとえば、旦那さんが手作り料理が好きでも、奥さんがあまり料理に興味がない場合もある。価値観がずれるときに、どちらかが押し通すだけではうまくいかないですよね。お互いが歩み寄って、相手の価値にアクセスしていく。そうしないと、ずっと平行線のままなんです。



なるほど!



横浜の公立中学校で宿題をなくしたことで有名な工藤勇一先生によると、兄弟げんかも同じなんですよ。感情でやり合ってしまうと、もうきりがないでしょ。
「あいつは許せへん」「こっちが悪かった」とか言い出すと、ずっと終わらない。だから僕は、あえて「このけんかを続けるのは、あなたたちにとって得ですか?」って聞くようにしてるんです。言い方はシンプルやけど、本質的なんですよね。「お母さんがこう言った」「先生がこう言った」で揉めてしまうケースは本当に多い。
学校のことでも同じで、「学校に行けない」という状況を、「損か得か」「自分にとってどうか」という視点で考えるのは悪いことじゃないと思っています。
社会がどうこうではなくて、“あなたにとって”どちらがいいのか。その人自身の価値観に沿って選ぶことが大切なんです。
たとえば、先生が「成績がいいから東大・京大を目指しなさい」って言うけど、本人は「本当は医者になりたくなかった」という話もよく聞きます。
そういう“他人の価値観”で選んだ結果、しんどくなってしまうことが多い。だからこそ、「あなたにとって何が大事か?」を考えることが一番大切やと思う。
不登校も、実はそういう価値に気づくきっかけになると思うんです。
学校が自分にとってどんな意味を持つのか、どんな価値をくれる場所なのか。それを考えることが、人生を自分で歩む第一歩になるんじゃないかと思います。
地域と病院、目の前の人を喜ばせることを大切に



次に、病院と地域や人とのつながりについてお聞きしたいんですけど、
いまちょうどクリニックの事務室で収録させていただいています。
朝からたくさんの子どもたちが来ていて、今も赤ちゃんの泣き声が響いていますね。日曜日や長期休暇のときもできるだけ診察を続けて、地域のお母さんたちに寄り添っていらっしゃる印象があります。こうした「地域に開いた病院」であり続けることについて、先生はどんなふうに向き合っておられますか?



最近読んだ本に、小林正観さん「人生の目的は何かを達成することではなく、人に頼まれごとをして喜んでもらうことだ」と書かれていて、すごく腑に落ちたんです。
うちのクリニックの理念も「目の前の人に喜んでもらうことに全力を尽くす」なんですが、やっぱり僕の中では“喜んでもらう”というのがキーワードなんですね。
これはアンパンマンの作者・やなせたかしさんの「人生は喜ばせごっこ」という言葉からも影響を受けていて。
僕も以前は海外、アフリカに行きたいと思っていたけど、今ここで身近な人を喜ばせられないのに、遠くの人を喜ばせられるわけがないなと感じたんです。
だから日曜や祝日もできるだけ診察を続けて、「4〜5時間かかるような大きな病院に行かなくても、1時間くらいで診てもらえる」――
そういう形でお母さんやお子さんが少しでも楽になればいいな、喜んでもらえたらいいなと思っています。
うちはマニュアルがほとんどなくて、スタッフにも「どうすれば目の前の人が喜ぶかを考えて」と伝えています。例えば、傘と荷物とコートを持って入ってきた患者さんがいたとき、「どれを先に預かるのが喜ばれるか」は、その場の状況によって違うでしょう?
そういう“その人に合った喜ばせ方”を大事にしてほしいんです。資格や肩書きも、やれることを増やすための手段ではあるけど、目的ではない。
目的を取り違えないことが大事だと思っています。医学部に入ること、学校に通うことも同じで、その先に“何のために”があるのかを考えてほしいですね。
まとめ
はい。いかがでしたでしょうか?
今ってグローバル化が進んで、いろんな価値観がある中で、
「お互いの価値観を尊重することが大事だよね」って、もう耳にタコができるくらい聞く言葉ですよね。
でも、尊重にも2種類あるのかなと思いました。
一つ目は、「よく知ろうとすること」。
たとえば、自分にとって理解しがたい出来事があったときに、「なんでこの人はこういう考え方をするんだろう?」って探って、自分の中で納得できるまで理解しようとする尊重の仕方。
そして二つ目は、浅井先生がおっしゃっていたような、
「距離感を間違えないようにする」尊重の仕方。感情に引きずられず、落ち込みすぎずに、出来事だけを冷静に見ることで、相手をジャッジしたり干渉したりせずに理解するというやり方です。
この二つに優劣はないと思うんですけど、私はどうしても、その後者の“距離をとる尊重”をすぐ忘れてしまうんですよね。なので、今回改めてそのことを知れて、すごく勉強になりました。