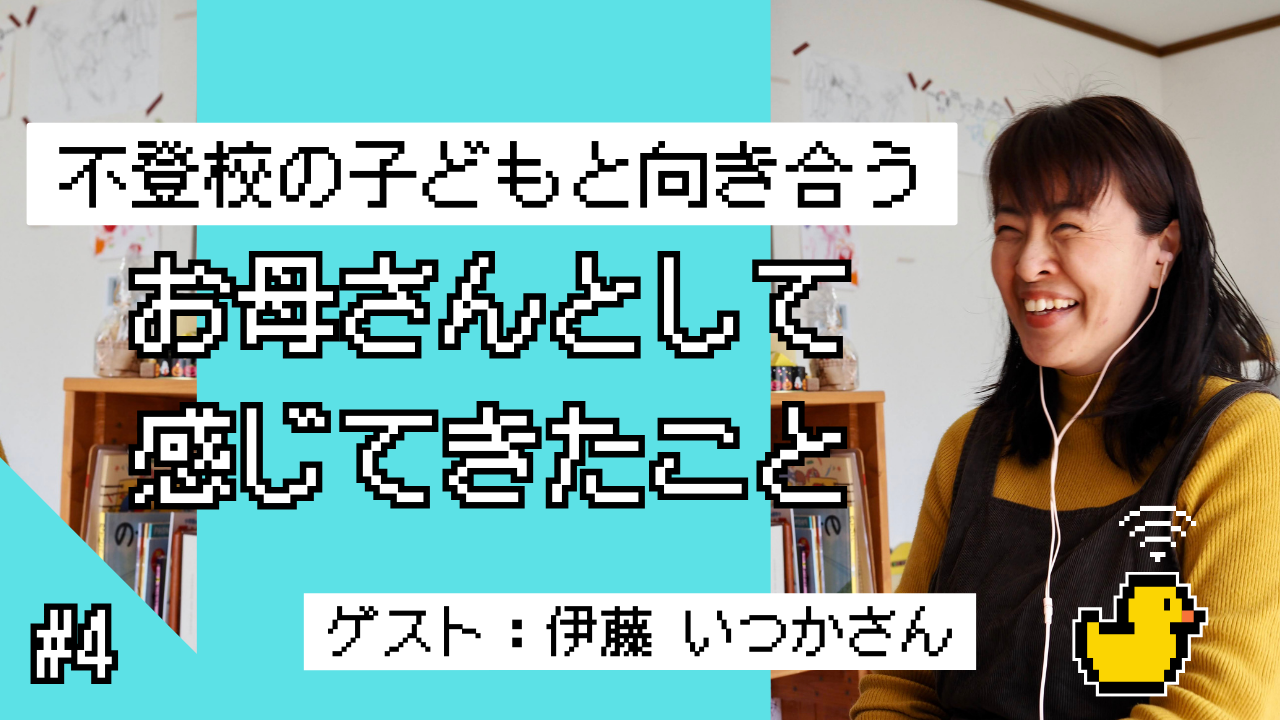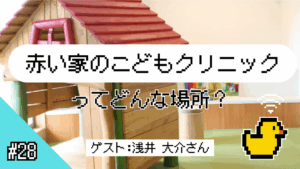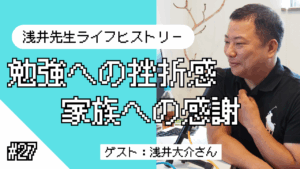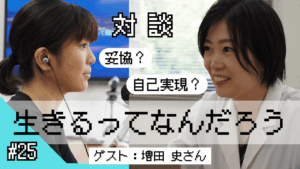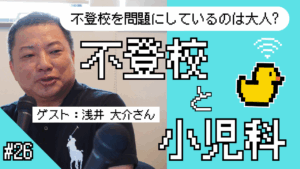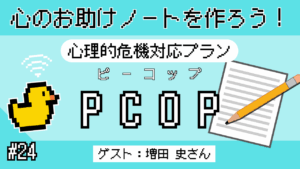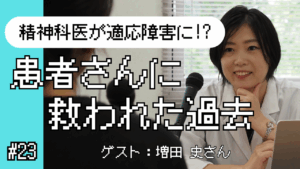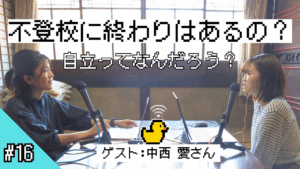本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
今回は、社会福祉士であり、市民活動団体「おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクト」の代表を務める伊藤 いつかさんをゲストにお迎えしました。今回は、不登校の子どもと向き合うお母さんとしての経験、またその経験から感じたことについてお話を伺いました。
伊藤いつかさん
社会福祉士。市民活動団体、おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクト代表として、滋賀県の各市町村にあるフリースクール等をまとめた「学校に行きづらい子どもたちのためのサポートブック」を制作。4児の母でもあり、過去には小学校教諭として約10年勤めその後、県や自治体のスクールソーシャルワーカーとして務めていた。
 井ノ口
井ノ口まず最初に、いつかさんのお子さんが不登校になった経緯を教えてください。



きっかけは引っ越しでした。もともと京都で先生をしていたんですけど、子どもが通っていた学童が終わってしまって、放課後に見る人がいなくなるので、実家に戻ることにしました。京都から浜松へ戻るタイミングだったんですけど、その「引っ越し」という変化が、子どもにとってものすごく大きな影響を与えたんです。
私自身も不安だったので、引っ越し前に「本当に引っ越しして大丈夫?」って子どもに聞いたり、話し合ったりしました。お互い納得したつもりだったんですが、いざ引っ越してみると……やっぱり違いました。



なるほど



浜松に引っ越したら、まず言葉も感覚も文化も価値観も違う。そんな環境の変化に、息子がすごく荒れたんですよね。
4月に転校して、3日目ぐらいに「先生、最悪や!」って言って帰ってきて、「俺、もう学校行かへん!」って。それを聞いたとき、すごく焦りました。
息子は特性があって、言葉に敏感なんです。発達の診断も受けていて、言葉の細かいニュアンスに引っかかるタイプ。言語能力が高い分、先生のちょっとした言葉に引っかかって、「もう行きたくない」ってなってしまったんです。



いつ頃から行きづらさを感じていらっしゃったんですか?



実は、4年生くらいから学校に行きづらくなっていました。もっと言えば、保育園の頃から「伊藤さんのお子さん、集団活動が苦手っぽいですよね」って言われていたんです。
お迎えに行くと、みんなは体育館みたいな広場に集まって「おかえりの会」をしているのに、うちの子だけ外で鉄棒をしていたり、砂遊びをしていたり。私は「うちの子、おもしろいな」と思う気持ちと、「でも、集団に入らないのはちょっと恥ずかしいな」という気持ちの半々でした。
京都では何とか学校に行けていたんですが、高学年になってくると特性がより強く出てきて、そこに引っ越しのストレスが重なり、完全に「学校に行かない」という選択になりました。



学校の先生も、ちょっとストレートに言葉をぶつけるタイプで、「出てけ!」と言ったら、本当に息子は教室から出て行ってしまう。(笑)
不登校が本格化したのは、小学6年生の夏休み以降です。最初は「別室登校」という形で教材室みたいな場所で過ごしていたんですが、だんだん行かなくなりました。そして、家の中での生活がどんどん荒れていったんです。



完全に不登校になってから、どんな風に過ごしていましたか?



浜松にいた頃は、息子は完全に家にこもっていました。おじいちゃんおばあちゃんも近くにいましたが、関係性はどんどん悪くなってしまいました。「学校行きなさい」「なんで家にいるの?」と祖父母が言うと、息子も反発して大喧嘩になる。
「これはもう物理的に距離を取るしかない」と思って、祖父母には「私が見るから」と伝え、なるべく息子と二人で過ごすようにして、ほんとに1人で抱え込むようになったんです。でも、そんな生活を3年間続ける中で、息子はゲーム依存のような状態になり、暴言や暴力が増えていったんです。
これはもう私一人ではどうしようもないと思って、最終的に児童相談所に相談しました。発達支援センターにもつながっていましたが、家庭内の状況を考えると、もっと第三者として介入してくれる機関が必要だと感じたんです。



その後、どんな風に変化があったんですか?



その後、中学時代に、縁があって滋賀に引っ越しました。
滋賀では、学校や病院の先生、児童相談所の方々が連携して支えてくれる環境があり、息子も少しずつ落ち着いていきました。さらに、地域のフリースクールや親の会に通うことで、ようやく外とのつながりを持ち始めました。
私自身も、親の会でいろんな情報を知ることができてようやく、「一人で抱えなくていいんだ」と思えるようになったんです。学校以外での学びの場があることを知り、学校の先生とも協力しながら、息子の成長をサポートするようになりました。



不登校から、立ち直るには、本当に何年も時間がかかるし、「学校に行ければOK」という問題ではないのかもしれませんね。いつかさんにとって、不登校の終わりみたいなものはありますか?



長い間、不登校の子どもを支える中で感じたのは、「学校に行くかどうか」よりも、子どもが日々の中で小さな幸せを感じられることが大切だということでした。最初からそう思えたわけではなく、私自身も少しずつ考えが変わってきたんですけどね。「今日はこれができた」「ちょっと気持ちが落ち着いた」「楽しいって思える時間があった」——そういう 小さな一歩を大切にすること で、子どもも少しずつ変わっていくのを実感しました。



今、不登校苦しむお子さんや、1人で抱え込んでいる親御さんたちに何かアドバイスはありますか?



子どもが「何に困っているのか」「どんな気持ちを抱えているのか」を知ることが大切だと思います。行く・行かないの話だけをしていると、余計に問題がこじれてしまうような気がします。
そして、親も一人で悩まず、頼れる人に相談することが大切です。私の場合、パートナーや友人、地域の親の会がすごく助けになりました。
結局のところ、ゴールは「学校に戻ること」ではなくて、その子が自分の人生を大切に思えること なのかなと。大人から見たら小さな進歩でも、それが積み重なれば、子どもにとっては大きな成長になります。
焦らず、子どものペースを尊重しながら、親も一緒に「小さな幸せ」を見つけていくことが、不登校の長い道のりの中で、とても大事なことだと思います。
まとめ
第4回のカモラジオでは、伊藤いつかさんが、不登校の子どもと向き合うお母さんとして感じてきたことについてお聞きしました。次回は、おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクトの活動についてお聞きしていきます。お楽しみに!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本編を聞くにはこちら↓