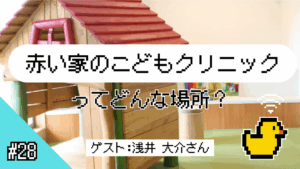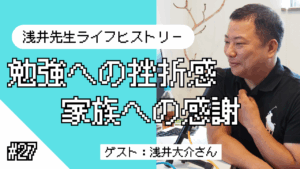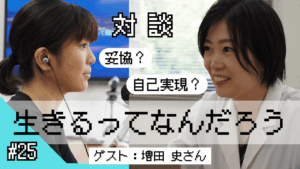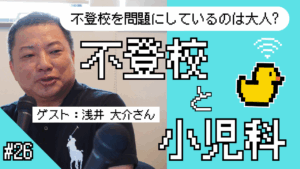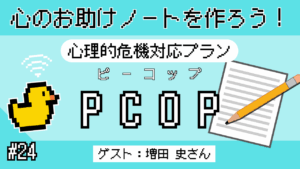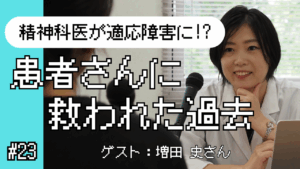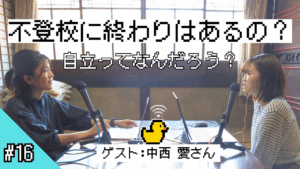本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
今回は、社会福祉士であり、市民活動団体「おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクト」の代表を務める伊藤 いつかさんをゲストにお迎えしました。今回は、「学校に行きづらい子どもたちのためのサポートブック」についてお聞きしていきます。
伊藤いつかさん
社会福祉士。市民活動団体、おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクト代表として、滋賀県の各市町村にあるフリースクール等をまとめた「学校に行きづらい子どもたちのためのサポートブック」を制作。4児の母でもあり、過去には小学校教諭として約10年勤めその後、県や自治体のスクールソーシャルワーカーとして務めていた。
 井ノ口
井ノ口今回「総集編」ということになっていますが…。



えっ、そうなんですね(笑)。総集編っていっても、私が今やっていることを改めてお話しする機会になればいいですね。
私が代表を務める「おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクト」では、滋賀県内のさまざまなフリースクールや居場所、不登校支援に関する情報をまとめた 冊子(サポートブック) を作っています。
この冊子では、フリースクールの情報だけでなく、病院や親の会、学校との連携方法など、不登校に関する体系的な情報を網羅しています。



実際に拝見しましたが、学校や病院との連携の仕方、教育機会確保法についての説明など、幅広い情報が詰まっていて驚きました。
なぜ、サポートブックを作ろうと思ったんですか?



私は、不登校の親・学校の先生・スクールソーシャルワーカー という三つの立場を経験しました。その中で感じたのが、「情報が整理されていない」という問題です。
困っている保護者は 「どこに相談すればいいかわからない」 ことが多いんです。私自身も、息子の不登校で悩んでいたとき、地域の居場所や支援団体の情報を自分で探すしかありませんでした。
でも実は、「教育機会確保法」 には、自治体がこうした情報を提供する義務があるんですよ。にもかかわらず、自治体が動いていない状況でした。
そこで、自治体に働きかけるだけでなく、「まずは自分たちで冊子を作ってしまおう!」 と考えたんです。
幸いにも、社協(社会福祉協議会)の助成金を活用できたので、資金面の支援を受けながら冊子を作ることができました。



不登校の背景には、発達特性なども関係していることが多いと聞きます。



そうですね。不登校自体は問題ではありませんが、放置すると 「二次障害」 につながることがあります。
たとえば、私の息子も発達特性がありました。学校に行かなかった期間が長くなるうちに 精神的に不安定になり、抑うつや強いイライラを感じるように なったんです。
これは 不登校の子どもたちに起こりうる問題 で、早めに周囲がサポートしないと、精神疾患に移行してしまうこともあります。だからこそ、 学校や地域が連携して「大丈夫だよ」と伝えられる環境を作ることが大切 なんです。



不登校の子どもを支える保護者の負担は、とても大きいですよね。



本当にそうです。私は シングルマザー で、当時は 学校の先生 をしていたのですが、仕事と家庭の両立がどうしても難しくなり、途中で 休職 しました。
担任を途中で交代するのは悔しかったですが、当時の同僚が 「息子さんに向き合うことが最優先」 と言ってくれたおかげで、2ヶ月間しっかりと子どもと向き合う時間を持てました。
働きながら不登校の子どもを支えるのは、本当に大変です。だからこそ、 地域の支援や情報が必要 なんです。



私自身、不登校の経験はないのですが、そういった子どもたちや保護者の力になりたいと思っています。でも、具体的に何をすればいいのか分からなくて……。



身近に不登校の子どもがいたら、まずは 「学校に行かないことを問題視しない」ことが大切 です。
例えば、
「おはよう!」と声をかける
「今日は風が強いね」など、日常の何気ない会話をする
「困っていることない?」とさりげなく聞く
こうした 小さな関わりが、子どもたちの安心感につながります。
もし「もっと支援したい!」と思うなら、 地域に居場所を作る活動 に関わるのもいいですね。例えば「未来の種プロジェクト」では、居場所づくりのアドバイスも行っています。



伊藤さんが目指しているのは、どんな社会ですか?



子どもたちが 「楽しい!」「美味しい!」「よく眠れた!」 と感じられる環境を作ることです。
子どもの権利条約にも 「遊ぶ権利」 があります。にもかかわらず、不登校の子どもたちは 「家にこもり、悩み続ける」 ことが多いんです。
でも、本来 子ども時代は遊ぶもの なんですよね。地域の大人が 「大丈夫だよ」「君はそのままでいいよ」 と言える社会を作りたいです。
サポートブック は、 滋賀県フリースクール等連絡協議会のホームページ で 無料ダウンロード できます。周りの人にもぜひ広めてほしいです。
まとめ
今回は、「学校に行きづらい子どもたちのためのサポートブック」ついてお話を伺いました。1人でも多くの人たちにサポートブックが届きますように。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本編を聞くにはこちら↓