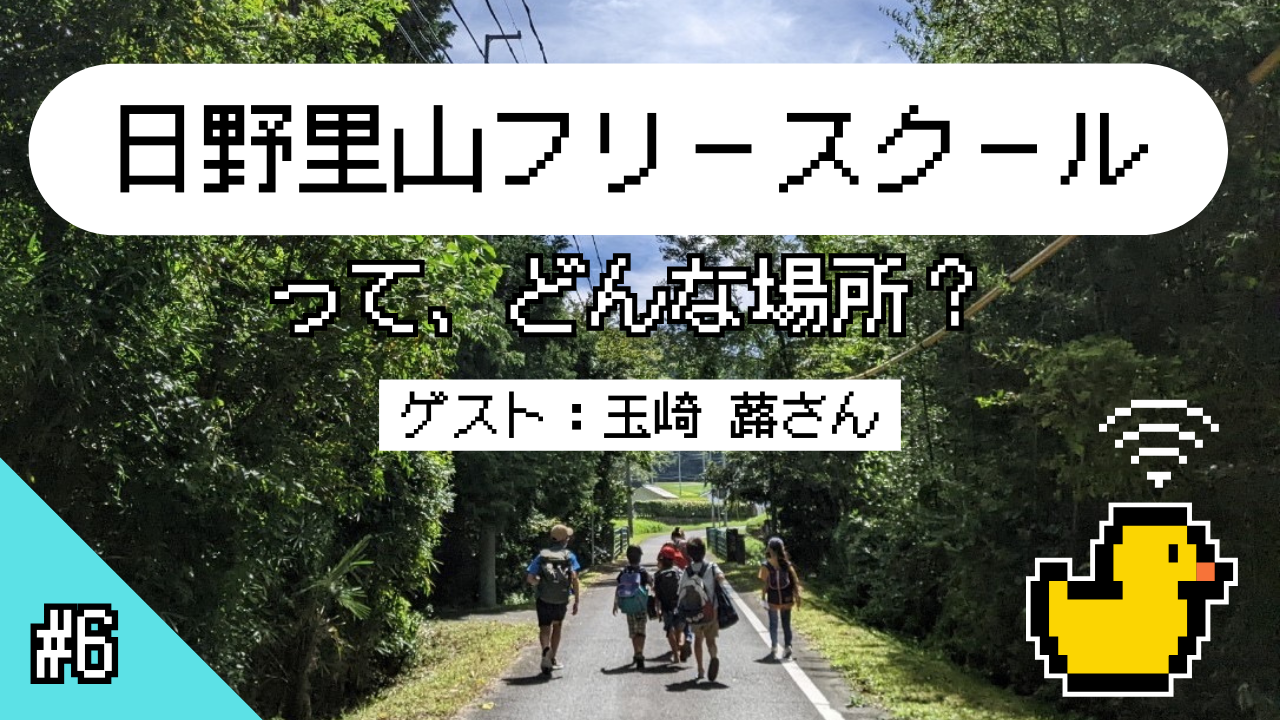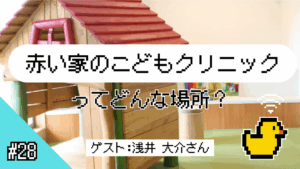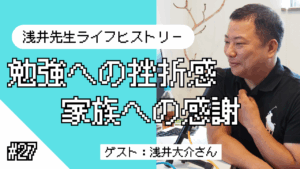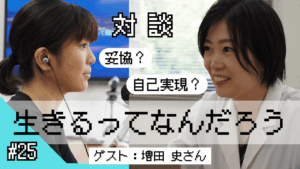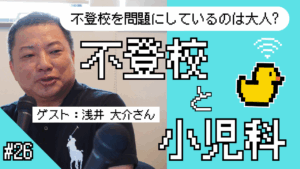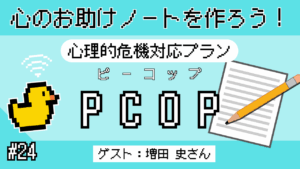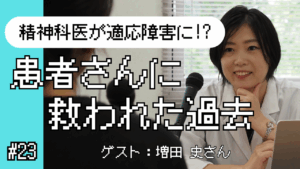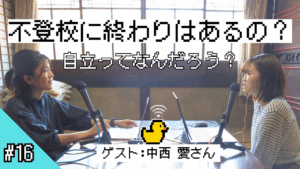本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第6回は、ゲストに日野里山フリースクールスタッフの玉崎 蕗さんをお迎えしております。今回は、日野里山フリースクールが活動を始めたきっかけや、活動において大切にしていることなどをお聞きしています。
玉崎蕗さん
滋賀県甲賀市出身。高校卒業後、進学や就職を選ばず、ボランティアをしたり、 ヨーロッパを旅したり、自由に2年間を過ごす。その後、独学で小学校の教員免許を取得し、2021年に友人とともに日野町にフリースクールを立ち上げる。現在は日野里山フリースクールスタッフ。
【一般社団法人 日野里山フリースクール】
滋賀県日野町の自然豊かな山間にある古民家を中心に毎週月〜金曜日にフリースクールの活動を行われています。対象は小学生〜中学生です。
場所:滋賀県蒲生郡日野町蔵王490
活動:月曜日〜金曜日 9:30~15:00
 井ノ口
井ノ口まず、蕗さんのこれまでのことを聞いてもいいですか?どんなふうに育って、今ここにいるのか…。



はい、私は滋賀県の信楽町で育ちました。自然がいっぱいの場所ですね。高校は大津市の進学校に行ってたんですけど、服装や髪型とか、校則が厳しかったのがすごく苦手で…。



うんうん。わかります。



「なんでこんなに決まりが多いんやろ?」って思ってました。受験のための勉強ばかりなのも違和感があって。「もっと自由に学びたい」「学校以外にも学びの場ってあるんちゃうか」って。



それで、進学や就職の道に進まなかったんですね。



はい。高校卒業後は進学も就職もせず、ドイツにワーキングホリデーに行きました。帰ってきてからは、地元の学校で特別支援員や学童保育の仕事をしながら、独学で小学校の教員免許を取りました。
「うちで預かろか?」から始まったフリースクール



日野里山フリースクールは、どういうきっかけで始まったんですか?



日野里山フリースクールの代表であるえっちゃんの子どもが、小学1年生で学校に行きたがらなくなったんです。
5月、6月くらいから学校に行きたくないっていうようになって…。最初は、えっちゃんが子どもを車に乗せて学校に連れて行こうとしてたんですけど、車に乗せたら、走っている車から飛び降りようとするぐらい、子どもが本気の抵抗をしていたんです。そのうち、その子のお父さんも、「朝起きて毎日を泣きながら始めるっていうのはどうなんや?」っていうふうに思ったらしくて。



それは相当しんどかったですよね…。



そう。でも、2人とも仕事をしていたから、家に1人で置いておくわけにもいかなくて。そうしてるうちに、他にも同じように困ってるお母さんたちがいるとわかって。私もその時、パートのお仕事を週3回ぐらいしかしていなくて、新しいこと始めたいなって思ってた時でした。「そういうことやったら週に2回ぐらい、その子預かれるわ」って言って始まったっていうのがきっかけでした。そこからだんだんだんだん人が集まっていって。「ほな、フリースクールっていう名前にしてみようか」みたいな感じでフリースクールを立ち上げました。



それが、いまのフリースクールにつながっていったんですね。



そうですね。活動を重ねていくうちに、2021年9月に正式に日野里山フリースクールとしてスタートしました。今は、小学生から中学生まで、町内外から、20人ぐらいの子どもたちが入れ替わり立ち替わり、毎日10人から15人ぐらい通ってくれています。
里山の自然とともに生きる



フリースクールの場所、すごく自然が豊かですよね!



はい、里山のど真ん中です。校舎の前にはグラウンドや田んぼ、川、山、竹やぶもあります。月に1回、「里山講座」という、森の専門家自然の専門家の人に来てもらって、季節に合った自然活動をしています。4月は野草を摘んで食べて、5月はお茶摘みをする予定で、そこからは季節によって違うけれど、山に登ったり、竹を切ってきて竹の間にご飯を入れてご飯を炊いたり…そういう活動を月に1回やっています。
あとは、地域の人と関わるっていうことをすごく大切にしているので、
地域の人にボランティアに来てもらって、みんなで絵を描いたり・冬やったら締め縄作りを教えてもらったり…。



いいなあ…。自然のなかで、のびのびと育ってる感じがします。
「大人と子どもが対等」な関係を大切に



蕗ちゃんが、日々の活動のなかで大事にしていることって、どんなことですか?



うーん…さっきも言ったように、日野里山フリースクールは、成り行きで始まってるんですね。だから、「こういう教育メソッドがいいはずや!」とか「こうするのが一番いいだろう」っていうのがあったわけではないんです。ここまで3年近くやってきて、やっと少しずつ確立されてきたかな?っていう感じではあるんですけど…。まずは、やっぱり「ありのままでいられること」と、「大人と子どもが対等であること」ですね。



印象に残ってる出来事とか、ありますか?



あ、運動会のことが印象的でしたね。競技も出る人も子どもたちが決めて、大人も参加するんですけど、「どうしたら全員が楽しめるか」って、自分たちで工夫して。50メートル走では、スタートラインを3本引いて、走る距離を自分で選べるようにしてたんです。年齢や体力に応じて、誰もがチャレンジできる形。あんまり勝敗が分かりやすくないようにっていうのはしてたかな。



面白い!



運動会の明確なルールは1つだけで、それが、「パン食い競争は1人1回」。なぜなら、パン食い競争はパンの数が限られてるから!(笑)



笑笑



あ、あとは、大切にしていることの一つとして「話し合い」っていうのはすごくあるかもしれない。民主的に決めるっていうか、スタッフが決めちゃうんじゃなくて、「スタッフはこう思ってるよ。子どもたちはどう思う?」っていうようなことを積み重ねていってるっていうのはあるんじゃないかなと思います。



それって大人でも難しくないですか?



難しいですね。みんな、乗り気じゃなかったりする時もあります。だけど、自分の意見を言わなかったら自分に不都合がある、っていうのは分かっているので、参加してくれるっていう感じかな。
ほんまに大変やったのは、運動会の種目を決める時。綱引きで、大人対大人の綱引きが見たい子と、大人対子どもの綱引きがやりたい子がいて。
「大人対大人は見てるだけやし絶対やりたくない!」
「大人対子どもは、絶対子どもが負けるから絶対やりたくない!」
とか(笑)。そういうのは見ててめっちゃ面白かったです。



決まり切らないこともありますか?



あります。やっぱり、意固地になっちゃって、譲れなくなってしまったりする子とかもいて。だから、「一旦置いとこかー」とか言う時もありますね。



そこまで、しっかり大人がつき合うのもすごいですね。
まとめ
日野里山フリースクールで過ごす、子どもたちののびのびとした様子が伝わってきます。次回は、勉強や運営事情など、もう少し踏み込んだフリースクールの様子をお聞きしていきます。お楽しみに!