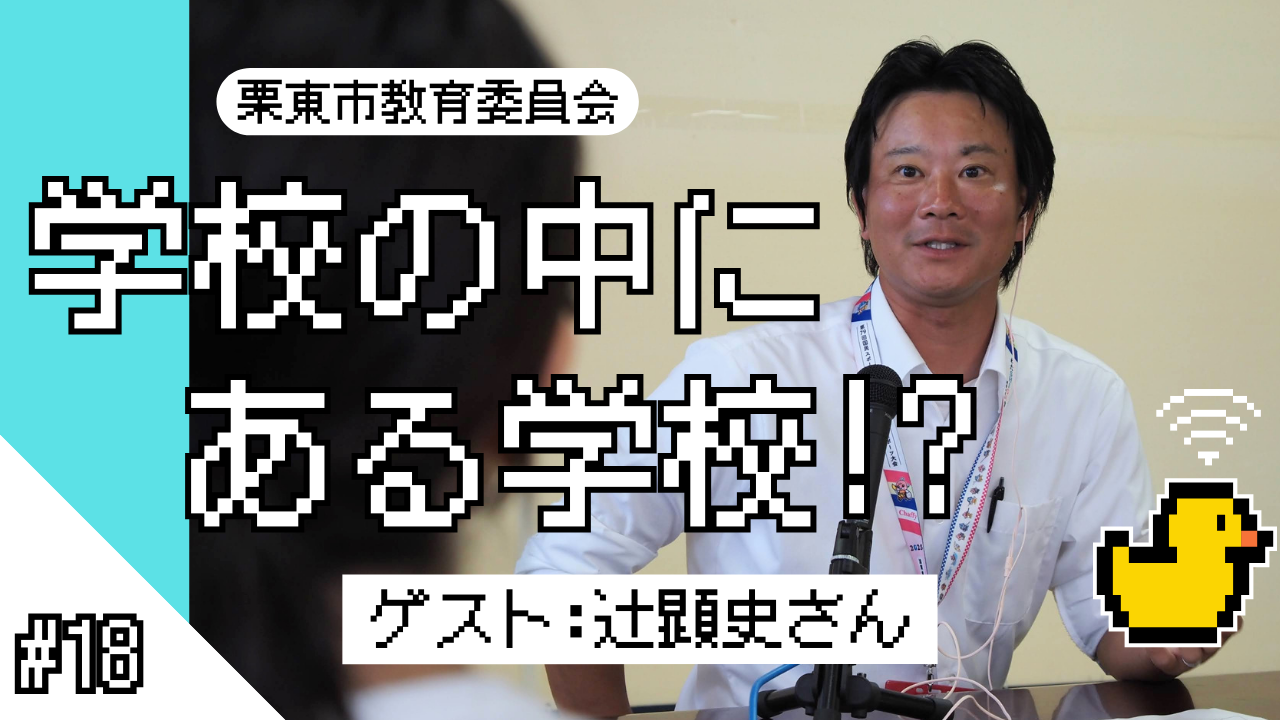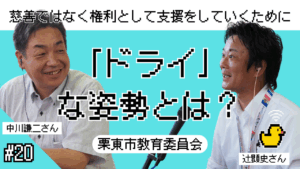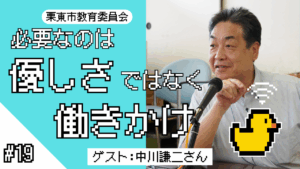本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第18回は、ゲストに栗東市教育委員会の辻顕史さんをお迎えしています。今回は、辻先生が中学校の生徒指導、不登校の担当の先生として働かれていた時のことをメインに、ハーバールームという教室のことをお聞きしていきます。
ハーバールームについて
(1)なぜハーバールームが必要なのか?
子どもたちは、学校で教科の学習や学級活動、行事、あるいは部活など通して、様々なことを学び、成長して いきます。 そして、学校が用意したカリキュラムだけではなく、学校に集まった多くの人との交わりを通して、人格を鍛え、社会の一員として活躍するすべを身につけていきます。 確かに人と共に何かを成し遂げること、人と共感し合うこと、それは”ひとり”では 味わうことのできない大きな感動とよろこびを与えてくれます。
しかし、未熟で思春期にある子ども同士のふれあいは、時には、繊細な心を傷つけることや、かけがえのない個性を排除すること、そして苛酷な努力や変化を教師以上に期待することもあります。一旦傷ついてしまった子どもたちは、まさに荒波の中を航海し続ける一般の船のようです。帆がおれても、船体に穴があいても、航海し続けるしかありません。本校では、そんな子どもたちのために、港(ハーバー:harbor )を用意しました。そこは“ドック”のように大々的な修理をする場所ではありません。しばし、荒波から逃れ、新たな航海に向けて、本来の力を回復させ、新たな航海に向け て態勢を整えるためのささやかな入り江…それがこの「ハーバー・ルーム」なのです。
私たちは、これまでのハーバールームでの働きかけを通じて、子どもたちは、
1.プレッシャーや集団から解放されるだけで、本来の明るさを取り戻すこと、
2.最終的には孤独ではなく、適度な人とのふれあいを求めること、
3.適切な教師の働きかけやルームメイトとのふれあいによって、コミュニケーション能力を高めること、
に気づきました。
(2)ハーバールームの使命と活動
ハーバールームの使命(目的)は、教育活動の一環として、個々の生徒の特性に応じた支援を行い、将来的な自立に向けて力を高めることです。そのために、ハーバールームでは、以下の取り組みを進めます。
1.登校から下校まで、一人ひとりの学校生活を見守ります。
2.個別の学習や活動の場を保障しつつ、ルームメイトのふれあいの機会を設けます。
3.生徒支援部が必要な支援や課題を考え、日々の運営はサボート支援員が行います。
4.全教職員が、利用生徒の教科指導(一日2時間)を分担して受け持ちます。
5.利用生徒と担任の絆をサポートします。
6.利用生徒へのカウンセリングやSSTをSCが行います。
7.いじめや暴力被害にあった子どもの安心安全を守ります
※『栗東市立栗東中学校 校内支援教室「ハーバールーム」 利用のしおり』より抜粋
“生徒指導”の先生が、不登校の担当の先生に!?
 井ノ口
井ノ口第18回のゲストは、栗東市教育委員会の辻顕史さんです。
今回は、辻先生が中学校で生活指導や不登校の支援を担当されていた頃のお話、そして「ハーバールーム」という教室について伺っていきます。辻先生、どうぞよろしくお願いします。



よろしくお願いします。



今日は栗東市役所の一室をお借りして、収録させていただいています。
「教育委員会」と聞くと、正直ちょっとお堅いイメージがあって、最初にご出演のお願いをするときも「引き受けてもらえるかな…」と不安だったんですが、打ち合わせの段階から「いいですよ」と即答してくださって、とても嬉しかったです。お忙しい中、本当にありがとうございます。
それではまず、簡単に自己紹介をお願いします。



はい。あらためまして、栗東市教育委員会 学校教育課 指導主事の辻 顕史です。よろしくお願いします。私は、栗東市内の中学校で11年間勤務していました。
最初の9年間は、生活指導を担当していました。当時の校長先生から「ここを任せたい」と言われて、いわゆる“問題行動”のある生徒たちと日々向き合っていました。その後の2年間は、不登校支援の担当となり、「ハーバールーム」という教室の運営にも関わりました。生徒支援を中心に、不登校の生徒と向き合う時間でした。



ありがとうございます。まず驚いたのは、「生徒指導」には大きく分けて「生活指導」と「生徒支援」がある、という点でした。



そうですね。一般的に「生徒指導」と聞くと、“やんちゃな子の指導”というイメージがあるかもしれませんが、実際は二つの軸があります。
栗東市では「生活指導」と「生徒支援」を両輪として位置づけ、どちらも重要な役割を担っています。



ちなみに、元々は数学の先生だったんですよね?



そうなんです。よく「体育の先生ですか?」と聞かれますけど(笑)、一応中高の数学の教員免許を持っています。
ある生徒には「先生って、数学教えられるんですか?」と本気で聞かれたこともあって…。「警察やと思ってました」とも言われたことがあります。(笑)生活指導の印象が強すぎたんでしょうね。



私も最初は意外でした。てっきり体育系の先生かと…。(笑)
さて、ここからは本題に入っていきます。
私自身、「やんちゃな子」と「不登校の子」って、最初は全然別の問題だと思っていたんです。でも先生は、そこに共通するものがあるとおっしゃっていましたね。



はい。僕も最初は全く別の問題だと思っていました。生活指導の現場では、日々“問題行動”のある生徒たちと関わっていましたし、不登校の支援はまったく別物、むしろ反対だと。でも、実際に不登校の支援を担当してみて、気づいたんです。“出方”は違うけれど、子どもたちが抱えているものはすごく似ているなと。



求めているものが同じ、ということでしょうか?



そうです。「誰かにわかってほしい」「関わってほしい」「期待している」というような気持ちですね。
生活指導の中で子どもたちと関わってきたときと、やっていることはそんなに変わらなかったんです。方法は違えど、子どもとの向き合い方は同じ。
中には、世の中から疎外されていると感じている子もいて、「学校は悪い場所じゃないよ」「大人って、そんなに失望しなくていいんだよ」って伝えたい思いがありました。



先生がそうやって関わってくださると、子どもたちも救われますよね。でも、生活指導から急に不登校支援に任命されたときは、びっくりされたのでは?



正直、めちゃくちゃ驚きました(笑)
周囲の先生も「えっ、辻先生が?」って感じで。でも、そう任命してくれた校長先生の見る目はすごいなとも思いました。
それまでは「学校に来ている子」の対応でしたが、今度は「学校に来ない子」の対応ですから。そこにどう気持ちを向けてもらうか、どう信頼を築くか。すごく葛藤しました。
“学校の中にある学校”、ハーバールームとは



その中で、「ハーバールーム」という教室が出てくるんですね。「ハーバー=港」という意味ですが、どんなお部屋なんでしょうか?



そうですね、学校の中で、子どもたちは人格を形成しながら社会の一員になる力を身につけていきます。ですが、中学生になると思春期の中で、他人との衝突やさまざまな困難に直面します。
そんなときに、すべての子がそれを“飛び越えられる”わけではない。挫折してしまう子もいます。そうした子どもたちが、もう一度立ち直るための“港”のような場所として「ハーバールーム」が生まれました。



フリースクールとはまた違って、「学校の中で、不登校の子どもたちが過ごす部屋」ってすごく珍しい取り組みですよね。



不登校の子がちょっと休憩する部屋や、ちょっと勉強する部屋は、どこの学校にもあると思います。
ハーバールームは、極端に言えば「学校の中にもう一つの学校がある」とイメージしてもらったらいいと思います。
中学校の現場では、やっぱり「人とどう関わるか」とか、「コミュニケーションをとる」っていうことがすごく大切になってくると思うんです。
これは、社会に出たときにも同じことが言えるんじゃないかなと。勉強だけじゃないよっていう部分ですね。たとえば、学級があれば、行事を通してとか、日常の中で自然と「人とつながる力」がついてくると思うんですけど、でも、もし教室に行けない子がいた場合、その「人とつながる力」をどうやって育んでいけるのか?というのは、すごく大きなテーマだと感じています。
だから、私たちは「学級」というイメージではなくて、もうひとつの「学校」という形で、別の部屋を用意しているんです。とはいえ、そこも同じ学校の中にあるので、実際に授業もしますし、もし可能であれば体育の授業にも参加してもらったり、大会に出ることもあるんですよ。そうやって、できる範囲で「学校の一員」としての体験をしてもらっています。



学校の先生って、勉強を教える人っていうイメージがあったので、先生から「勉強だけじゃない」という言葉が出るのは意外でした。



正直なところ、現場の先生たちは本当に多忙です。担任を持っていたり、学年主任をしていたりする中で、何百人という規模の生徒と関わるわけですから、一人ひとりに丁寧に関わるのは、どうしても難しくなってしまう部分があります。1クラス35人ほどの子どもたちを見るというのは、それだけでも大変なことです。
もちろん、どの先生も「関わりたい」「助けたい」という思いは持っています。ただ、物理的に手が回らない状況もあって、そんなときに“支援主任”という立場の私のような存在が、教室に入れない子どもたちのもう一人の“担任”のような立場として、サポートできる体制があるのは大きいと思います。
実際に、担当している子がハーバールームに来た日には、授業後などに担任の先生が「今日は来てましたか?」「元気にしてましたか?」と声をかけてくれることもあります。「見捨ててる」のではなくて、「関わりたいけれど、今はこの形でしかできない」と感じてくれているんだなと、そういうやりとりの中で分かるんです。



そうですね。先生だからといって、スーパーマンじゃないですよね。不登校の問題は担任の先生に押し付けるようなことではなくて、その組織の構造で解決できる部分もあるかも知れないです。



1人で抱えていたら、今の複雑化してる学校の中では対応はできないと思います。 やっぱり組織っていうのはすごく大事だなと思います。



ハーバールームでの過ごし方についてもお聞きしたいです。子どもたちはハーバールームでどんな風に過ごすんですか?



登校時間は、基本的に子ども自身が決めます。
普通の学校なら朝8時半から朝の会がありますが、ここでは「明日は10時に登校します」といったように、自分で申告してもらう形です。
「10時に行きたい」「午後から行きたい」など、それぞれのペースに合わせて登校してもらいます。そして、何時に来たかは、記録用のファイルに毎回記入しています。
1日の中で、子どもたちが比較的多く集まりやすい3・4時間目や4・5時間目あたりに、週2回、2時間程度の授業を設定しています。授業は私ではなく、各教科の先生に来ていただいて行っています。これは年度初めの職員会議で確認をとり、担任の先生方に担当してもらうこともあります。
週に1回は、ほぼすべての教科の先生がこの部屋に来て、子どもたちに授業をしてくれています。ただし、全員が授業を受けるわけではありません。「勉強はしたくない」という子もいますから、そこは無理強いはしていません。
そんなときは、一緒にトランプやカードゲームをしてもらったり、オセロやボードゲームを通じて、コミュニケーションをとったりしています。ゲームの中でも、子ども同士のやりとりが生まれるんですよね。
もし子どもたちの表情や様子が少し気になるときには、支援員や私が声をかけて、別室で話を聞くこともあります。また、週に1回ほど、スクールカウンセラーが来てくれる時間もありますし、スクールソーシャルワーカーの方にも来ていただくことがあります。
「来て何かしてもらう」というよりも、「子どものことを一緒に考える」存在として関わってもらっているんです。生活面や学習面を含めて、子どもたちに必要なケアを第一に考えながら、日々の支援を行っています。
1日の終わりには、子どもが今日の記録を書き残すファイルがあります。どんなふうに過ごしたかを自分の言葉で書いてもらい、その下の欄には担任の先生へのメッセージを書くスペースがあります。まるで“交換日記”のような形ですね。
放課後、そのファイルを担任の先生に届けてコメントをもらい、私がまた預かって次の日に渡す、という流れで日々を過ごしています。そうやって、教室にはいないけれど、担任の先生ともつながっていけるような工夫をしています。



ハーバールームの「申し合わせシート」を事前に拝見しましたが、かなり細かく打ち合わせがされていると感じました。
まず、ハーバールームに入るか、審査のようなものがあり、それが通った後に宿題プリントが必要かどうかなどの話し合いが行われています。
学校と子ども、そして保護者との連携が非常に細かく取られていると感じますが、実際にはどのようにハーバールームを運営されているのでしょうか。



ハーバールームは、誰でも来れるというわけではありません。
ハーバールームには、支援員などのサポートスタッフもいます。生徒の人数が多ければ良いというものではなく、生徒一人ひとりにどれだけ手厚く支援ができるかを重視しています。そのため、ハーバールームのルールを全て理解してもらった上で、子どもたちや保護者の方に参加してもらっています。
時には、問題行動を起こす子もいました。その時は、「次の日から来させへんで」と言ったことも実際にあります。実際は来るんですけどね(笑)
ハーバールームの定員は、最大でも15人以下、最も理想的なのは8人と言われていました。ただ、当時の中学校ではニーズが非常に高かったため、15人くらいで対応していました。
また、「アセスメント」と呼ばれる、教室復帰の可能性を判断するプロセスを重視していました。



本当にしっかりと制度があるんですね!



社会的自立の力がついたなと判断された子どもは、教室に戻っていきます。教室とハーバールームの併用が、途中から成り立つんですね。そこが、この学校の強みでもあると思います。
中には、小学校時代の友達に「俺、今ハーバールームにいるねん」って自分から話す子もいます。最初は「内緒にしておきたい」っていう子もいますが、だんだんとオープンになっていく子もいますね。
昼休みに友達と話しに行く姿を見ると、やっぱり感動します。ここに来たときは全く話さなかった子が、少しずつ力をつけて、半年ぐらい経つと教室に行けるようになったり、体育祭や学校行事を見に行ったりするようになるんです。



やっぱり、「登校できている」っていうだけで、その子の自身につながるのかもしれませんね。



そうですね。ハーバールームが「誰にもわからないような場所にあるのか」と言われると、実はそうではないんです。普通に学校の玄関から、職員用の通路を通って入る場所にあります。
はい。そこには下駄箱があって、そこに靴を入れて。通るときには、事務職員の方に「おはようございます」と挨拶することもあります。学校の中でも、特別な別の場所にあるわけじゃなくて、ちゃんと「学校の一部」として存在しているんですね。
そういう感覚、雰囲気のようなものを、みなさんにも少し感じ取ってもらえたら嬉しいなと思っています。
今、生徒たちに伝えたいこと



最後の話題にいきたいと思います。教育委員会に入られた今、生徒たちに対して、思ってらっしゃることがあったらお聞きしたいです。



そうですね。一旦現場から離れて、教育委員会という立場になって、改めて子どもたちへの思いを感じることがありました。やっぱり、以前見ていた子どもたちの多くが高校に進学したんですね。通信制の高校に行った子もいれば、公立高校に進んだ子もいます。
どこか心の中で、今もその子たちのことが気になっています。最近も、高校を辞めていないと聞いていて、「ああ、3年間通い続けてくれているんだな」と思うと、やっぱりホッとしますし、できれば無事に卒業してほしいという気持ちが強いです。
中学校時代には、一度は学校に足が向かなくなった時期があった。その中で、ハーバールームという場所を通じて、何かしらの思いを育くんでくれたのかなと思っています。
でも、正直「どこまでできたのかな」という思いもあります。それは、やっぱり子どもにしかわからない部分かなとも思っています。今はただ、これからの子どもたちの姿を見ていきたい。開設から3年間経ちましたが、今思うのは、高校をしっかり卒業して、その後、働いたり自分の道を歩んだりしていけたら、「やってきたことは間違っていなかったのかな」と思えるような気がするんです。
私が子どもたちに一番願っているのは、「社会的に自立してほしい」ということ。そして、「自分で生きていってほしい」。その中で信頼できる人が一人でもできたら、「助けて」って言ってくれていい。人に頼る力って、とても大切だと思うんです。大人になってからも、人とのつながりって本当に大事ですから。
頼る力と、自分で自立していく力。その両方を持って、これから社会に出ていってほしい。そしてこの先、どんな形であれ、仕事をしてお金を稼いで、もしかしたら結婚して……。もちろん、結婚がすべてではありませんが、「自分は社会の中で幸せだな」と、そう思えるようになってくれたら、本当に嬉しいですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
初対面のときから、辻先生は本当に気さくに話してくださる方で、思わず「今、教育委員会にいるんだったよな」と忘れてしまいそうになるほどでした。でもやっぱり、お話の一つひとつにポイントがあり、とても説得力があるなあと感じました。
さて、次回は、ハーバールームを立ち上げた先生のひとり、中川 謙二さんにご登場いただきます。ハーバールームがどうやってできたのか、その背景について、詳しくお話を伺っていきます。