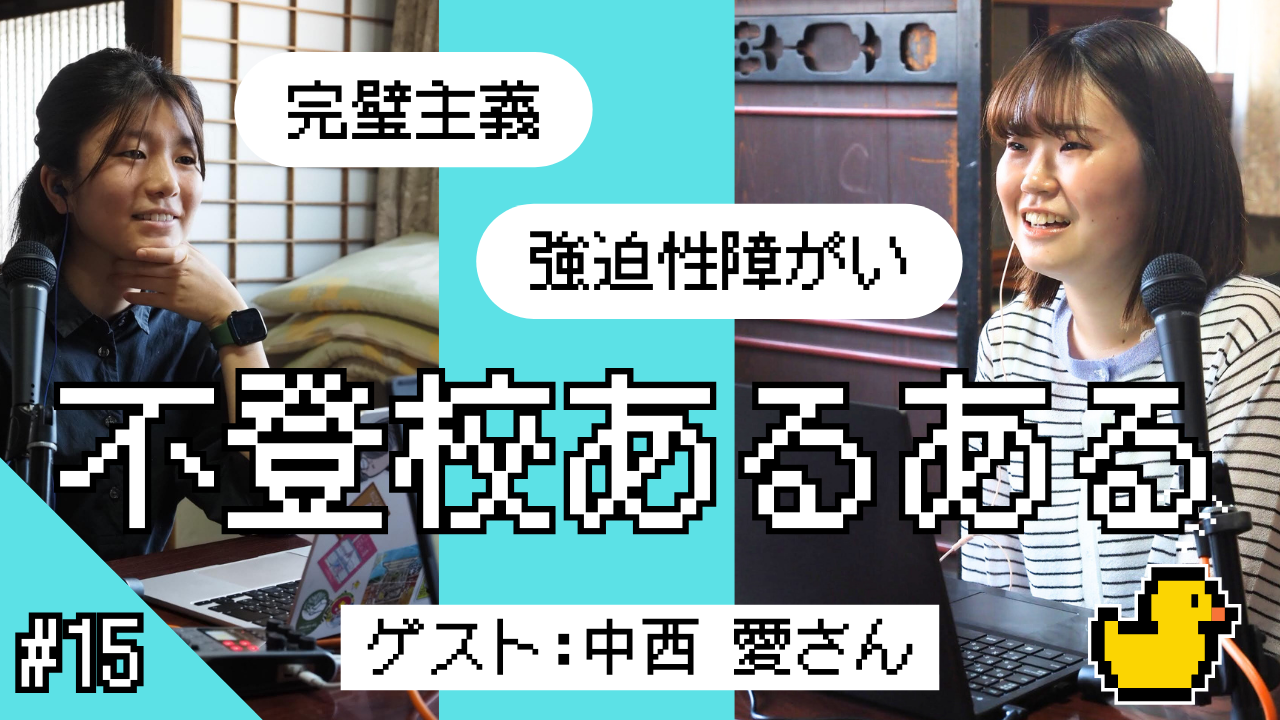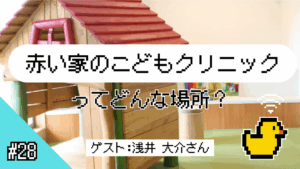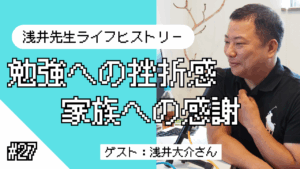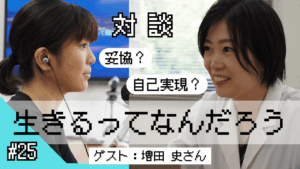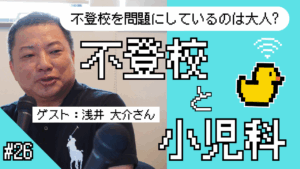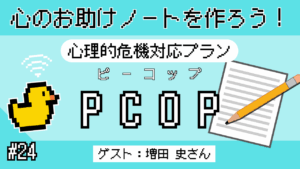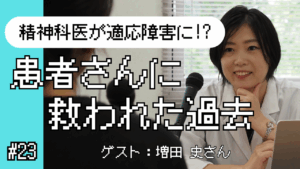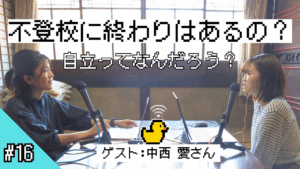本記事は、音声配信『学校行かないカモラジオ』の内容をもとに抜粋・編集しています。内容や状況は配信当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
第15回は、前回に引き続きゲストに滋賀県野洲市で活動する、心の居場所~toiro~の中西愛さんをお迎えしています。今回は、愛さんが高校生だった時のエピソードから、不登校に関するキーワードを挙げて、不登校の子が陥りがちなこととその向き合い方についてお聞きしていきます。
中西 愛さん
学校でのトラウマ的経験や、音や匂いに敏感で、にぎやかな場所や集団行動が苦手な自身の特徴によって、小学校1年生から学校に通いづらくなる。その後、強迫性障がいなどと向き合いながら、約10年間の不登校を経験。現在は自身の不登校経験にもとづき滋賀県野洲市で心の居場所〜toiro〜を運営。
📌インスタグラムはこちら
📌noteはこちら
~心の居場所~toiro
頑張らなくてもいい、ただただ心の元気を取り戻すための場所、でも、元気が出てきたら程よい距離感で背中を押してくれる人がいる。という愛さん自身が必要としていた場所を形にした居場所。時間はかかるかもしれないけれど、一歩ずつでも、いま困っている子たちのために伝えていければいいな、という思いで、月に1~2回開催している。いつかは、不登校の子どもも親御さんも、周りにいる人たちも支援者も、み〜んなの心が楽になる世の中になるように、アプローチができたらいいなと考えている。
高校生に進学した時のエピソード
 井ノ口
井ノ口今回は、不登校の子どもたちが陥りやすい――と言ったらいいでしょうか、ある種の「気持ち」や「生活のルーティン」について取り上げながら、それがどんなふうにしんどかったのか、あるいは、どうやってそれを乗り越えてきたのか、そんなことをお聞きしていけたらと思っています。まずは、愛さんが高校生だったときのエピソードをもとに、不登校に関するいくつかのキーワードを挙げながら、お話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。



よろしくお願いします。



今回は、高校生の時のエピソードからお聞きしていこうと思います。愛ちゃんは、実は全日制の高校に入学されたんですよね。そして入学直後は毎日通っていたそうですね?



約2ヶ月くらいは、今まで毎日学校に行けなかった私が、逆に2ヶ月間ずっと休まずに通いました。本当に「優等生」を演じまくってたって感じで(笑)、とりあえず学校にはちゃんと行ってました。
自分で「行く」って決めたことやったから、とにかくやり遂げようと思って、必死に頑張ってたんです。その中にはやっぱり、「学校に行かないとダメだ」っていう思いが自分の中にあって。「本当に自分が学校に行けるのか」って、それを試してみたかった、見てみたかった、っていう気持ちもあったと思います。
当時の私は、ほんまに完璧主義で。全部ちゃんとしていたかった。たしか、そのとき…あれ何て言うんやったっけ、学級委員?それも「やります」って自分から言って。結局その2ヶ月しか学校行ってなかったんやけど、その最初の期間はちゃんとやり遂げました。
それくらい、「私は完璧でいたい」「学校に馴染んでる私は正しい」って、強く思ってたんだと思います。今思えば、自分自身に偏見を持ってたのかもしれません。「自分はこうでなければいけない」って、自分をがんじがらめにしていたような気がします。



不登校って、「怠けてる」とか「真面目じゃない」って誤解されがちだけど、実際はその逆のことが多いですよね。



本当にそう思います。その2ヶ月が経ったときに、やっぱり限界が来てしまって…。一気にしんどくなって、学校に行けなくなっちゃいました。
最初は「今日は1日だけ休もう」って思って。ちょうどテスト前やったんで、「とりあえずテストは受けに行こう」って自分に言い聞かせて、なんとか行って、テストも受けたんです。でも、もうそのあとがボロボロでした。
テストを受けたあとの反動で、心も体もガタガタになって、「あ、もう無理や…」って。1回行けなくなると、授業のことも全然思い出せへんし、何をどうしたらいいか分からなくなって、そこからは完全に「行かない」という選択をしました。
だから、友達からは「なんで来てへんの?」とか、「最近どうしたん?」って、LINEが届いたりもしたけど、それにさえ返す元気がないくらい、もう本当に疲れ果ててしまってました。
強迫性障がいとの付き合い方



その後、愛ちゃんは「強迫性障がい」と診断されたんですよね?



はい。ほんまに、もう…とりあえず「脅迫ルーティン」っていうか、毎日同じことを同じようにこなさないと不安で仕方なかったんです。それがないと、自分の気持ちが保てなくて。それと「不潔恐怖」っていうか、汚いものがすごく怖くなってしまって。でも、それが本当に汚いのかって言われたら、実際はそうじゃなくて…。
自分の中で「これは汚い」って決めつけてしまって、その思いがどんどん大きくなって、不安が膨らんでいく、っていうことが起きてたんです。
お弁当箱も、「拭いてからじゃないと持ち出せない」とか、そういうことがいくつもありました。でも、そのルーティンが毎日、少しずつ崩れていくんです。
そうやって、朝、学校に行けなくなることもありました。
自分の中のルーティンがうまく収まらないから、行けない。
とにかく、不安なんです。
「ちゃんと全部きれいにした」って自分では思っても、ちょっと風がふわっと吹いただけで、「あ、汚くなった…」ってなったりして。
もう、自分でもその不安をコントロールできなくなっていました。



それも「完璧じゃないとダメ」という思いとつながっていたんでしょうか。



そう思います。安心が足りていないと、「ま、いっか」ができない。多分人間って、実は、「ま、いっか」っていうのを日常の中でいっぱいやっているんです。でも、安心が心の中にないと、「ま、いっか」で飛ばせない。



強迫性障がいがひどくなった時期には、「誰かに見られている」と思ってしまうこともあったそうですね。



そう、家の中にいるのに、「誰かが外から見てる」って思ってしまったりして…。
でも、そういう――「強迫観念」っていうんですかね――
そういう不安が、勝手に頭の中に浮かんできてしまうんです。
「なんでそんなこと思いつくん?」って、今になって思えば不思議やけど、そのときは、どうしようもなくて。
もう不安が大きくなりすぎて、病院に駆け込む、みたいな状態でした。
で、多分こういうふうになったのって、不登校がきっかけで、ある意味「二次障がい」みたいな形で出てきたんやと思います。
でも、これって実はけっこう「あるある」で、SNSで相談が来たりすると、「私もそうです」って言ってくれる人が多くて、「ああ、自分だけじゃないんやな」って思えたりもして。やっぱり根本には、「不安」があるんですよね。
ひとつ、よく覚えてるエピソードがあるんですけど、小学校1年生ぐらいのときの先生が、「字をきれいに書きなさい」って、すごく厳しい先生で。ちょっとでも汚いと、めっちゃ怒られる。それで、私はどんどん「ちゃんと書かなきゃ」「綺麗に書かなきゃ」って思うようになって、宿題でも何回も書き直して、納得できるまでずっと書き続けるようになってしまいました。実際には、そんなに怒られへんぐらいの字でも、「先生は怒る」って思い込んでるから、「ここまできれいにしないとダメ」って、自分でどんどんハードルを上げてしまって。そうなると、1文字書くのに5分くらいかかってしまって、宿題も全然終わらない。
そういうのが積み重なって、「強迫性障がい」っていう病名がつくくらい、しんどくなってしまいました。



それは本当に辛かったですね…。



めっちゃ辛いです。しんどいけどその時はもうそれが普通やと思っちゃってるから、「これをしないと自分は生きてられへん」ぐらいの気持ちでいましたね。



私は、学校には普通に行けてたし、「強迫性障がい」っていう名前がついてたわけじゃないけど、すごく思い当たることがあるんです。それは、授業中に先生が答えを言って、みんなで自分のプリントに「シュッ」て丸つけしていく――
そういう場面があったんですけど、その「シュッ」っていう音が、もう本当に怖くて。で、自分が間違ってたら、それだけで涙が出るくらい悲しくなってしまって。なんかもう、自分がダメな気がして、すごく落ち込んでしまってました。今思えば、「間違ってたな〜、直せばいいやん」って思えるんですけど、当時は本当に、「もうあかんわ」「人生終わった」ぐらいの気持ちになってしまってて。
なんか、そういう気持ちの延長線上に、強迫性障がいみたいなものがあるのかなあって、今になって思います。



自分のしんどさが「本当にしんどいことなのかどうか」がわからなくて、病院に行ったときに、「やっぱりこれは甘えなんじゃないか」って思って、先生にそう聞いたんです。
そしたら、先生が「その人がしんどいと感じているとか、生活に支障が出ている時点で、それはもう診断がつけられる状態だから、あなたが悪いわけじゃないよ」って言ってくれて。その言葉が、すごくホッとする言葉でした。
私、当時はまだすごく小さかったんですけど、先生はすごくやさしい言葉で、わかりやすく噛み砕いて伝えてくれて…。本当に安心したのを覚えています。その一言だけで、帰りの車の中で感じていた強迫がスッと減ったんです。「後ろから誰かが追いかけてくる」とか、そういう感覚もなくなって。ほんまに、不安と安心って綱引きみたいなもので、ちょっとでも安心できたら、不安ってスッと引いていくんやなって実感しました。



今は、強迫性障がいとはどんなふうに向き合っているんですか?



私自身、強迫性障がいが「完全に治った」わけではないけど、少しずつ変わってきたとは思っています。
高校の時にすごく悪化して、主治医も変わって、京都の大きい病院で専門医にかかりました。今もその先生に診てもらってるんですけど、
「治るというより、上手く付き合っていけるようになることが目標やね」って言われてて。
たぶん、強迫ってゼロにはならないと思います。考え方のクセや、トラウマの経験も関係してるから、一生つきあっていくものやと思ってるけど、
それでも「うまく付き合えたらいいよね」って感じで、今は落ち着いています。
最初のころは「曝露反応妨害法」っていう治療を受けたこともあります。
わざと汚いと思ってるものを触ったり、不安に立ち向かう方法です。
でも、私にはそれが合わなくて、診察の日には診察室に入れないぐらい嫌になってしまって、先生に「もうこれはやめよう」って言ってもらいました。
そこからは「生活を安定させることを大事にしよう」って治療方針に変わって、無理に不安と戦うんじゃなくて、安心できることを探す方に変えてくれたんです。
それが私にはすごく合っていて。
「強迫外来」に通ってたけど、先生との会話はまったく強迫の話じゃなくて、「家で何してるん?」「ゲームとかしてる?」って聞かれたり「私、こんなお菓子作ってんけど、あんたも作ってみる?」って言われたり。
そういうたわいもない会話の積み重ねが、安心に繋がって、少しずつ、少しずつ「うまく付き合える感覚」が育っていったんだと思います。
正直、まだ強迫性障がいは、全然あります。
でも、前みたいに「誰が見てもわかる」ような強迫は、だいぶ減ってきました。家の中では今もあるけど、外から見てわかるほどではなくなったかな。だから、今は「うまく付き合いながら調整中」っていう感じです。焦らず、自分のペースでやっていけたらいいなって思ってます。
勉強はどうしてたの?



次に、学校に行けなくなってからのこと、勉強はどうしていたのか、お聞きしてもいいですか?



そうですね…。
私は「家でめっちゃ勉強してました!」って感じではなくて。
ただ、私は「勉強しろ」って言われたらやるタイプではあるんです。
得意でも好きでもないけど、やれって言われたらやる。でも、本当にしんどい時は、「勉強」っていう言葉すら嫌で、もう立ち向かうことができませんでした。でも家族が「もう勉強せんでいいよ」って言ってくれてたので、その時期は本当に勉強してませんでした。
ただ、「高校に入りたい」って自分で決めたときから、勝手にやり始めたんです。自分で決めたことだったから。やるってなったら、やるんです。
小学生の頃とかも、たぶん人よりは全然できてなかったと思います。
今でも小学生の問題、解ける気しない(笑)。抜けてるとこも多くて。でも、「今から取り戻せばいいか」って思ってます。



勉強ができないほど辛い時、家ではどんなふうに過ごしてたんですか?



もう、とにかく寝てました。ずーっと寝てて、朝、みんなが学校に行く時間に寝て、夕方みんなが帰ってくるくらいに起きる、みたいな。
それしかできなかったんですよ。
本当に、それが精一杯。「今の自分にはこれしかできひん」っていう感じでした。だからやっぱり、勉強って安心がないとできないなって。不安が強いと、どうしても勉強に向かえなくて。



でも、それでも高校には進学したって、すごいですね。



うん、進学しました。私、自分のペースでやるのがすごく合ってて、逆に学校の授業だと、暇すぎたり、ついていけなかったりって差があるんです。
中3のときは、夜中に勉強してました。夜って、みんなが寝てて静かで、自分の中で「嫌なことが起きたことがない時間」って思ってて、不思議と安心できるんです。だから、夜中にひとりで勉強してました。「勉強がしたい」という気持ちはあったので、安心できる時間を選んでやってました。



それってすごい。自分で夜中に勉強って、尊敬する…。



ありがとうございます(笑)。
でも、それが「楽しい」になってたからできたんやと思います。効率よくやるにはどうしたらいいかって考えるのが楽しくて。
あとは、完璧主義っていうのもあって、「やるって決めたらやりきる」っていう自分ルールがあったから、それを勉強に活かしてました。



完璧主義がプラスに働いたんですね。



そうそう。たぶん勉強とか受験の面では、いい方向にいったと思います。でも、不安が強くなった時には、それがしんどさにもつながってしまって…。だから完璧主義って、良い面もあれば、しんどくなる面もあるなって思います。



勉強を支えてくれた出来事って、ありましたか?



ありました。別室にいたときに、信頼できる数学の先生がふらっと来てくれて、「ちょっとこれ、やってみひん?」って声をかけてくれたんです。
30分くらい一緒に問題を解いてくれて、それだけでテスト、半分くらい取れたんです。それがすごい自信になって、「あ、私できるんや」って思えて。それからは、その先生にちょこちょこ質問しに行って、教えてもらって。
「学校なんか行ってられへん」って思いながら、必要なときだけピュッと行って、パッと帰る、みたいなことをしてました。



それ、すごい大事な話ですね。信頼できる大人と安心できる時間。



ほんまにそうなんです。小さなことかもしれへんけど、私にとってはそれがすごく大きな安心になったんです。
「できるかも」っていう自信って、誰かのちょっとした声かけとか、時間の中に生まれるんやなって思いました。
振り返り
いかがでしたでしょうか?愛さんのお話を聞いて、「不登校の子は特別」というイメージが崩れました。「自分にも思い当たるな」と感じる方も多いのではないでしょうか。次回は、学校の成績や制度の話、不登校の「終わり」や「自立」についても深掘りしていきます。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。