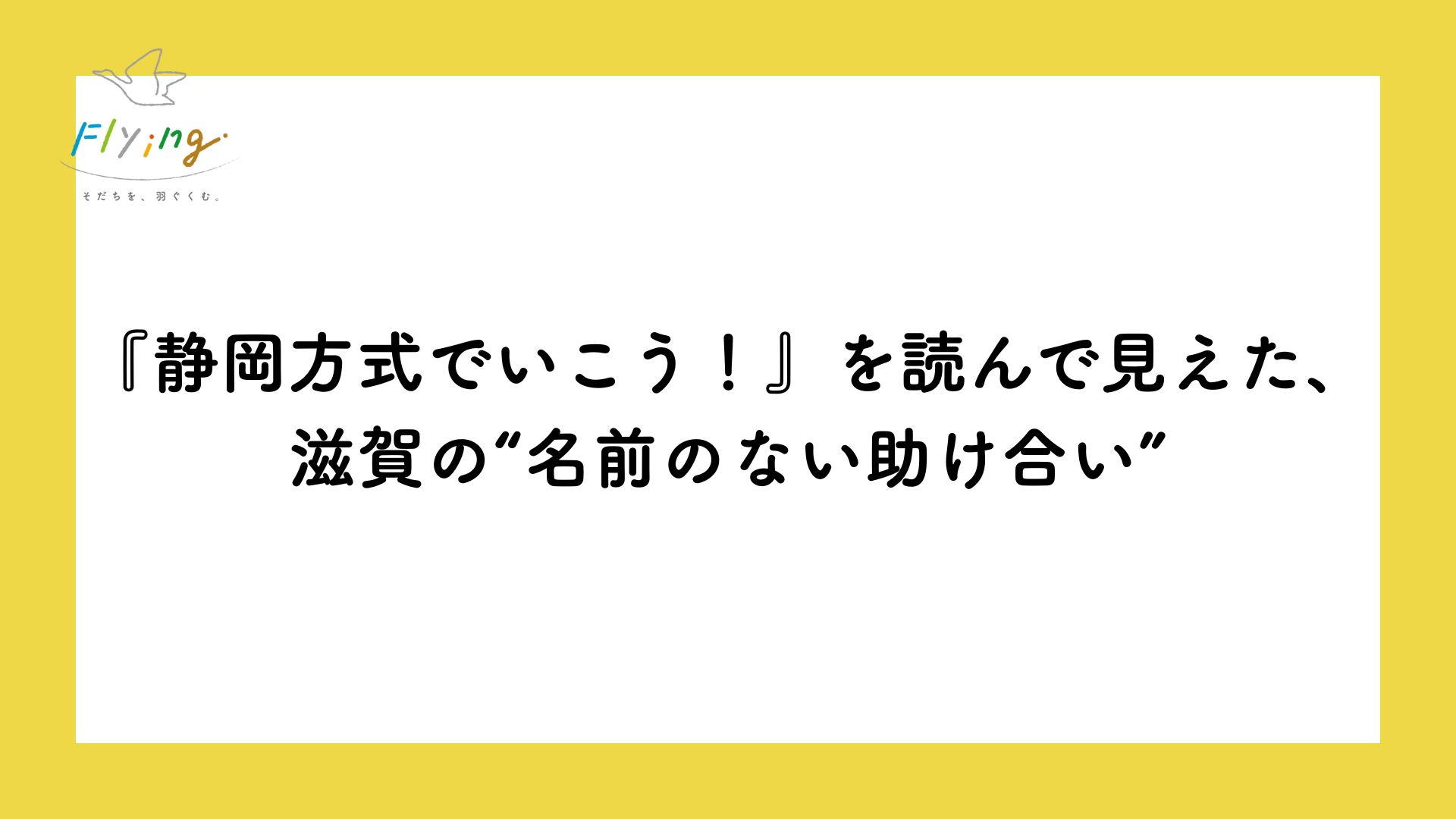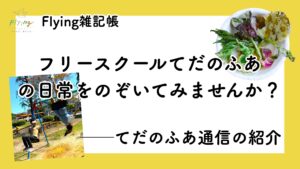皆さんは、「静岡方式」でいこう!という本をご存知でしょうか?
静岡方式とは、静岡県のNPO法人「青少年就労支援ネットワーク静岡」を中心に広がった、地域ぐるみの就労・生活支援モデルです。もともとは「働きたいが働けない」若者を対象に始まりましたが、いまや地域社会そのものを編み直すプロジェクトへと発展しています。
….とchat gptは教えてくれましたが、ん〜、難しい。
私は碧いびわ湖の根木山さんにこの本を勧めてもらうまでは、「静岡方式」という言葉も、本の存在も知りませんでした。今回は、根木山さんからの依頼もあって、「静岡方式とはどんなものか」を、本を読みながら私なりにまとめてみることにしました。
すごいぞ静岡方式!ここがユニーク3選
支援の始まりは、就労!?
静岡方式にとって、就労は目的ではなく、地域とつながる入り口。
北条さんは現在五〇代前半。シングルマザーで四〇代後半まで働きづめだった。さいわいクレーン運転資格を持っていたので、肉体労働の現場で働きながら、子どもを大学まで出した。今、子どもは就職して名古屋に住んでいる。〜中略〜働きたいが、五〇代ではなかなか求人もなく、すっかり困り果て市役所の福祉課に相談に行ったところ、ここ(沼津市自立相談支援センター)をすすめられてやって来た。
だいたいのことを話し終えたころ、突然、またちがう女性に声をかけられた。といっても、声をかけられたのは、北条さんの話し相手になってくれているボランティア・サポーターのほうだ。
「あれ?〇〇さん、どうしたの?」
「いや、今、北条さんの話聞いてたんだけど、一日四、五時間の仕事ってどこかにないかな?」
「北条さん、どんな仕事がしたいの?」
「肉体労働は苦にならないんだけど、体の調子もあるし、無理かなぁ」
「やってみたいことはある?」
「接客の仕事とか飲食店とか、やったことないけどやってみたい」
「ねえねぇ、それじゃあ、あそこがいいんじゃない?堤さんが前に言ってたカフェ」
「それ、いいかも。女性のスタッフがほしいって言ってたみたいだからね」
相手の女性二人は意気投合したふうで、「堤さあん、ねぇ、ちょっとちょっと」とセンターのスペース内に向かって呼びかける。
「なになに?」
出てきたのはセンターのスタッフ、堤 絵理である。しかし、名札も下げていない堤がまさかセンターのスタッフであるとは、北条さんにはわからない。
「あ、いいね、いいね。今、電話してみよう」
事情を聞いた堤は、さっそく二人が言っていたカフェとやらに電話をかける。
「知り合いの人が接客の仕事したいって言ってるんだけど・・・・・・」
堤は電話口でそう言った。いきなり「知り合い」呼ばわりされたが、それもいやではなかった。
「今から行こう!えっとお名前は?」
電話を終えた堤は言う。名前も知らない人間を影躇なく知人扱いし、紹介したわけだ。「この人たちはいったいなんなのだろう?」と思いながら、北条さんはセンターについてわずか三〇分足らずの間に、就職を決めていた。
カフェの店主もやはりボランティア・サポーターの一員らしく、北条さんをひと目見て即決。「大変だったねぇ」と、これまた同級生のようなノリで北条さんをねぎらってくれた。
津富宏, 青少年就労支援ネットワーク静岡 編著. 生活困窮者自立支援も「静岡方式」で行こう!! 2, クリエイツかもがわ, 2017.11. pp8-12
引きこもりや貧困の支援において、就労はゴールであることが多いですが、静岡方式では、まず「本人には働く力がある」と信じ、「まず働いてみて、そこで力を伸ばす」という考え方を大事にしています。
また、求人サイトを探して面接を重ねる…というやり方ではなく、地縁(つながり)を頼って仕事につなぐのが基本です。相談があれば、数日以内に知り合いを頼って「とりあえず働ける場所」を見つけます。
そして大事なのは、その仕事にずっと定着しなくてもいいということ。静岡方式は「試行錯誤」を当たり前のプロセスと考えていて、もし合わなければ次の仕事へ、さらにその次へ…と、転職を重ねながら少しずつ働き方に慣れていけばいい、という考え方なのです。
スタッフはみんなボランティア
静岡方式を支えているのは、ほとんどがボランティアのスタッフです。
お金をもらっている人も「職員」とは呼ばず、「有償ボランティア」と呼ぶそうです。
そして驚くべきは、その人数。ボランティア・サポーターは、静岡県全体で2500人(2025年1月時点)もいます。
さらに、ボランティアがボランティアを誘うという連鎖が起こり、仲間はどんどん増え続けているのだとか。
ボランティアと有償ボランティアの違い
ボランティア
- 基本は完全無償
- 「やりたいからやる」「関わりたいから関わる」という自主的な活動
- 就労支援のサポートや、イベントの手伝い、若者の話し相手など、できる範囲で自由に参加
有償ボランティア
- NPOが行政から受託した事業に伴い、NPOに雇用されたボランティアサポーター
- 役割はボランティアのコーディネーターのような存在
- 例:
- ボランティアの登録や管理
- 誰がどんな得意分野(ストレングス)を持っているか把握
- 新しいボランティアを誘ったり、活動をつなぐ
なぜボランティアなのに、人が集まるの?
正直、私がいちばん疑問に思ったのはここでした。
「ただでさえ仕事や家庭の事情で忙しいのに、さらにボランティアで人助けなんて…どうして?」
静岡方式も、最初からボランティアが豊富にいたわけではないようです
有賞ボランティアは、訪問した会社の社長さん、支援で連携してくれるほかの団体の人、応援してくれる行政の人たちに声をかけまくった。
「ボランティア・サポーターに登録してくれませんか?」
しかし、それを聞いた相手は、決まってこう言った。
「そんなに大変なことはとてもできない。無理だよ」
当初、米山がイメージしていたのは、若者就労支援における伴走者としてのボランティア・サポーターだった。半日のセミナーが三回、一泊二日の宿泊セミナー、一回に参加して、担当の若者をひとり受け持ち、半年の間にその若者を就労へと伴走する。それが年に二回。若者はたしかにそれぞれの困難を抱えているのだが、若者への思いがあれば難しいことではないし、そんなに大変でもない…。
米山はそう伝え、ボランティア・サポーターに勧誘するのだが、「時間的に難しい」「ひきこもりの若者の面倒をひとりで見るなんて、責任が重すぎる」と断られるばかりだった。
〜中略〜
そこで、米山は方針を変えることにした。
「伴走型支援には参加しなくてもいい。メーリングリストを受け取るだけで構わないから、ボランティア・サポーターに登録してくれませんか?」
こういう誘いなら、誰もがOKしてくれた。そして、ボランティア・サポーターはどんどんと増えていった。
増えつづけるボランティア・サポーターに、米山たちスタッフは、メーリングリストを通じて積極的に情報を流していった。
〜中略〜
中学の体操着が買えない家庭のために譲ってくれる人はいないか、ひきこもりだった若者が働く練習となるようなアルバイトを知らないか、進学したい若者のために小論文を添削してくれないか、シングルマザーのために子どもを乗せられる自転車を譲ってくれないか。
「働けなくて困っている若者のことも、生活困窮のことも知らない人がほとんどだったけれど、こういう人たちが僕たちの住んでいる地域にいて、実際に困っているという情報だけでも届けたかった」
米山はこんなふうに言う。
〜中略〜
ひとりの悩みや困りごとをオープンにし、複数の出会いをつくり出す。こうすることで、青年は何人ものボランティア・サポーターと知り合うことができる。そして、ボランティア・サポーターも新たな人と知り合う機会を得られる。
「ボランティア・サポーター自身がやりたいと思うことなら、別に就労支援とは関係がない催しをやるのでもいい。それによって、”ここに来ればやりたいことができる”と思ってくれればそれでいい」
津富理事長は言う。たしかに、大人になると、仕事と家庭の往復になってしまい、出会いの範囲は狭まるものだ。そのなかで、自分のやりたいことを一緒にやってくれる仲間、それも世代や環境のちがう仲間を地域のなかで見つけるのは至難の業だ。しかし、ボランティア・サポーターのネットワークが「多様な出会いが生まれる場所」になれば、魅力を感じた人が自ら近づいてくる。
そして、仲間をつくり、動き出す。
有償ボランティアがほかのボランティア・サポーターの強みを熟知し、さまざまなイベントや催しを繰り出しながら、ボランティア・サポーター同士のつながりをつくり出していく。すると、ボランティア・サポーターの活動は、有償ボランティアが関わらなくても、自然発生的に広がっていくのだ。
津富宏, 青少年就労支援ネットワーク静岡 編著. 生活困窮者自立支援も「静岡方式」で行こう!! 2, クリエイツかもがわ, 2017.11. pp37-4
引用が長くなりましたが、ボランティアは“ボランティアだからこそ”の良さがあると、私はこの文章を読んで感じました。
たとえば、自分の好きなペースで、好きなことをできる。
“やらされる”のではなく、「やりたいからやる」からこそ続けられる。
そして、静岡方式のボランティアの様子を見ていると、そこにはもう「支援する人/される人」という境界線があまりないような気がします。
困ったことがあれば、誰でも気軽に相談できる。
助けてもらった人が、今度は誰かを助ける。
そうやって、「ここに来ればなんとかなる」という場を知れることが、ボランティアにとってのメリットなんじゃないかなと思いました。
場所を持たなくてもいい
もうひとつ驚いたのが、「活動拠点を持たなくてもいい」という考え方です。沼津市自立相談支援センターセンター長・NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡 東部代表(2017年11月時点)の米山世紀さんによると、
この場所があることはありがたいですけれど、極端なことを言えば、「場」「拠点」といったオフィス的なものは不要です。居場所がほしいならどこかにつくればいいし、電話は転送して、取れるボランティア・サポーターが取ればいいんです。もっと言ってしまえば、自立相談支援センターがなくなったとしても、地域で困りごとが解決されるならそれでいいと思っています。そうなれば、うちのNPOだって役割を終えて解散ですよ(笑)。
津富宏, 青少年就労支援ネットワーク静岡 編著. 生活困窮者自立支援も「静岡方式」で行こう!! 2, クリエイツかもがわ, 2017.11. p48
静岡方式を進めている青少年就労支援ネットワーク静岡は、あえて「組織っぽくならないこと」を大切にしているのかな?と思います。なぜなら、きちんとした組織になればなるほど、助成金や行政との契約に縛られてしまうからです。書類やルールが増えれば、「支援のための支援」になってしまい、本来の柔軟さが失われてしまいます。
上記のように、静岡方式のスタッフはほとんどがボランティアです。組織化が進みすぎると、「仕事だからやらなきゃ」という義務感に変わりがちですが、静岡方式はやりたい人が、やりたいことを持ち寄る場であり続けようとしています。
さらに、組織化しないことで、「支援する側」と「される側」を分けない空気が保たれています。静岡方式は上下関係ではなく、ネットワークのような横のつながりで成り立っています。
静岡方式は、必要なときに必要な人が関わり、誰かのやりたいことから動き出す、ゆるいネットワークだからこそ、ここまで広がってきたのかもしれません。
静岡方式が目指す、相互扶助の世界とは?
本を読んで強く感じたのは、静岡方式のゴールは「みんなを就職させること」じゃないということ。助けてもらった人が、今度は誰かを助ける。そうやって助け合いが当たり前の世界を作っていくのが、静岡方式の本当の目標なのかもしれません。
だから静岡方式は、人の弱さを前提にして、「助け合い」で生きていける社会をつくることを目指しています。
静岡方式による就労支援に参加することは、相談者(働きたいけど働けない人)にとっても、相談者を応援するボランティア・サポーターにとっても、地域の相互扶助ネットワークに入り、誰かを支え、誰かに支えられるための入り口なのです。
滋賀県には既に「滋賀方式」がある
本を読み終えて思ったのは、滋賀県にも、名前はついていないけれど、地域をベースにした相互扶助は、既にたくさんあるのではないか?ということです。
たとえば、地元の人が声をかけあって野菜を分け合ったり、子どもを一緒に見守ったり、ちょっと困ったときに助けてもらえる関係。そういう日常の中に、「滋賀方式」と呼んでもいいような、小さな助け合いがたくさん隠れている気がします。
それは大きな制度や仕組みの名前がついていなくても、確かにそこで暮らす人を支えているものです。静岡方式の本を読んだことで、私は改めて滋賀の中にある、そうした名前のない助け合いに目を向けたくなりました。
もしかしたら、これからやるべきことは、ゼロから何かを作ることじゃなく、もうある関係を見つけて、つなぎ直すことなのかもしれません。静岡方式の学びをきっかけに、滋賀でできることを考えていきたいなと思いました。